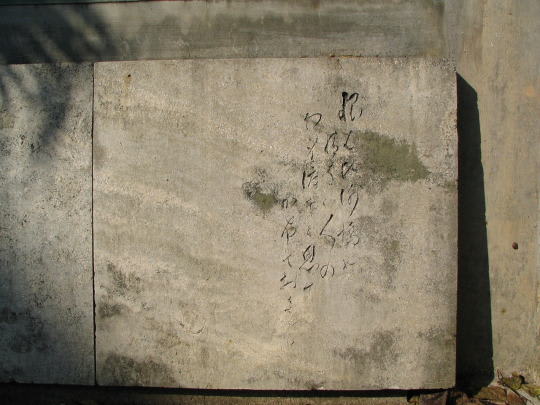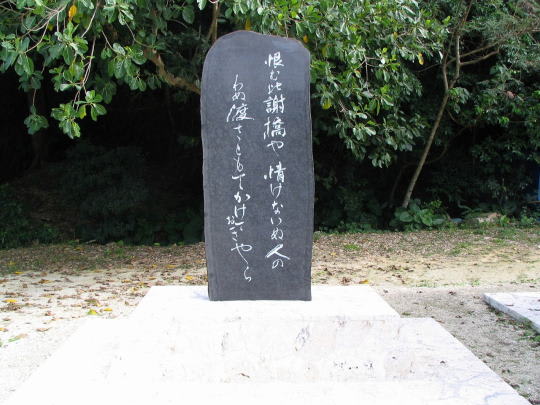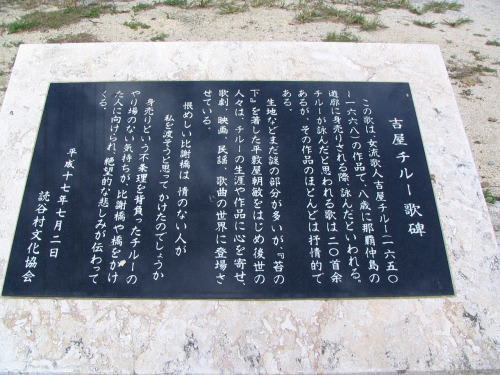奥武山公園駅 ( おうのやまこうえんえき )

奥武山公園駅の近くにある 「 沖縄セルラースタジアム 」
壷川駅⇒奥武山公園駅の間で流れる車内メロディーは 「 じんじん 」 である。
1
じんじん じんじん 酒屋ぬみじくゎてぃ うてぃりよー じんじん さがりよー じんじん
(ホタル ホタル 酒屋の水を喰って 落ちろよ ホタル 下がれよ ホタル)
2
じんじん じんじん 壷屋ぬみじぬでぃ うてぃりよー じんじん さがりよー じんじん
(ホタル ホタル 壷屋の水を飲んで 落ちろよ ホタル 下がれよ ホタル)
3
じんじん じんじん 久茂地ぬみじぬでぃ うてぃりよー じんじん さがりよー じんじん
(ホタル ホタル 久茂地の水を飲んで 落ちろよ ホタル 下がれよ ホタル)
「じんじん」は沖縄の幼児語の方言 ”ホタル”の意味。
沖縄の方言でホタルは 「じーなー」
「うてぃり」は ”落ちろ”
「さがり」は ”下がれ”
壷屋、久茂地は那覇の地名で、繁華街にあり、
久茂地 ( くもじ ) は、県庁付近で、
壷屋は、やちむん ( 焼物 ) で有名な場所である。