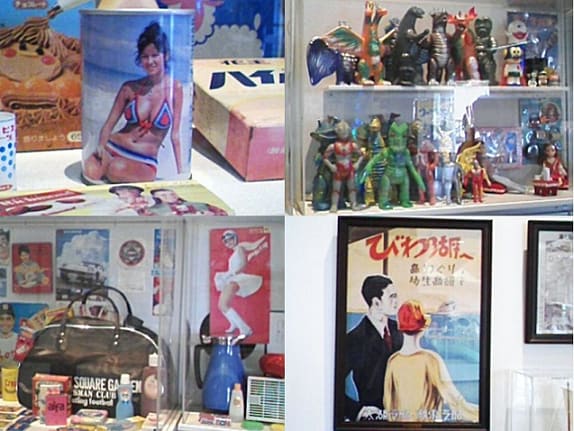自分の目で見た、津幡町に関するごく短いニュースの不定期通信。
今回は、改装にまつわる2篇。
【セブンイレブン、お色直しでいい気分。】

きのう「セブンイレブン津幡横浜店」が、リニューアルオープンした。
かなり大掛かりだったようで、昨年末から長期に亘る工事だった。

駐車場スペースが広くなって、道路からも入りやすくなった印象。
再開初日という事もあり、来客多し。
僕も店内のマルチコピーで競艇予想誌を買い求めた。
おめでたいタイミングにあやかり、こちらも幸運が訪れるといいな(笑)。
【板壁、三代。】
拙ブログにも度々登場している、津幡町の造り酒屋「久世酒造」。
その蔵を覆う板壁が、一部、新しくなっていた。

3つの色違いが分かるだろうか?
画像左が、最近のもの。
真ん中が、それ以前のもの。
画像右が、更に以前のもの。
斜めからも撮ってみた。

板壁の耐用年数はどの位なのか?
気象条件にもよるだろうし、木材の質にもよるが、
厚みのある板だから20年は固いだろう。
…とすると、古い壁は昭和から蔵を守ってきたのかもしれない。
<津幡短信vol.29>
今回は、改装にまつわる2篇。
【セブンイレブン、お色直しでいい気分。】

きのう「セブンイレブン津幡横浜店」が、リニューアルオープンした。
かなり大掛かりだったようで、昨年末から長期に亘る工事だった。

駐車場スペースが広くなって、道路からも入りやすくなった印象。
再開初日という事もあり、来客多し。
僕も店内のマルチコピーで競艇予想誌を買い求めた。
おめでたいタイミングにあやかり、こちらも幸運が訪れるといいな(笑)。
【板壁、三代。】
拙ブログにも度々登場している、津幡町の造り酒屋「久世酒造」。
その蔵を覆う板壁が、一部、新しくなっていた。

3つの色違いが分かるだろうか?
画像左が、最近のもの。
真ん中が、それ以前のもの。
画像右が、更に以前のもの。
斜めからも撮ってみた。

板壁の耐用年数はどの位なのか?
気象条件にもよるだろうし、木材の質にもよるが、
厚みのある板だから20年は固いだろう。
…とすると、古い壁は昭和から蔵を守ってきたのかもしれない。
<津幡短信vol.29>