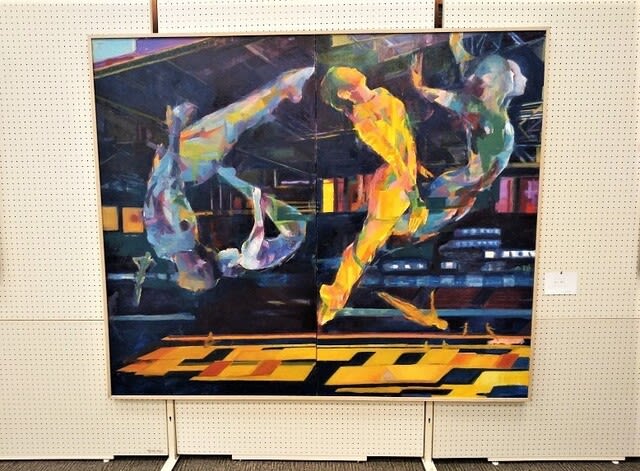きのう(2022/06/24)石川県内にフェーン現象が発生。
各所で35℃を超え、今年初めての猛暑日となった。
加えて、加賀で70ミリ、能登で50ミリの雨が降り、
蒸し暑く寝苦しい夜を過ごした。

それから一転。
今日は朝から快晴に恵まれ暑くなっているものの
湿度が、きのう程じゃないのが救いである。
気象庁が先日発表した1ヶ月予報によれば、
向こうひと月の降水量は、北日本と沖縄・奄美では「ほぼ平年並み」。
一方、東・西日本では「平年並みか少ない」らしい。
ここ北陸も、梅雨前線や湿った空気の影響を受けにくく、
梅雨明けが早まる可能性が高まったかもしれない。
大雨は困りものだが、少雨もまた同じ。
やはりレイニーシーズンは、それなりであってもらいたいのである。

さて、そんな「雨乞い気分」に浸っていると、ある曲のタイトルが思い浮かんだ。
「Creedence Clearwater Revival」のナンバー
「Have You Ever Seen the Rain(邦題:雨を見たかい)」。
有名な作品だから、ファンならずとも聴き覚えがあるかもしれない。
サビの歌詞---
“I want to know, have you ever seen the rain
(知りたいんだ、雨を見たことあるかい?)
Coming down on a sunny day”
(晴れた日に、空から降り注ぐ雨を)
--- この「雨」は「暗喩」だとする説がある。
曲がリリースされた70年代初頭は、ベトナム戦争のさ中。
つまり晴天に降る雨は、米軍がジャングルに落としている「ナパーム弾」だと、
当時、多くのリスナーが捉えた。
制作者は否定しているが、時代はそうは思わず、
反戦のメッセージを重ね合わせて、耳を傾けた。
折しも、ロシアがウクライナへ軍事侵攻に踏み切って(2022/02/24~)から、
丸4ヶ月が経った。
この機会に、反戦のメッセージを重ね合わせ耳を傾けてみてはいかがだろうか。
Have you ever seen the rain CCR Vietnam combat footage
Someone told me long ago
(ずいぶん前、誰かが言ってた)
There’s a calm before the storm
(嵐の前は静かになるものだって)
I know and it’s been coming for some time
(このところ、そんな気配がしていたんだ)
When it’s over so they say
(さらにあいつ等はこうも言う)
It’ll rain a sunny day
(晴れた日にも雨は降る)
I know shinin’ down like water
(閃光が雨水のように降り注ぐと)
I want to know, have you ever seen the rain
(知りたいんだ、雨を見たことあるかい?)
I want to know, have you ever seen the rain
(なあ教えてくれ、見たことあるんだろ?)
Coming down on a sunny day
(晴れた日に、空から降り注ぐ雨を)
Yesterday and days before
(昨日も、一昨日も、その前も)
Sun is cold and rain is hard
(陽の光は閉ざされ、雨は激しくなるばかり)
I know, been that way for all my time
(このところ、周りはいつもそんな感じなんだ)
Till forever on it goes
(どこまでゆけば終わりが見えるのか)
Through the circle fast and slow
(速くなったり、遅くなったりするけど、結局堂々巡り)
I know, and I can’t stop my wonder
(まったくもって不可解だけど、何も変わらない)
I want to know, have you ever seen the rain
(知りたいんだ、雨を見たことあるかい?)
I want to know, have you ever seen the rain
(なあ教えてくれ、見たことあるんだろ?)
Coming down on a sunny day
(晴れた日に、空から降り注ぐ光の雨を)
<作詞作曲:John Fogerty /意訳:りくすけ>

想像してみて欲しい。
貴方が暮らす町の空から、鉄と火薬、核の炎が降り注ぐ光景を。
そんなものは、誰も見たくないはずだ。