先月(2024/04)、僕は西美濃へ小旅行に出かけた。
訪問地の1つ、岐阜県・大垣市は「松尾芭蕉」が、有名な旅を終えた地である。
326年前のちょうど今時分。
元禄2年 旧暦3月27日に門人を伴い江戸深川を出発した「芭蕉」は、
関東~東北(奥州)~北陸と、和歌の題材になった名所・旧跡「歌枕」を訪ね歩いた。
およそ150日間、2,400kmに亘る大旅行の紀行文が『奥の細道』。
そこに収められた60余りの歌の幾つかは、
発表から長い時を経た今日(こんちに)でも、容易に思い浮かべることができる。
『夏草や 兵どもが 夢のあと』
(なつくさや つわものどもが ゆめのあと)
『閑さや 岩にしみ入る 蝉の声』
(しずかさや いわにしみいる せみのこえ)
『五月雨を あつめて早し 最上川』
(さみだれを あつめてはやし もがみがわ)
『無残やな 甲の下の きりぎりす』
(むざんやな かぶとのしたの きりぎりす)
個人的には、序文冒頭も忘れ難い。
『月日は百代の過客にして 行き交ふ年もまた旅人なり
船の上に生涯を浮かべ 馬の口とらへて老いを迎ふる者は
日々旅にして旅を栖(すみか)とす
古人も多く旅に死せるあり』
時は永遠の旅人。
歩みを止めず巡る季節も旅人だ。
一生の殆どを水の上に浮かべて過ごす船頭、
馬のくつわを引くうちに老いてゆく馬子などは、毎日が旅そのもの。
彼らにとって旅はねぐらである。
未練を残し道半ばで倒れた先人達の例を引き合いに出すまでもなく、
人生はゴールのない旅のようなものかもしれない。
(※現代意訳/りくすけ)
--- とまあ、少々拡大が過ぎる気もするが、ずい分若き日にそう解釈をした僕は、
「旅の空の下で死ぬ自分」にヒロイックな憧れを抱いたりした。
オッサンになって思い返せば面映い限りである--- 。
さて、後の人々が「松尾芭蕉」に冠した称号は“俳聖”。
“古今に並ぶ者のない俳句の大名人”だ。
そう聞くと近寄り難い印象かもしれないが、出自は庶民階級。
伊賀上野(現/三重県・伊賀市)の下級武士(実態はほゞ農民)の次男で、
城主に仕え俳諧の心得を学び、文芸で身を立てようと大都会・江戸へ出た。
まだ、俳句は歴史の浅い新ジャンル。
いわば「芭蕉」は、地方出身のハングリーな前衛芸術家だったとも言える。
日本橋に居を構え、様々な俳人と交流を持ち句会の審査員や指導をする傍ら、
土木工事などに従事して糊口をしのぎつつ腕を磨いた。
およそ6年間の下積み生活後、見事、宗匠(そうしょう/師匠格)になる。
いよいよ大活躍か!?--- と思いきや、せっかく手に入れた地位を捨て、
草深い江戸の外れへ転居し粗末なあばら家に籠る「芭蕉」。
世俗と距離を保ち、自然に包まれ、時の流れに身を任せ、
やがて心眼に映る「風流」をこう詠んだ。
『古池や 蛙飛びこむ 水のおと』
(ふるいけや かわずとびこむ みずのおと)
当時の俳壇の主流は、複数人が即興で歌を連ねてゆく言葉遊び、洒落、笑いなど。
それとは明らかに一線を画していた。
古典の美と身辺の日常を重ね合わせ、十七音の向うにある世界を考えたくなる詩的な表現。
独自のスタイル「蕉風」を確立。
そして彼は創作の旅を重ね、各地に多くのフォロワーを生んでいった。
では、ここからはアーティスト人生集大成となった紀行文『奥の細道』から、
俳聖の人間味が窺える一作にスポットを当ててみたい。
ほんの手すさび 手慰み。
不定期イラスト連載 第二百三十五弾「市振(いちぶり)にて」。

『一家に 遊女もねたり 萩と月』
(ひとつやに ゆうじょもねたり はぎとつき)
『奥の細道』には、この句に関する挿話が綴られている。
暑さに焼かれ、雨に打たれながら北陸街道の難所を越え、
ようやく辿り着いた「市振の関」(現/新潟県・糸魚川市・市振)。
疲れ果てた「芭蕉」は草鞋を脱ぎ、早々床に就いたが、
隣から聞こえてきた年老いた男と2人の若い女の会話が気になった。
女はどうやら越後の遊女。
一夜の契りを重ねる罪深い暮らしを嘆き、前世の因果応報を憂いているようだ。
その話を耳にしながら「芭蕉」はいつしか寝入ってしまうのだった。
夜が明けて支度をしていると、遊女たちが涙ながらに頼み込んでくる。
女だけの旅は心細い。
後追いで構わないから、随行させてもらえないだろうか。
気の毒に思わないではなかったが、所々で滞在することも多いからと申し出を辞退。
歩き始めたものの、後ろ髪を引かれる気持ちが残り一句を創った。
--- という事らしい。
名所旧跡「歌枕」以外を題材にした句は、どことなく艶っぽい。
耳をくすぐる襖越しの声。
未練を残した早朝の別れ。
袖触れ合った遊女は、容姿端麗だったのではないかと空想してしまう。
俳聖といえど美人に弱く、人情にほだされ、人恋しい男の顔が垣間見えるのだ。
そもそもこのエピソード、
「芭蕉」に帯同した弟子の日記に記録がないことから、フィクションとも考えられている。
楽しくも苦しみ多い旅に、作者が添えた「彩り」かもしれない。
季語は秋の七草の一つ「萩」。
また一語だけの「月」も秋の月を指す。
地球と38万km離れて寄り添う大きな天体は、夜空が澄む秋こそ存在感が増すからだ。
2つ以上の季語が同居する「季重なり」の訳は何だろう?
季節感を強調している。
萩と月が主従の対を成している。
そんな捉え方もできるが、個人的には遊女の「境遇」を表していると考える。
燃えたぎる発光体が空を支配する日中(ひなか)より、
清光を放つ反射体が宙に浮かぶ時間、夜の方が似合う。
また、小さな蝶に似たつつましく美しい萩の花も、
影を纏う女性にしっくりくるのだ。
西美濃への小旅行に起因する「芭蕉」関連投稿は続く。
同カテゴリーの次回をお楽しみに!
<付 記>
「芭蕉」が活躍した江戸時代、
5・7・5のリズムで編んだ十七音の短文定型詩は「俳諧」と言われていた。
「俳句」と呼び名を変えるのは明治以降なのだが、
今投稿は読み易さを考慮優先し「俳句」で統一した。










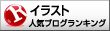


















コメントありがとうございます。
今回のブログ、数あるりくすけさんのブログの中でも、珠玉の投稿ですね。
>時は永遠の旅人。
>歩みを止めず巡る季節も旅人だ。
>一生の殆どを水の上に浮かべて過ごす船頭、
>馬のくつわを引くうちに老いてゆく馬子などは、>毎日が旅そのもの。
>彼らにとって旅はねぐらである。
>未練を残し道半ばで倒れた先人達の例を引き合いに出すまでもなく、
>人生はゴールのない旅のようなものかもしれない。
僕のブログの副題、「日常の中に旅があり、旅の中に日常がある。僕たちは、旅の途上。」にも通じる気がします。
素晴らしい!
では、また
貴新設ブログへの移行、
速やかに進むことをお祈りいたします。
今後ともどうぞよしなに。
また拙文へ過分なお褒めを与り恐縮です。
僕の拡大解釈した現代訳はさることながら、
「芭蕉」さんの原文の素晴らしさが
貴方様の琴線に触れたなら幸いです。
続篇も投稿します。
また、都合と時間が許せば読んでやって下さいませ。
では、また。