私は東京郊外の調布市に住む年金生活の69歳の身であるが、
ここ3日、敬愛している作家のひとりの嵐山光三郎(あらしやま・こうざぶろう)さんが、
60代の時、ご両親の晩年を記した2冊の本を再読している・・。
嵐山光三郎さんは、1942年(昭和17年)1月に生を受けられ、
やがて1965年(昭和41年)に國學院大學文学部国文科卒業され、専攻は中世文学であり、
在学中の講師として丸谷才一、安東次男らに学んだひとりである。
この直後、平凡社に入社されて、編集者として奮闘されながら、
やがて『別冊太陽』と『太陽』のそれぞれ編集長に抜擢された後、
この後は、散漫経営のため平凡社が経営危機となった1981年(昭和56年)に退社され、
出販社を設立されたりする中で、編集者、作家としてもご活躍された。
この後は、 1987年(昭和62年)に『素人庖丁記』で翌年に第4回講談社エッセイ受賞、
その後も俳諧の分野も含めて、多彩な分野の数多くの本を上梓されている。
そして2006年(平成18年)に『悪党芭蕉』を上梓され、第34回泉鏡花文学賞、
翌年には第58回読売文学賞を受賞された現代作家の第一人者お方である・・。
私は氏の少なくとも100作品以上の中で、30冊ぐらい購読してきた愛読者ひとりであるが、
今回、再読しているは『よろしく』(初出:集英社, 2006.10 )、
そして『おはよう!ヨシ子さん』(初出:新講社, 2008.7)である。

私が嵐山光三郎・著の『よろしく』を遅ればせながら読んだのは、確か2010年(平成22年)の6月であった。
たまたま駅前の本屋で、氏の『よろしく』(集英社文庫)を見かけ、購読した。
この本の内容紹介には、
《・・コロコロと死んでゆくのが人生だ。
人は「よろしく」と現れ「よろしく」と去っていく――
介護・死・老いらくの恋といった深刻で厄介なテーマを、ユーモラスに描く小説。
物語を追いながら自分自身の死に方について、考えさせられる。・・》と明記されている。
あとがきに明記されているが、
本書の初出は2006年10月、集英社より刊行された本であり、
著作者は2001年前後の60歳前後の当時、創作を精力的に専念し、
体力の衰えも感じながらも、自身の学生時代の学友や知人が突然に亡くなったり、
街中の隣人や知人の死去を知り、驚きとため息の中で過ごされている。
こうした中で、父親が高齢者85歳となり、ボケはじめて、
母親は80歳の体力の衰えた身であるので、
やむえず老人介護施設に父親は入居し、その後まもなく悪化し、
病院で親族一同の涙ぐましい介護に関わらず、
死去され、葬儀などを得て、新盆を迎えるまでの著作者の自伝でもある。
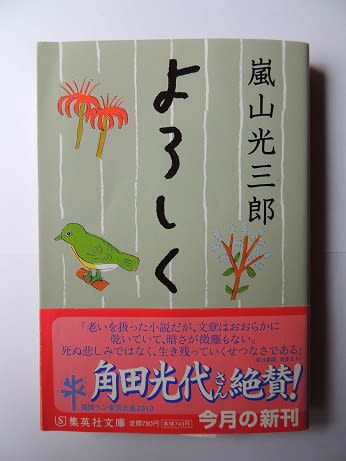
私は最初に読了後、身につまされたひとりである。
私達夫婦は子供に恵まれず、たったふたりだけの家族であり、
この当時の私は65歳を過ぎた高齢者となり、家内も60歳の年金受給者となっている。
そして私の父親は私が小学2年の時に病死され、
母親は私がサラリーマン現役の54歳の時に死去された。
やがて家内の父親は、私が60歳を過ぎ定年退職時の直前に病死され、
家内の母親は80歳なり、独り住まいをしている。
こうした私の背景もあり、私達夫婦の今後の更なる老後の生活を思いながらも、
この本を読みながられ、多々教示をされたりしていたのである・・。
たとえば、男性の後期高齢者80歳となれば、
《・・(父親)ノブちゃんは85歳である。
ノブちゃんはT美術大学教授をしていた。
グラフィック・デザイン科科長をつとめて、70歳でやめた。
ぼくより背が高く、筋肉隆々としていたが、
80歳をすぎたころより痩せて、すすきの穂のようになった。
昔からおしゃれな人で、服の着こなしがダンディーであった。
(略)
それが、ここ一、二年というもの、洋服にかまわなくなった。・・》
注)本書のページ16の一部を引用し、あえて改行も多くした。
或いは、著作者の母親は句会などに参加し、日常は俳句を詠んだりする方が、
80歳となれば、
《・・トシ子さんが、
「歩くと雲の上を歩くようにフラフラする」と言う。
T川厚生年金病院のめまい科へ受診に行くと、女医に、
「あんたぐらいのローバなら、みんなフラフラしていますよ」
と叱られたらしい。・・》
注)本書のページ31の一部を引用し、あえて改行も多くした。
そして父親がボケはじめ高齢の母親に手が終えなくなり、
父親が老人介護施設に入った初めの頃、
《・・施設庁長が、「福祉の精神より、まず接客技術をモットーとしております」と言った。
すべてを高齢者本人の身になって考えることが基本であるという。
たとえば、痴呆の高齢者の夫が妻の顔を忘れてしまうケースがある。
「その場合、つぎの三つのうちどれが正しいでしょう」と質問された。
(1)妻であることを根気よく説得する。
(2)結婚式の写真などを見せて納得させる。
(3)あきらめてニコニコする。
このうち(1)や(2)は、高齢者本人がかかえる問題の解決とはなりません。
夫に顔を忘れられても、ニコニコと笑って
「どこかの親切な人」としてふるまうのがいいのです、と教えられた。
「三つの選択肢のなかで一番いけないのは(2)です。
こんなことされたら、夫は逃げ道を失って、屈辱感を味わうだけですから。
失望した顔をすると、本人は傷つきます」
ノブちゃんは、まだそこまではぼけていない。
話す内容は理路整然としている。でありながら思考のネジがはずれている。・・》
注)本書のページ95の一部を引用し、あえて改行も多くした。

このようなことを多々、私は教示されたりしたが、
何よりの驚きは老人介護施設に入居されている人たちの日常の言動であった。
それぞれのお方の晩年のふるまい、しぐさ、そして突然の死去など、多々綴られているが、
私は、たとえ現役時代に立派な人と敬(うや)まれる方でも、老後は・・、
とため息を重ねながら、ここでは書けないのである。
このことは、本書を読まれた方の特権と思い、本書をお読み下さい。
昨今、高齢者に関しての実用書がブームときいたりしているが、
この本書こそ、著作者が父親の介護に、生活を共にし、
父親の思い、母親の見つめる思い、著作者の死生観まで明確で、
くまなく綴られ、それぞれの方たちの人生の晩節の生きた哲学書ともいえる。

もうひとつの嵐山光三郎・著の『おはよう! ヨシ子さん』は、
私が2009年(平成21年)7月に、やはり本屋で見かけて購読した本である。
この解説文に明示されている通り、
今回は著作者の母上で「ヨシ子さん」と称した91歳のご高齢(作品発表時)、
著作者自身も66歳(作品発表時)で、 同じ敷地の別棟で暮らし、過ごされている。
母上はご高齢の日常生活に於いて、
《・・記憶力はまあ半分ぐらいはちゃんとしているほうだが、耳は遠く、体力がついていかない。
頭はしっかりしているのに、体が言うことを聞かない。
箸1本が重く、リンゴひとつ持つのがやっとである。
ヨシ子さんが俳句を詠もうとする念力が、生きる力を呼びおこす。
なにか題材を見つけるために、夕方は、杖をついて散歩に出る。
フーラフラとした蚊トンボみたいな散歩で、見ちゃいられない気もするけれど、
散歩を休むと、かえって体調が崩れる。
ヨシ子さんは、俳句で生きている。(略)・・》
注)原文(ページ64)より引用したが、あえて改行を多くした。
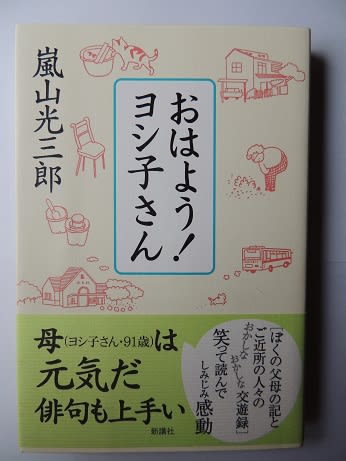
このようにご子息の著者の視線から、母上のヨシ子さんを見守り、
そして、 せっかちだったという著者の父、ヨシ子さんの夫はすでになく、
ヨシ子さんは小さな仏壇に毎朝花と御飯を供え、毎日俳句を詠み、
それを毎日見ていた著者は、ヨシ子さんの詠む俳句を毎日「相談にのっている」情景が主軸で、
さりげない日常が描かれている。
そして著者はご高齢のさりげない日常を優しいまなざしで描かれ、
父上の思いで、そして弟ふたりとの交流と過去の出来事を綴られ、
ヨシ子さんの家族の軌跡として重ねている。
淡々と日常生活の母上と著者自身の周辺の出来事を加味され、
私なりに多々教示を受けたのである。
この本を初めて読んだのは、私が64歳の時で、
改めてご高齢のご婦人の日常の思い、願いはこうであったのかしら、
そして著者自身の日常の思索、ふるまい等である。

このように著者が60代の時、ご両親の晩年を記した2冊の本を、
私はそれぞれの晩年の生きた教科書と思いながら、再読しているである。
☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪
 にほんブログ村
にほんブログ村

ここ3日、敬愛している作家のひとりの嵐山光三郎(あらしやま・こうざぶろう)さんが、
60代の時、ご両親の晩年を記した2冊の本を再読している・・。
嵐山光三郎さんは、1942年(昭和17年)1月に生を受けられ、
やがて1965年(昭和41年)に國學院大學文学部国文科卒業され、専攻は中世文学であり、
在学中の講師として丸谷才一、安東次男らに学んだひとりである。
この直後、平凡社に入社されて、編集者として奮闘されながら、
やがて『別冊太陽』と『太陽』のそれぞれ編集長に抜擢された後、
この後は、散漫経営のため平凡社が経営危機となった1981年(昭和56年)に退社され、
出販社を設立されたりする中で、編集者、作家としてもご活躍された。
この後は、 1987年(昭和62年)に『素人庖丁記』で翌年に第4回講談社エッセイ受賞、
その後も俳諧の分野も含めて、多彩な分野の数多くの本を上梓されている。
そして2006年(平成18年)に『悪党芭蕉』を上梓され、第34回泉鏡花文学賞、
翌年には第58回読売文学賞を受賞された現代作家の第一人者お方である・・。
私は氏の少なくとも100作品以上の中で、30冊ぐらい購読してきた愛読者ひとりであるが、
今回、再読しているは『よろしく』(初出:集英社, 2006.10 )、
そして『おはよう!ヨシ子さん』(初出:新講社, 2008.7)である。

私が嵐山光三郎・著の『よろしく』を遅ればせながら読んだのは、確か2010年(平成22年)の6月であった。
たまたま駅前の本屋で、氏の『よろしく』(集英社文庫)を見かけ、購読した。
この本の内容紹介には、
《・・コロコロと死んでゆくのが人生だ。
人は「よろしく」と現れ「よろしく」と去っていく――
介護・死・老いらくの恋といった深刻で厄介なテーマを、ユーモラスに描く小説。
物語を追いながら自分自身の死に方について、考えさせられる。・・》と明記されている。
あとがきに明記されているが、
本書の初出は2006年10月、集英社より刊行された本であり、
著作者は2001年前後の60歳前後の当時、創作を精力的に専念し、
体力の衰えも感じながらも、自身の学生時代の学友や知人が突然に亡くなったり、
街中の隣人や知人の死去を知り、驚きとため息の中で過ごされている。
こうした中で、父親が高齢者85歳となり、ボケはじめて、
母親は80歳の体力の衰えた身であるので、
やむえず老人介護施設に父親は入居し、その後まもなく悪化し、
病院で親族一同の涙ぐましい介護に関わらず、
死去され、葬儀などを得て、新盆を迎えるまでの著作者の自伝でもある。
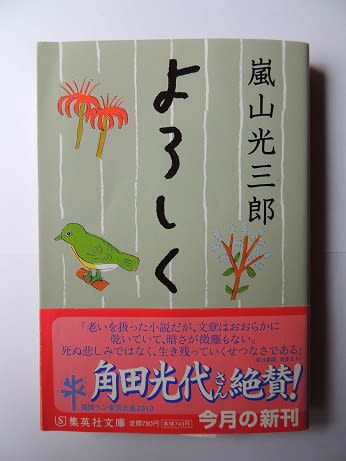
私は最初に読了後、身につまされたひとりである。
私達夫婦は子供に恵まれず、たったふたりだけの家族であり、
この当時の私は65歳を過ぎた高齢者となり、家内も60歳の年金受給者となっている。
そして私の父親は私が小学2年の時に病死され、
母親は私がサラリーマン現役の54歳の時に死去された。
やがて家内の父親は、私が60歳を過ぎ定年退職時の直前に病死され、
家内の母親は80歳なり、独り住まいをしている。
こうした私の背景もあり、私達夫婦の今後の更なる老後の生活を思いながらも、
この本を読みながられ、多々教示をされたりしていたのである・・。
たとえば、男性の後期高齢者80歳となれば、
《・・(父親)ノブちゃんは85歳である。
ノブちゃんはT美術大学教授をしていた。
グラフィック・デザイン科科長をつとめて、70歳でやめた。
ぼくより背が高く、筋肉隆々としていたが、
80歳をすぎたころより痩せて、すすきの穂のようになった。
昔からおしゃれな人で、服の着こなしがダンディーであった。
(略)
それが、ここ一、二年というもの、洋服にかまわなくなった。・・》
注)本書のページ16の一部を引用し、あえて改行も多くした。
或いは、著作者の母親は句会などに参加し、日常は俳句を詠んだりする方が、
80歳となれば、
《・・トシ子さんが、
「歩くと雲の上を歩くようにフラフラする」と言う。
T川厚生年金病院のめまい科へ受診に行くと、女医に、
「あんたぐらいのローバなら、みんなフラフラしていますよ」
と叱られたらしい。・・》
注)本書のページ31の一部を引用し、あえて改行も多くした。
そして父親がボケはじめ高齢の母親に手が終えなくなり、
父親が老人介護施設に入った初めの頃、
《・・施設庁長が、「福祉の精神より、まず接客技術をモットーとしております」と言った。
すべてを高齢者本人の身になって考えることが基本であるという。
たとえば、痴呆の高齢者の夫が妻の顔を忘れてしまうケースがある。
「その場合、つぎの三つのうちどれが正しいでしょう」と質問された。
(1)妻であることを根気よく説得する。
(2)結婚式の写真などを見せて納得させる。
(3)あきらめてニコニコする。
このうち(1)や(2)は、高齢者本人がかかえる問題の解決とはなりません。
夫に顔を忘れられても、ニコニコと笑って
「どこかの親切な人」としてふるまうのがいいのです、と教えられた。
「三つの選択肢のなかで一番いけないのは(2)です。
こんなことされたら、夫は逃げ道を失って、屈辱感を味わうだけですから。
失望した顔をすると、本人は傷つきます」
ノブちゃんは、まだそこまではぼけていない。
話す内容は理路整然としている。でありながら思考のネジがはずれている。・・》
注)本書のページ95の一部を引用し、あえて改行も多くした。

このようなことを多々、私は教示されたりしたが、
何よりの驚きは老人介護施設に入居されている人たちの日常の言動であった。
それぞれのお方の晩年のふるまい、しぐさ、そして突然の死去など、多々綴られているが、
私は、たとえ現役時代に立派な人と敬(うや)まれる方でも、老後は・・、
とため息を重ねながら、ここでは書けないのである。
このことは、本書を読まれた方の特権と思い、本書をお読み下さい。
昨今、高齢者に関しての実用書がブームときいたりしているが、
この本書こそ、著作者が父親の介護に、生活を共にし、
父親の思い、母親の見つめる思い、著作者の死生観まで明確で、
くまなく綴られ、それぞれの方たちの人生の晩節の生きた哲学書ともいえる。

もうひとつの嵐山光三郎・著の『おはよう! ヨシ子さん』は、
私が2009年(平成21年)7月に、やはり本屋で見かけて購読した本である。
この解説文に明示されている通り、
今回は著作者の母上で「ヨシ子さん」と称した91歳のご高齢(作品発表時)、
著作者自身も66歳(作品発表時)で、 同じ敷地の別棟で暮らし、過ごされている。
母上はご高齢の日常生活に於いて、
《・・記憶力はまあ半分ぐらいはちゃんとしているほうだが、耳は遠く、体力がついていかない。
頭はしっかりしているのに、体が言うことを聞かない。
箸1本が重く、リンゴひとつ持つのがやっとである。
ヨシ子さんが俳句を詠もうとする念力が、生きる力を呼びおこす。
なにか題材を見つけるために、夕方は、杖をついて散歩に出る。
フーラフラとした蚊トンボみたいな散歩で、見ちゃいられない気もするけれど、
散歩を休むと、かえって体調が崩れる。
ヨシ子さんは、俳句で生きている。(略)・・》
注)原文(ページ64)より引用したが、あえて改行を多くした。
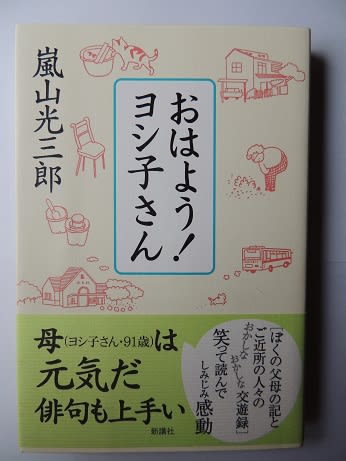
このようにご子息の著者の視線から、母上のヨシ子さんを見守り、
そして、 せっかちだったという著者の父、ヨシ子さんの夫はすでになく、
ヨシ子さんは小さな仏壇に毎朝花と御飯を供え、毎日俳句を詠み、
それを毎日見ていた著者は、ヨシ子さんの詠む俳句を毎日「相談にのっている」情景が主軸で、
さりげない日常が描かれている。
そして著者はご高齢のさりげない日常を優しいまなざしで描かれ、
父上の思いで、そして弟ふたりとの交流と過去の出来事を綴られ、
ヨシ子さんの家族の軌跡として重ねている。
淡々と日常生活の母上と著者自身の周辺の出来事を加味され、
私なりに多々教示を受けたのである。
この本を初めて読んだのは、私が64歳の時で、
改めてご高齢のご婦人の日常の思い、願いはこうであったのかしら、
そして著者自身の日常の思索、ふるまい等である。

このように著者が60代の時、ご両親の晩年を記した2冊の本を、
私はそれぞれの晩年の生きた教科書と思いながら、再読しているである。
☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪

















