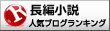人がもっとも怖(こわ)いもの・・それは見えないモノだ。その見えないモノが生物でなく、ただの物であれば、見えなくても取り分けて問題になることもない。ただ、そのモノが生物だと、大小にかかわらず厄介(やっかい)なことになる。どう厄介なのか? といえば、善悪を問わず勝手に動き回るからだ。善なる場合はいいが、悪の場合は相手が見えないのだからそれこそ厄介である。医学的には悪性の細胞やウイルス、悪霊などと呼ばれる憑依(ひょうい)霊的なモノ、犯罪者をそうさせる教唆(きょうさ)犯などがそうだ。この教唆犯も見えればいいが、魔と呼ばれる見えないモノの場合、益々、厄介だ。なにせ、魔は知的にありとあらゆる手段を駆使(くし)して人を困らせようとする。魔が刺した・・などと言う場合がそれで、出来るだけ刺さないで欲しいものだ。^^
とある宝くじ売り場の前である。一人の男がくじを買おうか買うまいか…と、立ち止まっている。
『いや、買わなけりゃ、たこ焼きが一舟、食えるぞ…』
そう思った男はトボトボと売り場から遠退(とおの)き始めた。ところが、しばらくすると、また立ち止まった。見えないモノがヒソヒソと囁(ささや)いたからだ。
『いやいや、当たりゃ、五万と食えるか…』
男はふたたび売り場の方へ戻(もど)り始めた。そして、財布を取り出したとき、またまた思った。
『いやいやいや、五万は食えんぞっ!』
男は、また売り場から遠退き始めた。そして、しばらくすると、ふたたび立ち止まった。
『いやいやいやいや、タコ焼き以外のモノなら鱈腹(たらふく)食えるか…』
男は、またまた売り場の方へ戻(もど)り始めた。
そうこうするうちに、日はとっぷりと暮れ、売り場のシャッターは閉じられた。
このように、見えないモノに魅入(みい)られると、それでも…と繰り返すことになり、目的が果たせなくなる訳だ。^^
完
過去の長閑(のどか)な時代では気にならなかったものが、現在のように生活が向上して複雑化すると、いろいろと気になり始める。安全性である。食品の安全性、ガス漏れの安全性、火災の安全性、耐震構造の安全性、通学の安全性、治療や投薬の安全性、機械の安全性・・などと枚挙(まいきょ)に暇(いとま)がない。よぉ~~~く考えれば、完璧(かんぺき)に安全なものなど、この世には存在しないのだが、それに気づかず、世間の人々は安全性を連呼(れんこ)する。最たる例が放射能の安全性だ。原子力発電が身近な問題として取り上げられているが、全然、取り上げられていないものもある。我が国は保有していないから関係ないが、原子力空母がそれである。確かに燃費コストは馬鹿安なのだろうが、安全性では如何(いかが)なものか? なのである。平和時はいいが、一端、戦闘で船体が損傷を受け、原子炉の放射能漏れでも起こせば、現在の放射性からして乗組員は全員、致命的にアウト! だろう。被爆して助かる余地は、ほぼない。こんな見過ごされがちな安全性もある訳だ。^^
夕闇が迫るとある、ふぐ専門店の店先である。二人の客が店の暖簾(のれん)を潜(くぐ)ろうとしていた。
「ここのは美味(うま)いんだよっ!」
「まあ、君が言うんだから間違いはないんだろうが…」
「と、いうと?」
「もちろん、安全性さっ!」
「安全性? ふぐ専門店の安全性を疑(うたぐ)っちゃ、お終(しま)いだぜ」
「そりゃまあ、そうだが…」
「そういや、この前のステーキ専門店でも狂牛病の・・とか言ってたな?」
「そうだったか?」
「ああ。鳥スキの店前でも鳥インフルエンザが人にも・・とか言ってたぞ」
「そうだったか?」
「ああ。そう言いながら、食べて美味かった。ただ、俺はお前の頭の安全性の方が心配だっ!」
「…」
言われた男は言葉をなくし、押し黙った。
安全性は、それでも! と気にしない方が、楽しく生活できるようだ。^^
完
誰しも、その本人に生まれ持って備わった力量(りきりょう)というものがある。その力量には個人差があり、小さい人から大きい人まで千差万別(せんさばんべつ)だ。力量が小さいにもかかわらず、それでもやろうとすれば、出来ないのだから当然、失敗したりダメにしてしまう訳だ。^^
ここは、とある会社の社長室である。室内には創業者である初代社長から先代社長に至る十数人の顔写真入りの額(がく)が所狭(ところせま)しと飾(かざ)られている。その額を見上げながら、社長が弱々しい声でボソッと独(ひと)りごちた。
「皆さん、力量があったんだな…」
社長がそう呟(つぶや)くのも無理からぬ話で、会社は経営の危機に瀕(ひん)していたのである。そのとき、専務がドアをノックした。
「社長! 専務ですっ! 入ってよろしいか?」
その声は、額を見上げる社長にも否応(いやおう)なく聞こえた。
「ああ、どうぞ…」
社長は、自分のことを普通、専務と言うかね? …と、思いながら返した。そして、専務が社長室に入ってきた途端、ふたたび、力量を見損(みそん)じたか…と思った。さらに、専務が軽く頭を下げた途端、会社が傾くのも当然か…と、自分の経営の力量のなさを痛感した。
力量を見損じ、それでも気づかないと、組織は傾いたり危機に瀕するのである。^^
完
物事をする場合、すぐやるタイプと、算段して…と、スケジュールを立てて行動するタイプの二通りに分かれる。すぐやるタイプは、そのまま放っておけない人によく見られるが、放っておけない性格が災(わざわ)いして、出来ないとそれでも続ける・・という状況に至(いた)ってしまう。出来ないものは出来ないのだから一端(いったん)やめて、スケジュールを組んだ後日、やればいい訳だが、それが出来ないのだ。こんな点から見ると、スケジュールは食物をよく咀嚼(そしゃく)[嚙(か)み砕(くだ)く]作業に似ていなくもない。よく噛めば、消化にも良く、栄養がスムースに体内へ吸収される。スケジュールを立てた後の実行は、よく嚙み砕くことと同じなのだ。^^
とある原っぱで二チームに分かれて草サッカーが行われている。草野球があるのだから、当然、草サッカーもある訳だ。^^ 正式なサッカー大会に向けた練習試合ということもあり、草サッカーながら本格的に熱が入っている。監督、コーチはスケジュールどおりチームの強化を計ってきたが、今日の試合がその集大成である。
「監督、どうなんですかね?」
「? なにが?」
「これで勝てますかね?」
「そらまあ、スケジュールどおり強化してきたんだから勝てるさ、ははは…」
自信なさげに監督がコーチに返す。
「なら、いいんですが…」
「スケジュールどおりなら祝勝会だな」
「はあ、まあ。スケジュールどおり勝てばっ! の話ですが…」
「負けた場合はっ?」
「負けた場合は負けた場合で、お疲れ会のスケジュールとなっております」
「勝ち負けはスケジュールどおりにはならんが、それでも勝ってもらいたいものだな、コーチ」
「はあ、それはもう…」
二人は試合の様子を見ながら、自分に言い聞かせるように頷(うなず訳だ)いた。
このように、スケジュールは安心面から言えば、それでも! と、立てておくに越したことはない訳だ。^^
完
なんでもあるに越したことはない。あれば、それを使って物事を成せばいいからだ。しかし、そういつも物がなんでもある・・ということはあり得ない。そうなると、あるものを工夫(くふう)して足らないものを補(おぎな)う知恵が要求される。その知恵の有りようは人によって違うから、工夫してコトが成るか成らないかは、そのときどきの個人の裁量(さいりょう)に委(ゆだ)ねられることになる。だから、工夫しない前の方がよかった…と言われることも当然、覚悟して工夫しなければならない。^^
とある都市のデバートである。定休日で客の出入りは皆無だが、店内はレイアウトの変更作業が急ピッチで進められていて人の動きで雑然としている。
「そこは、そのままでいいんじゃないか? 副店長」
「そうですかぁ~? 私は左横の陳列棚と入れ替えた方がいいと思うんですがね…」
「いやぁ~副店長、それじゃ工夫してレイアウトを変えた意味がないじゃないか、副店長」
店長は、ようやく念願の店長に昇格できたもんだから、自分の地位を誇示(こじ)するかのように副店長を連呼(れんこ)した。今まで自分が副店長だったことも忘れて、である。
「そうですか? 十分、工夫できたと思うんですが…」
「いや、そうは思えんが…」
それでも店長は言い張る。
「いいでしょ! 他の店員に訊(き)いてみましょう! その結果如何(けっかいかん)で考えられては、いかがですか?」
「おっ! それはナイス、アイデアっ!」
二人は勤務中の店員を集め、決を取った。結果は工夫した副店長に軍配(ぐんばい)が上がった。
それでも工夫する場合は決を取ったほうが賢明だ。^^
完
風の所為(せい)で風邪(かぜ)を引く・・とは上手(うま)く言ったものだ。漢字が示すとおり、風の邪(じゃ)、邪(よこしま)な風が吹いて体調を崩(くず)す・・ということである。それでも、初期のうちに気づいて処置をすれば、その邪悪(じゃあく)な風は、『チェッ! 他へ行くとするか…』などとブツクサ言いながら退散するから、それ以上に体調が悪くなる・・ということはない。^^
とある町のとある大衆食堂である。昼時(ひるどき)ということもあってか、大層(たいそう)賑(にぎ)わっている。
「へいっ! 木の芽ラーメン上がったよっ!!」
店奥から気前のいい声がする。その声に急(せ)かされたように若い女店員がトレーに二鉢(ふたはち)の木の芽ラーメンを乗せ、客が待つテーブルへと急ぐ。
「お待ちどおさま…」
二人の客は置かれた木の芽ラーメンをソソクサと食べ始める。そのとき、一人の客が思わずクシャミをした。
「どうした?」
「いや~、花粉が飛び始めたからでしょう…」
クシャミをした後輩風の男は、とりあえず花粉の所為にする。
「いやっ! それは風の所為だっ! 注意しろっ!」
先輩風の男はジロジロと神経質に辺(あた)りを見回す。
「風なんか吹いてないじゃないですか」
「いや、吹いていなくても、邪な風はどこに潜(ひそ)んでいるか分からんからなあ~」
「…そうなんですか?」
「そうなんだ…」
先輩風の男が自信ありげに語る。
「あっ! すいませんっ!!」
そのとき、後方の席から客の声が飛ぶ。
「はぁ!?」
後輩風の男が後ろを振り返る。
「いゃ~、胡椒(こしょう)が出過ぎましてねっ!」
「…」
先輩風の男は形無(かたな)しで黙ってしまう。ところが、見えない風は、『ヒヒヒ…俺の所為だがねっ!』と思わずニヤリと。
このように、他に妥当な原因があったにしろ、それでも邪な風は存在し、嗤(わら)っているのである。^^
完
息を止めれば苦しくなる。それでも止めていれば人はチィ~~ン! と鉦(かね)が鳴ることになる。要は死ぬ訳だ。^^ まあ、そこまで止められる人は異星人以外いないだろうから、当然、荒い呼吸をス~ハ~ス~ハ~とすることになる。このように、何気(なにげ)なく生きている私達ではあるが、知らず知らずのうちに呼吸をし続け、生きているのである。
とある町で奇妙な競技大会が行われている。水中息止め選手権である。選手達はA~Fの各グループに別れ、数人ずつ横一列に並ぶ。選手達の前には長椅子が並び、その上には水を張った洗面器が人数分、置かれている。選手達は合図のピストル音とともに顔を水中へ浸(つ)け、そのままでいられる長さのタイムを競う・・という趣向だ。
「こ、これはっ! せ、世界記録が出そうですっ!!」
マイクを握りしめた大会本部席の係員が興奮気味に喚(わめ)く。
他の選手達が顔を上げたあと、一人の選手だけが顔を洗面器に浸け続けている。
「ギネスっ! せっ! 世界記録の誕生ですっ!!」
会場全員の視線がその選手に向けられる。ところが、その選手はいっこうに顔を上げる気配がない。
「… ? これは、どうしたことかっ!!」
不審に思った係員が、思わず選手に駆け寄る。選手は顔を浸けたまま呼吸をやめ息絶えていた。と、いうことはなく、仮死状態で気絶していた。すぐに人工呼吸措置が施(ほどこ)され、選手は息を吹き返した途端、片手の指でVサインを高らかに上げた。会場からは割れんばかりの拍手が湧き起こった・・と、話はまあ、こうなる。
このように呼吸は生死に直結し、それでも止め続けられるという馬鹿な話はあり得ない。^^
完
久しぶりに掃除と整理を終えた丸太(まるた)は、ホッコリとした気分で淹(い)れた茶を啜(すす)りながら辺(あた)りを見回した。すると、今までが雑然としていた所為(せい)か、整い過ぎた物足りなさが、どこかした。
『なんか、寒々(さむざむ)しいなぁ~』
そう思えた丸太は戸棚(とだな)の上に花でも…と思った。上手(うま)い具合に手頃な器(うつわ)や剣山(けんざん)があったから、丸太は庭に咲いた花で生(い)け花(ばな)を始めることにした。作業は順調に進み、次第にそれらしくなっていった。
『まあ、このくらいか…』
と、思えた丸太だったが、生け終えた器を戸棚の上へ置くと、どこか生け過ぎた感がしなくもなかった。そのままでもよかったのだが、それでも気になった丸太は、生けた花の枝先を鋏(はさみ)でチョン切った。
『まあ、このくらいか…』
と、ふたたび思えた丸太だったが、今度は反対側の方が少し生け過ぎてるぞ…と、気になり出した。丸太は、生けた花の枝先を、また鋏(はさみ)でチョン切った。そして器をふたたび戸棚の上へと置き、遠目(とおめ)に眺(なが)めてみると、少し上の方が生け過ぎた感がしなくもなかった。丸太は、また気になる枝先を鋏(はさみ)でチョン切った。すると…と、また鋏でチョン切る繰り返しが続き、いつの間にか生けたはずの生け花はほとんど器から消え去っていた。
このように、生け花はそれでも! と深追いせず、少し気分を我慢した程度にしておく方が無難(ぶなん)だと言える。^^
完
双方(そうほう)の間にギャップ[食い違い]があればあるほど、その差が際立(きわだ)ってグッ! とくる度合いや凄(すご)みが増す。例えば時代劇なんかだと、悪役が憎々(にくにく)しいほど、その悪役をやっつける主役が格好よく見えたりする・・といったところだ。色気方面だと、美人なのに秘部が汚(きたな)らしく卑猥(ヒワイ)でそそるとか、弱そうな男子が意外とナニが強く強壮家・・といった類(たぐい)いの話となる。^^
とある家庭のキッチンで、どこにでもいそうな主婦が、お汁粉(しるこ)を作っている。
「どれどれ…ちょっと味見してやろう」
「偉(えら)そうに…」
主婦は膨(ふく)れながら、お玉で小皿(こざら)に煮汁(にじる)を少し入れて手渡す。主人はその小皿を、さも当然のように受け取り、口に含む。
「…まあ、不味(まず)くはないが、それでも今一、甘みがな…」
「そう? なら…」
主婦はそう言いながら、食塩を指先でほんの少し、煮汁へ摘(つま)み入れる。
「お、おいっ!! そんなことしたらっ!」
「これでいいのよっ! はいっ!」
主婦は自信ありげに、もう一度、小皿に煮汁を少し入れて主人に手渡す。主人はその小皿を、ふたたび受け取り、口に含む。
「おっ! ギャップがっ!!」
「でしょ!?」
主人はそう言われ、思わず頷(うなずく)く。
このように、それでも! と、より以上の効果を望むなら、ギャップが必要となる訳だ。^^
完
悪いことが続いたとき、ふと、心に浮かぶのが、あの頃だ。ああ、あの頃はいいあの頃だったなぁ~…などと、あの頃をコロコロと思い出す訳だ。^^ どういう訳か悪かったあの頃を思い出そうとしないのは、深層心理の防御機能が働いていると見られなくもない。詳しいことは心理学者か専門医の先生方に訊(たず)ねてもらいたい。^^
長閑(のどか)だった森の風景が消え、入れ替わるかのように伐採(ばっさい)された樹々の跡地に建物が建つようになったとある町の細道である。一人の老人がボケェ~っと気抜けしたような顔で変わった景色を見ながらあの頃を思い出している。
「あの頃は、よかった…」
溜息(ためいき)混じりに、老人は小さくそう呟(つぶや)いた。まだ車が飛び交うほどには発展していない町だけに、ボケェ~っと道に立っていても事故に遭わないだけが勿怪(もっけ)の幸いだった。
「どうかされましたか?」
そこへ通りがかったリールに猫を繋いで散歩している老人が訊(たず)ねた。
「いや、べつに…。ほう! 猫の散歩ですかな?」
「はあ? まあ…」
確かに、散歩に犬を連れなければならない・・という決めはない。^^
「この辺(あた)りも変わりましたなぁ~」
「なんか殺伐(さつばつ)として、風情(ふぜい)が消えました…」
「木が伐採されて殺伐ですか? ははは…」
「上手いっ!! 私らも孰(いず)れは切られますかな? ははは…」
「まあ、そのようで。ははは…」
「不便ではありましたが、それでもあの頃は、そういう心配はなかったですなぁ~」
「はいっ!」
あの頃は生伐だった・・ということになる。^^
完