2013年、初のSP作製になります。
今まで何台のスピーカーを作ってきたかカウントしてみたところ、
何と、これで35台目!!
そんな訳で、今日もがんばってスピーカー工作です。
<今まで作製してきた自作スピーカー一覧はこちら。>
今回のテーマは、薄型サラウンドスピーカー。
部屋の壁に沿うような、薄型デザインを目指します。
使用するスピーカーユニットは、
手元にあったALPINE「DLS-108X」。

無駄な音を出さない、現代的なユニットで、
特に音場再現性に優れることを知っていたので採用しました。
箱の構成は、ダブルバスレフ型とします。
スペースファクターと、低音再生能力の兼ね合いが好バランスな方式です。
一般的なダブルバスレフ型は、長岡鉄男先生の設計によるものですが、
今回は、知人の協力もあり、新しい設計法での挑戦になります。
<クリックで拡大>


設計法は、知人の長年のダブルバスレフ経験によるもので、
作例を聴く機会があった時には、非常に自然な低音質感に感心したものです。
今回は、その公式を頼りに設計を進めました。
こうして、各容量とダクト面積・長さが決まりますので、
あとは形にするだけです。
ノートを前にしてムニャムニャ…と鉛筆でデザインしていきます。

んで、最終ver。

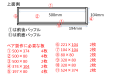

厚さは11.6cmで、
薄型スピーカーを名乗るのに十分な出来栄えです。
設計も終わったことすし、
ホームセンターに行って、
木材をカットしてもらいました。

使用したのは12mm厚のシナ合板。仕上げもよく音も上々。
1820mm×910mmのサイズで4千円前後で買えました。
ただ、今回はそれだけでは微妙に寸法が足りなかったので、
追加で900×600mmの12mm厚合板も購入です。

大まかにはホームセンターの機械で切ってもらいますが、
細かいところは、下記の図に従って自分でカットします。


板材はこれで入手完了!
次回は、工作編です。
今まで何台のスピーカーを作ってきたかカウントしてみたところ、
何と、これで35台目!!
そんな訳で、今日もがんばってスピーカー工作です。
<今まで作製してきた自作スピーカー一覧はこちら。>
今回のテーマは、薄型サラウンドスピーカー。
部屋の壁に沿うような、薄型デザインを目指します。
使用するスピーカーユニットは、
手元にあったALPINE「DLS-108X」。

無駄な音を出さない、現代的なユニットで、
特に音場再現性に優れることを知っていたので採用しました。
箱の構成は、ダブルバスレフ型とします。
スペースファクターと、低音再生能力の兼ね合いが好バランスな方式です。
一般的なダブルバスレフ型は、長岡鉄男先生の設計によるものですが、
今回は、知人の協力もあり、新しい設計法での挑戦になります。
<クリックで拡大>


設計法は、知人の長年のダブルバスレフ経験によるもので、
作例を聴く機会があった時には、非常に自然な低音質感に感心したものです。
今回は、その公式を頼りに設計を進めました。
こうして、各容量とダクト面積・長さが決まりますので、
あとは形にするだけです。
ノートを前にしてムニャムニャ…と鉛筆でデザインしていきます。

んで、最終ver。

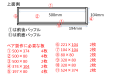

厚さは11.6cmで、
薄型スピーカーを名乗るのに十分な出来栄えです。
設計も終わったことすし、
ホームセンターに行って、
木材をカットしてもらいました。

使用したのは12mm厚のシナ合板。仕上げもよく音も上々。
1820mm×910mmのサイズで4千円前後で買えました。
ただ、今回はそれだけでは微妙に寸法が足りなかったので、
追加で900×600mmの12mm厚合板も購入です。

大まかにはホームセンターの機械で切ってもらいますが、
細かいところは、下記の図に従って自分でカットします。


板材はこれで入手完了!
次回は、工作編です。


























この式ですとcabinetの体積に関係なくfd2が決定されることになりますが。
コメントありがとうございます。
ご指摘のとおり、式にミスがありました。
作品の設計は正しい式でやっていたのですが、画像に起こしている時に下記間違いをしてしまったようです。
細かい部分まで見てくださり、とても嬉しく思います。今後も何かありましたら、ご指南よろしくお願い致します。