【題名】
『教授のおかしな妄想殺人』(原題『Irrational Man』)
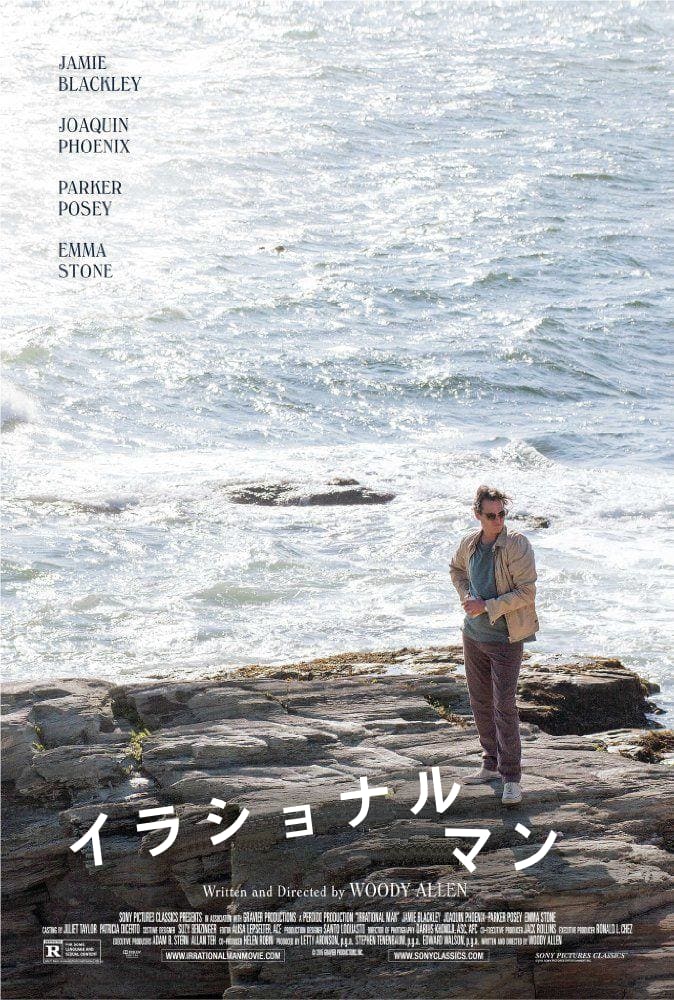
※思いっきりネタばれしています。
ネタばれを気にされる方は下記ご注意ください。
『教授のおかしな妄想殺人』こと『イラショナルマン』を観ました。
『重罪と軽罪』や『マッチポイント』の系譜にある作品と言う前知識のみで鑑賞。
端的に言って、『イラショナルマン』はその系譜の地続きではあると感じました。
町山さんの『マッチポイント』評を援用しつつ、考えてみたいと思います。
【あらすじ】
仕事にも恋愛にも打ち込めない日々を送っていた主人公がある日、悪徳判事の噂を耳にする。
そして何故か彼はその悪徳判事の殺害を夢想することで、
社会正義を果たすことが出来、惹いては自信の存在の意義が生まれると考える。
自身の存在に自信を見出してからと言うもの、仕事にも恋愛にも精力的になり、人生を謳歌し始める。
そして彼は実際にその夢想を現実に移してしまう。
【殺人を扱った過去作との比較】
『重罪と軽罪』では、
資産家の娘である妻を持ちながら愛人がいる歯科医が愛人に離婚を迫られ、
マフィアに殺害を依頼し愛人を始末する。歯科医の罪は露見はせずに逃げ果す。
『マッチポイント』でも、
金持ちの令嬢と結婚した主人公が、その裏でスカヨハと不倫し妊娠させてしまう。
自体が露見し妻の財産を失う事を恐れた主人公はスカヨハを強盗の仕業に見せかけ射殺する。
その際、自身の姿を目撃した無関係な老婆を射殺してしまう。
主人公の計画は酷く杜撰だったが、運良くホームレスが犯人として逮捕され逃げ果せた。
ラスト、生まれたばかりの主人公の子供に対して運だけあればいいと願う。
『イラショナルマン』では、
人生に意味を見出せなくなり、死を渇望する日々を送る哲学科の教授が、
ふとした切っ掛けで金で動く悪徳判事の存在を知り、義憤に駆られる。
判事を殺して社会正義を実現すれば、自分の人生に価値を見出せると考えた彼はそれを実行。
ところがその犯罪の事実を知った教え子に、告発すると告げられその教え子の殺害を計画するが、
その過程で事故死してしまう。
【比較検討】
『罪と罰』では、
学生のラスコリーニコフが義憤から悪徳金貸しの老婆を殺害するものの、
居合わせた老婆の妹も殺害してしまい罪の意識に苛まれる。
罪の意識に耐えかねて、結局ラスコリーニコフは自首をする。
上記3作品の主人公たちはみながみな『罪と罰』を読んでいるシーンがあります。
3作は実存主義と神の存在をテーマとして持っているように思いますが、
『重罪と軽罪』は不倫相手を殺すという物語的な話に落とし込んでいます。
『マッチポイント』に居たっては、不倫相手を殺すという筋は『重罪と軽罪』から引きつつ、
結末以外はほぼ『罪と罰』の構造をなぞっています。というか、まんまです。
そして『イラショナルマン』は義憤によって悪を正すという動機と、
悪徳判事を殺害し、それに気づいた教え子をも手に掛けようとするという展開も含めて、
『罪と罰』に寄せてきていると思います。
そもそも『Irrational Man』というタイトル自体が60年代の実存主義の教科書のタイトルだそうで
(しかもアレンの愛読書!)、主人公が実存主義哲学の教授であることからそのテーマは明らかです。
作品を重ねる毎に、実存主義的テーマを物語に落とし込むということから遠のき、
元ネタであろう『罪と罰』の動機、物語の構造、結末に寄せてきていて、
どんどんと純化というか、短絡化しているとも言いえると思います。
【感想】
生きる目的が見出せず、死を望む哲学の教授を演じるのが、まさかのホアキン・フェニックス。
アレンや若しくは優男が演じていれば、この映画の印象は大きく異なっていたように思います。
いつも飲んだくれて、死を渇望してやまない、屁理屈をこねまくる哲学者がアレンであれば、
それは恐らく同じ脚本であってもコメディ然としていたように思いますが、
演じるのは稀代の獣性を称えたホアキンであり、それは必然的にコメディにもなりえず、
かといってシリアスなドラマにもなりきれて居ない、つまりは下手にリアリティがあるのです。
正直、本作で哲学科の教授が語る授業の中の哲学の説明はとても表層的な部分にとどまります。
またエイブが悪徳判事の存在を知るダイナーでのシーンに関しても、唐突で不自然な印象を受けます。
はっきり言って、脚本の推敲が足りていないと感じます。
ただ、アレンやそれに準じたコメディの空気を持つ俳優が演じていれば、
受け取る印象は異なったと思います。
ホアキンが演じることで必要以上のリアリティが生まれてしまい、
この粗が目立つ物語がコメディにも寓話にも、
かといって『マッチポイント』のようなサスペンスにもなりえなかったと思います。
また本作が下手にリアリティを持ってしまっているのは、
撮影監督のダリル・コンジの写実的なパキっとした映像のためでもあるように思います。
脚本とテーマ性と俳優と映像が不協和音を奏でているような印象です。
あと、日本語タイトルと宣伝の仕方、ビジュアルワークが酷いです。
原題だと伝わりづらいから仕方が無い部分があるとは言え、
『教授のおかしな妄想殺人』では原題のタイトルの持つ意味が失われてしまいます。
【参考】
「町山智浩の「映画の謎を解く」⑦ ウディ・アレン『マッチポイント』(05年)」(町山智浩の映画ムダ話)
https://tomomachi.stores.jp/items/560e4726bfe24cda5f004e10
「Woody Allen interview: 'Murder and death are very seductive'」(The Telegraph)
http://www.telegraph.co.uk/film/irrational-man/woody-allen-interview/
「Woody Allen dishes on money, murder and music」(Telegram.com)
http://www.telegram.com/article/20150720/NEWS/150729976
『教授のおかしな妄想殺人』(原題『Irrational Man』)
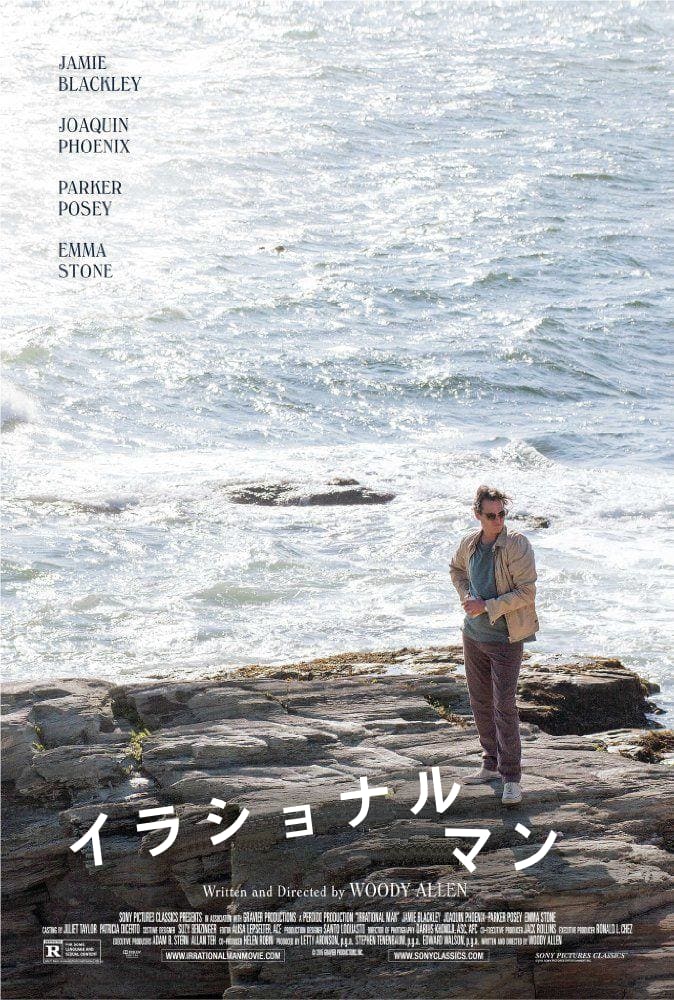
※思いっきりネタばれしています。
ネタばれを気にされる方は下記ご注意ください。
『教授のおかしな妄想殺人』こと『イラショナルマン』を観ました。
『重罪と軽罪』や『マッチポイント』の系譜にある作品と言う前知識のみで鑑賞。
端的に言って、『イラショナルマン』はその系譜の地続きではあると感じました。
町山さんの『マッチポイント』評を援用しつつ、考えてみたいと思います。
【あらすじ】
仕事にも恋愛にも打ち込めない日々を送っていた主人公がある日、悪徳判事の噂を耳にする。
そして何故か彼はその悪徳判事の殺害を夢想することで、
社会正義を果たすことが出来、惹いては自信の存在の意義が生まれると考える。
自身の存在に自信を見出してからと言うもの、仕事にも恋愛にも精力的になり、人生を謳歌し始める。
そして彼は実際にその夢想を現実に移してしまう。
【殺人を扱った過去作との比較】
『重罪と軽罪』では、
資産家の娘である妻を持ちながら愛人がいる歯科医が愛人に離婚を迫られ、
マフィアに殺害を依頼し愛人を始末する。歯科医の罪は露見はせずに逃げ果す。
『マッチポイント』でも、
金持ちの令嬢と結婚した主人公が、その裏でスカヨハと不倫し妊娠させてしまう。
自体が露見し妻の財産を失う事を恐れた主人公はスカヨハを強盗の仕業に見せかけ射殺する。
その際、自身の姿を目撃した無関係な老婆を射殺してしまう。
主人公の計画は酷く杜撰だったが、運良くホームレスが犯人として逮捕され逃げ果せた。
ラスト、生まれたばかりの主人公の子供に対して運だけあればいいと願う。
『イラショナルマン』では、
人生に意味を見出せなくなり、死を渇望する日々を送る哲学科の教授が、
ふとした切っ掛けで金で動く悪徳判事の存在を知り、義憤に駆られる。
判事を殺して社会正義を実現すれば、自分の人生に価値を見出せると考えた彼はそれを実行。
ところがその犯罪の事実を知った教え子に、告発すると告げられその教え子の殺害を計画するが、
その過程で事故死してしまう。
【比較検討】
『罪と罰』では、
学生のラスコリーニコフが義憤から悪徳金貸しの老婆を殺害するものの、
居合わせた老婆の妹も殺害してしまい罪の意識に苛まれる。
罪の意識に耐えかねて、結局ラスコリーニコフは自首をする。
上記3作品の主人公たちはみながみな『罪と罰』を読んでいるシーンがあります。
3作は実存主義と神の存在をテーマとして持っているように思いますが、
『重罪と軽罪』は不倫相手を殺すという物語的な話に落とし込んでいます。
『マッチポイント』に居たっては、不倫相手を殺すという筋は『重罪と軽罪』から引きつつ、
結末以外はほぼ『罪と罰』の構造をなぞっています。というか、まんまです。
そして『イラショナルマン』は義憤によって悪を正すという動機と、
悪徳判事を殺害し、それに気づいた教え子をも手に掛けようとするという展開も含めて、
『罪と罰』に寄せてきていると思います。
そもそも『Irrational Man』というタイトル自体が60年代の実存主義の教科書のタイトルだそうで
(しかもアレンの愛読書!)、主人公が実存主義哲学の教授であることからそのテーマは明らかです。
作品を重ねる毎に、実存主義的テーマを物語に落とし込むということから遠のき、
元ネタであろう『罪と罰』の動機、物語の構造、結末に寄せてきていて、
どんどんと純化というか、短絡化しているとも言いえると思います。
【感想】
生きる目的が見出せず、死を望む哲学の教授を演じるのが、まさかのホアキン・フェニックス。
アレンや若しくは優男が演じていれば、この映画の印象は大きく異なっていたように思います。
いつも飲んだくれて、死を渇望してやまない、屁理屈をこねまくる哲学者がアレンであれば、
それは恐らく同じ脚本であってもコメディ然としていたように思いますが、
演じるのは稀代の獣性を称えたホアキンであり、それは必然的にコメディにもなりえず、
かといってシリアスなドラマにもなりきれて居ない、つまりは下手にリアリティがあるのです。
正直、本作で哲学科の教授が語る授業の中の哲学の説明はとても表層的な部分にとどまります。
またエイブが悪徳判事の存在を知るダイナーでのシーンに関しても、唐突で不自然な印象を受けます。
はっきり言って、脚本の推敲が足りていないと感じます。
ただ、アレンやそれに準じたコメディの空気を持つ俳優が演じていれば、
受け取る印象は異なったと思います。
ホアキンが演じることで必要以上のリアリティが生まれてしまい、
この粗が目立つ物語がコメディにも寓話にも、
かといって『マッチポイント』のようなサスペンスにもなりえなかったと思います。
また本作が下手にリアリティを持ってしまっているのは、
撮影監督のダリル・コンジの写実的なパキっとした映像のためでもあるように思います。
脚本とテーマ性と俳優と映像が不協和音を奏でているような印象です。
あと、日本語タイトルと宣伝の仕方、ビジュアルワークが酷いです。
原題だと伝わりづらいから仕方が無い部分があるとは言え、
『教授のおかしな妄想殺人』では原題のタイトルの持つ意味が失われてしまいます。
【参考】
「町山智浩の「映画の謎を解く」⑦ ウディ・アレン『マッチポイント』(05年)」(町山智浩の映画ムダ話)
https://tomomachi.stores.jp/items/560e4726bfe24cda5f004e10
「Woody Allen interview: 'Murder and death are very seductive'」(The Telegraph)
http://www.telegraph.co.uk/film/irrational-man/woody-allen-interview/
「Woody Allen dishes on money, murder and music」(Telegram.com)
http://www.telegram.com/article/20150720/NEWS/150729976









