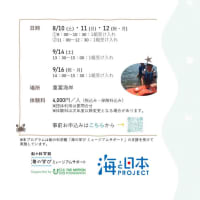アロマトリートメントで、よそ様の体のケアはするのですが、
今日は自分の体が、どんよりしています。
頸部右、肩甲骨周り右。
右側がなんだか滞っています。
ぐぅーーーーー。
セルフケアで、乗り切ります。
先月の算数セミナーで、メモっていた言葉がありました。
「分解能」という言葉で、
散乱する点の数をきちんとわかるようになるという部分で、
講師の矢ケ崎響さんが使われた言葉でした。
そして、「からだの動きは分解能につながる」と、
私は響さんの言葉ととしてメモしていて、
それが今ひとつ、ピンと来ずに響さんに質問をしていました。
分解能という言葉自体も、聞くのが初めてで調べてみると、
分解能~器械・装置などで、物理量を識別できる能力。
望遠鏡・顕微鏡では、見分けられる二点間の最小距離または視角。
分光器では、近接する2本のスペクトル線を分離できる度合い。
分解力。解像度。 デジタル大辞泉より
とあり、ちっともピンと来なかったのです。
響さんからの解説で納得。
分解能というのは、顕微鏡や望遠鏡でどれだけ細かく見えるか、という能力を示す言葉だそうです。
響さんは「見える細かさ」という意味で分解能という言葉を用いられたようでした。
そして、「手先が器用になるほどに、細かい所も見えるようになってくる」ということを言いたくて、
分解能という言葉を使ったと質問に答えてくださいました。
なるほどなぁ、と思いました。
分解能が高いほど、細かいものが見える。
子どもたちも分解能が高くなると、
散乱する無数の点をきちんと1個ずつ数えて、
数え忘れや二重に数えるという失敗をしなくなるのですね。
そのためには、1対1対応にしっかり取組み、
経験を積み注意深くなれば分解能も高くなるのでしょう。
そして、分解能の高さは、
自分もどうやったら、あんな風にボールが投げられるかな、
どうやったらきれいに書けるかな、
今、何しないといけないのかな、などという、
比較したり、真似したり、観察する力に繋がっていくのだなぁと思いました。
響さんは私から見ると超理系で、大学では物理が専門だったそうです。
実験して、失敗すると「この失敗の原因は?」と遡って原因を1つ1つつぶしていく。
だから、子どもたちが「わからない」とつまずくと、
「そのつまずきの現象の原因は何から来ているのか?」という風に、
実験の手法さながらに、1つ1つ検証していかれるそうです。
その様は、フォイヤーシュタインの「システマチックサーチだな。」と思うことでした。
…システマチックサーチについては、また、別の機会に…(『王様のレストラン』風で。古っ )
)
今日は自分の体が、どんよりしています。
頸部右、肩甲骨周り右。
右側がなんだか滞っています。
ぐぅーーーーー。
セルフケアで、乗り切ります。
先月の算数セミナーで、メモっていた言葉がありました。
「分解能」という言葉で、
散乱する点の数をきちんとわかるようになるという部分で、
講師の矢ケ崎響さんが使われた言葉でした。
そして、「からだの動きは分解能につながる」と、
私は響さんの言葉ととしてメモしていて、
それが今ひとつ、ピンと来ずに響さんに質問をしていました。
分解能という言葉自体も、聞くのが初めてで調べてみると、
分解能~器械・装置などで、物理量を識別できる能力。
望遠鏡・顕微鏡では、見分けられる二点間の最小距離または視角。
分光器では、近接する2本のスペクトル線を分離できる度合い。
分解力。解像度。 デジタル大辞泉より
とあり、ちっともピンと来なかったのです。
響さんからの解説で納得。
分解能というのは、顕微鏡や望遠鏡でどれだけ細かく見えるか、という能力を示す言葉だそうです。
響さんは「見える細かさ」という意味で分解能という言葉を用いられたようでした。
そして、「手先が器用になるほどに、細かい所も見えるようになってくる」ということを言いたくて、
分解能という言葉を使ったと質問に答えてくださいました。
なるほどなぁ、と思いました。
分解能が高いほど、細かいものが見える。
子どもたちも分解能が高くなると、
散乱する無数の点をきちんと1個ずつ数えて、
数え忘れや二重に数えるという失敗をしなくなるのですね。
そのためには、1対1対応にしっかり取組み、
経験を積み注意深くなれば分解能も高くなるのでしょう。
そして、分解能の高さは、
自分もどうやったら、あんな風にボールが投げられるかな、
どうやったらきれいに書けるかな、
今、何しないといけないのかな、などという、
比較したり、真似したり、観察する力に繋がっていくのだなぁと思いました。
響さんは私から見ると超理系で、大学では物理が専門だったそうです。
実験して、失敗すると「この失敗の原因は?」と遡って原因を1つ1つつぶしていく。
だから、子どもたちが「わからない」とつまずくと、
「そのつまずきの現象の原因は何から来ているのか?」という風に、
実験の手法さながらに、1つ1つ検証していかれるそうです。
その様は、フォイヤーシュタインの「システマチックサーチだな。」と思うことでした。
…システマチックサーチについては、また、別の機会に…(『王様のレストラン』風で。古っ
 )
)