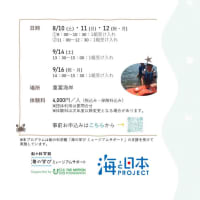今年の養生の〆は、
去年同様、森の中だった。
お弁当屋さんを営む養生仲間の
手作りお弁当を頬張って、
森の中のフユイチゴを採り、
カラスの声に耳を傾け…。
森の中の14時はもう夕方のような雰囲気。
フユイチゴを摘みながら、色々考え、
また春に来ることができるといいな、と
森を後にしました。
8.8%。
何らかの子どもの支援に関わっている人には、ピンとくる数字が先週ニュースを賑わせていました。
NHK
Nikkei
前は6%台だったのに発達障害の子の割合が一学級に8.8%だ!と大騒ぎです。
大元の文部科学省の調査では、懸命に、
何度も何度も繰り返して、
知的発達に遅れはないものの学習面や行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒数の割合を推定している調査であり、発達障害のある児童生徒数の割合や知的発達に遅れがある児童生徒数の割合を 推定する調査ではないことに十分留意いただきたい。
と言っていますが、
メディアは万人がイメージしやすい言葉で、内容も容易に安易にイメージしやすいように「発達障害の可能性」と言って憚りません。
きっと、このイメージ戦略が大事で、
このニュースを聞いた人たちは、
「ああ、うちのクラスのあの子も!」とか
「○○さんって、もしかして!」
と色々想像たくましく、あたかも、
それが決定のように個人のことを語る人も
いるかもしれません。
この調査はどれだけの効力を持つものなのでしょう。
調査は質問に対して、学級担任が回答したものをもとに数字が出されています。
大体が週5行く学校。
小学校ならほぼ時を共に過ごす担任。
でも、人間だもの、相性ってあります。
中学では教科によって担任は変わりますが、朝夕は顔も合わせることでしょう。
高校はもっとシビアで、教科によっては
顔をあまり合わさない担任もいることでしょう。
そういうことだけでも、私は
この調査の意味意義にちょっと距離を感じます。
更に、近頃、立ち話的に聞いた話が
頭をよぎりました。
連絡帳に毎日毎日、
お子さんのマイナス面をびっしり書いて、
担任が持たせるので精神的に参っている
親御さんがいらっしゃると。
できないことも多いけれど、
どうにかしようと取り組んでいるらしい。
担任の先生にも、
他に方法がないか聞くと、
「療育に行って!」というだけだと。
そんな担任の先生が調査に協力したら、
きっとその子は困難な子になるのではないでしょうか。
知的遅れはないけれど、
学習面で困難な子、行動面で困難な子。
それに対する方針も対策も書かれていない、数字だけがひとり歩きするこの調査。
この8.8%という印象操作的な数字。
誰が得をするのでしょうか。
ただの風邪のような症状でも、
新規感染者数を発表するマスコミ報道。
数字の持つ力を知る人たちに操られたくないものですね。