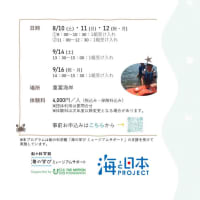今日は天気もよくて、まさに春!
早朝、仕事しながら汗ばむし、吹く風が気持ちよく感じました。
さて、昨日に引き続き、がっかりな本のご紹介です。
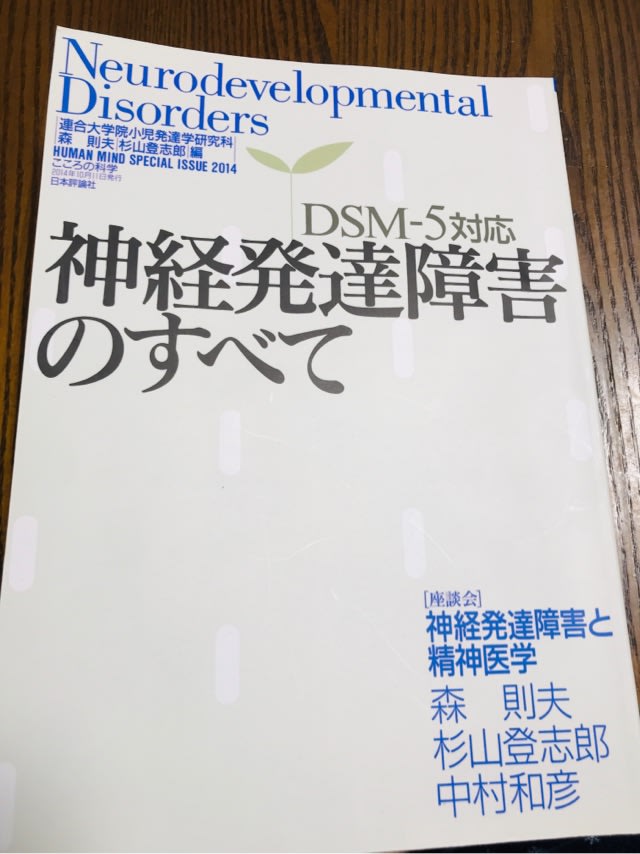
残念な放談や杉様のまったく神経について触れられない「神経発達障害とは何か」もひどいですが、
他にも、医者治す気ない感満載の内容が目白押しです。
まず、「疾病の病因や予後を検討する目的において最も優れた研究デザイン」という
コホート研究という手法でひたすらASD研究に没頭するセンセー。
「乳幼児からのデータ収集が比較的難しい」ため
「乳幼児を対象としたコホート研究が立ち後れている』現状を嘆き、
「以前は、三歳ごろまで顕在化しなかったASDの行動兆候」が、
「より早期の段階で捉えられるようになったという知見」に喜ぶという
治すことよりデータ収集第一主義の研究頭!(褒めてません)
そして、抑うつや不安、引きこもり、就労の問題が高い水準を保つだの、
二十代後半には横ばいだの、まったく良いことないのに、
「予後因子に関する研究が進むことで、ASD児者に対する効果的な介入方法について示唆が得られることが期待される」
という脳天気な結論。
この本が出た2014年の時点で、
治しもせずに予後を追っかけている意味もわかりませんしが、
5年経った現在においても「治りません!」を貫くギョーカイ先生方に
解決の糸口は見つからなかったのだなぁと、と遠い目です。
で、次、「神経発達障害への治療の進歩」と題した、中京大学のセンセーは、
「現代においてペアレント・プログラムを含めたPTは神経発達障害の家族支援の必須技法となっている。」
と宣い、私が6年前に「お!これは!」と思い、色々試した感覚統合については、
「ASD児を対象にした感覚統合療法の効果研究自体は少ないものの(中略)注目すべきアプローチといえる」と
うすーくかすって終了。
身体に注目した花風社さんとは一線を画すセンスのなさです。
また、誰が頼んだのか、「神経発達障害の生涯発達支援という全体像」という、
治しもせずに、生涯関わろうとする恐ろしい神経の持ち主です。
生涯関わろうとする人たちの納得の「治療の進歩」状況を垣間みて、ぞっとしました。
さらに、「神経発達障害への教育」では、大阪大学大学院の方が、
「個別ニーズに対応」と言いつつ、専門性について声だかに訴えられています。
その専門性は何だろう、と読み進めてあがってきたのが、
「応用行動分析アプローチ」だの「TEACCHプログラム」です。
学校での教育=学習、知識の修得、と思っていた私はびっくりしました。
「教育」という言葉ひとつとっても、思い浮べる内容は人それぞれであるのだ、と、
己の言葉に対する解釈の狭さを反省することでした。
ちょっと、お!と思ったところは、
福井大学のセンターの先生が、「ASD生物学研究の進歩」として、後ろの方に、
「エネルギー代謝異常の観点から得られた研究成果」として「ミトコンドリア機能」を評価し、
結果、「ASDにおけるミトコンドリアの機能低下を示す所見を見いだした」とあり、
現在、SNSの仲間内でタンパク質押ししていることとの関係があるのかも!と、
ちょっとだけ、「ほお!」となりました。
あとは、もう、薬物療法のすすめとか、「みんな!発達性運動障害って知ってる!?」的ないじけた体育系の項目。
でも、実は、このいじけた体育系項目にこそ、学習障害や不器用さを治す活路があるにも関わらず、
ここでは、診断基準云々でその活路に気がついていおらず、果ては、
保護者が「『不器用さ』に対する問題意識が芽生えていないか、芽生えていてもあまり成長していない」
との親御さんディスに走る始末です。
さらには、この本に流れる失礼の川がここにもあり、
「運動面の問題ということから、医療的な取り組みとして作業療法士、理学療法士が担当すべきであるが、
保険の点数がつかないので十分実施されていないことが多い。」という正直さです。
本当に、病院では治りませんねぇ。
そして、最後、トリはお名前の知れた鳥取大学のセンセーです。
ここでは、なぜか、「わが国独自の福祉行政上の概念」である、「強度行動障害」についてです。
内容は「ハイリスク児」を抽出し、
「医療との連携のもとで早期からの個別療育や親指導を行うとともに、
特別支援教育においてもASD特性に配慮した個別的な支援を継続することが望まれる」という提案や
「学齢期から成人期までの一貫した支援システムの構築のために、専門機関からの継続的なコンサルテーションの必要性」と
釣った魚は逃さない恐怖の束縛的支援の押し売りなど、治す感のない内容で終了。
このように、読んでも読んでも読んでも読んでも、神経について言及している箇所はありませんでした。
5年経っても今のことのように読めるこの本。
ギョーカイ先生方は、いつまで本の内容が色あせぬように、
今日も治さない医療を全力で突き進んでおられることがよくわかった本でした。
早朝、仕事しながら汗ばむし、吹く風が気持ちよく感じました。
さて、昨日に引き続き、がっかりな本のご紹介です。
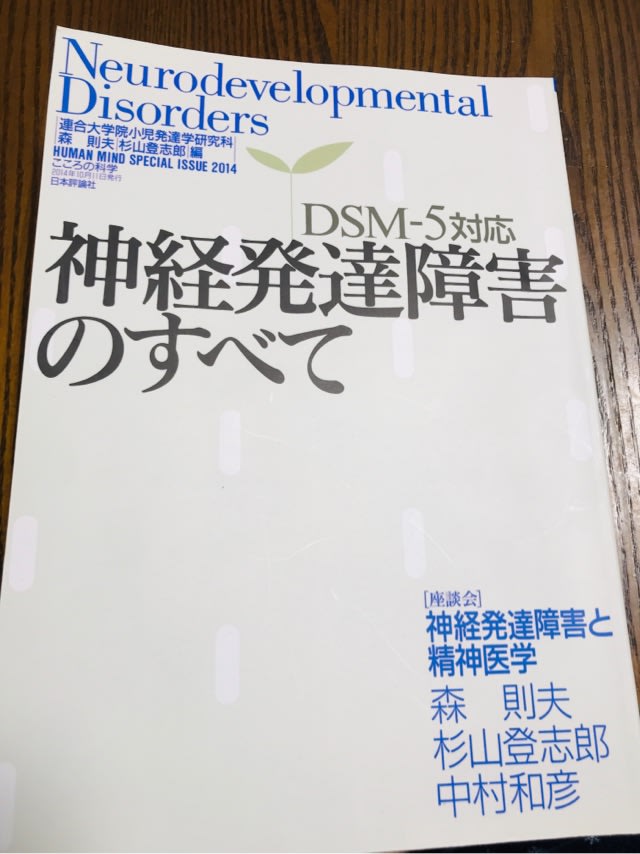
残念な放談や杉様のまったく神経について触れられない「神経発達障害とは何か」もひどいですが、
他にも、医者治す気ない感満載の内容が目白押しです。
まず、「疾病の病因や予後を検討する目的において最も優れた研究デザイン」という
コホート研究という手法でひたすらASD研究に没頭するセンセー。
「乳幼児からのデータ収集が比較的難しい」ため
「乳幼児を対象としたコホート研究が立ち後れている』現状を嘆き、
「以前は、三歳ごろまで顕在化しなかったASDの行動兆候」が、
「より早期の段階で捉えられるようになったという知見」に喜ぶという
治すことよりデータ収集第一主義の研究頭!(褒めてません)
そして、抑うつや不安、引きこもり、就労の問題が高い水準を保つだの、
二十代後半には横ばいだの、まったく良いことないのに、
「予後因子に関する研究が進むことで、ASD児者に対する効果的な介入方法について示唆が得られることが期待される」
という脳天気な結論。
この本が出た2014年の時点で、
治しもせずに予後を追っかけている意味もわかりませんしが、
5年経った現在においても「治りません!」を貫くギョーカイ先生方に
解決の糸口は見つからなかったのだなぁと、と遠い目です。
で、次、「神経発達障害への治療の進歩」と題した、中京大学のセンセーは、
「現代においてペアレント・プログラムを含めたPTは神経発達障害の家族支援の必須技法となっている。」
と宣い、私が6年前に「お!これは!」と思い、色々試した感覚統合については、
「ASD児を対象にした感覚統合療法の効果研究自体は少ないものの(中略)注目すべきアプローチといえる」と
うすーくかすって終了。
身体に注目した花風社さんとは一線を画すセンスのなさです。
また、誰が頼んだのか、「神経発達障害の生涯発達支援という全体像」という、
治しもせずに、生涯関わろうとする恐ろしい神経の持ち主です。
生涯関わろうとする人たちの納得の「治療の進歩」状況を垣間みて、ぞっとしました。
さらに、「神経発達障害への教育」では、大阪大学大学院の方が、
「個別ニーズに対応」と言いつつ、専門性について声だかに訴えられています。
その専門性は何だろう、と読み進めてあがってきたのが、
「応用行動分析アプローチ」だの「TEACCHプログラム」です。
学校での教育=学習、知識の修得、と思っていた私はびっくりしました。
「教育」という言葉ひとつとっても、思い浮べる内容は人それぞれであるのだ、と、
己の言葉に対する解釈の狭さを反省することでした。
ちょっと、お!と思ったところは、
福井大学のセンターの先生が、「ASD生物学研究の進歩」として、後ろの方に、
「エネルギー代謝異常の観点から得られた研究成果」として「ミトコンドリア機能」を評価し、
結果、「ASDにおけるミトコンドリアの機能低下を示す所見を見いだした」とあり、
現在、SNSの仲間内でタンパク質押ししていることとの関係があるのかも!と、
ちょっとだけ、「ほお!」となりました。
あとは、もう、薬物療法のすすめとか、「みんな!発達性運動障害って知ってる!?」的ないじけた体育系の項目。
でも、実は、このいじけた体育系項目にこそ、学習障害や不器用さを治す活路があるにも関わらず、
ここでは、診断基準云々でその活路に気がついていおらず、果ては、
保護者が「『不器用さ』に対する問題意識が芽生えていないか、芽生えていてもあまり成長していない」
との親御さんディスに走る始末です。
さらには、この本に流れる失礼の川がここにもあり、
「運動面の問題ということから、医療的な取り組みとして作業療法士、理学療法士が担当すべきであるが、
保険の点数がつかないので十分実施されていないことが多い。」という正直さです。
本当に、病院では治りませんねぇ。
そして、最後、トリはお名前の知れた鳥取大学のセンセーです。
ここでは、なぜか、「わが国独自の福祉行政上の概念」である、「強度行動障害」についてです。
内容は「ハイリスク児」を抽出し、
「医療との連携のもとで早期からの個別療育や親指導を行うとともに、
特別支援教育においてもASD特性に配慮した個別的な支援を継続することが望まれる」という提案や
「学齢期から成人期までの一貫した支援システムの構築のために、専門機関からの継続的なコンサルテーションの必要性」と
釣った魚は逃さない恐怖の束縛的支援の押し売りなど、治す感のない内容で終了。
このように、読んでも読んでも読んでも読んでも、神経について言及している箇所はありませんでした。
5年経っても今のことのように読めるこの本。
ギョーカイ先生方は、いつまで本の内容が色あせぬように、
今日も治さない医療を全力で突き進んでおられることがよくわかった本でした。