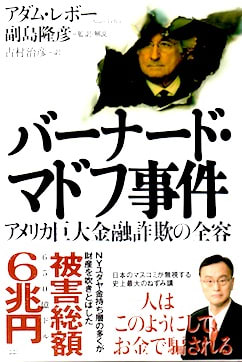世界で最も有名な科学方程式はアインシュタインが発見したE=mc2(エネルギー=質量 X 光速の2乗)であろう。これは特殊相対性理論から導き出されたもので、エネルギーと質量が等価関係を持ち、相互に互換性があり、条件が整えばエネルギーが質量に変換されるのと同様に、質量もまた適切な条件のもとではエネルギーに変換されることを示している。この方程式により人類は「原子の火」を手に入れて、まず原爆が、ついで原子力エネルギーが生み出された。
アインシュタインは、純粋にこの式を理論から導きだしたので、核分裂によるエネルギーの解放などは予想もしていなかった。それを物語る有名なエピソードがある。 1920年の年末、ベルリンにいたアインシュタインのもとに一人の青年が分厚い原稿を抱えて訪れ、会って話したいと言い張った。受付で押し問答があり、面倒な手続きの末、青年はようやくアインシュタインに会うことができた。彼はアインシュタインに、あの有名な方程式E=mc2を基にして、軍事目的に利用できる驚異的な爆発力を持つ兵器が作れると語った。その場に居合わせた人たちの話では、アインシュタインはこの話をまったく相手にしようとせず、こう言ったといわれる。 『まあ落ち着きたまえ。きみのばかばかしい説の詳しい話に立ち入らなければ、きみはさらに恥をかかずにすむよ』 ところがなんと、それから二十五年後、広島・長崎への原爆投下をもたらしたのは、アインシュタイン方程式の応用にほかならなかったのである。
原子物理学の分野で飛躍的な発展が遂げられ、核反応が発見されたのは、レオ・シラードが神がかり的な直感を得た1933年のことだった。すなわち、もしある元素内の原子が衝撃を受けて二つの中性子を放射すると、連鎖反応が始まるのではないかというものだった。ヨーロッパの数人の科学者たちが実際に核分裂を発見したのは、1938年になってからだった。イタリアのエンリコ・フェルミが、その第一発見者だと言われている。それに続いてキュリー夫人の義理の息子であるフランスのフレデリック・ジョリオ、ドイツでは化学者オットー・ハーンとフリッツ・シュトラスマンもそれを発見した。ニールス・ボーアは、核分裂の実験が成功し、その理論的な説明もすでにできているというニュースを、1939年にワシントンで開催された第5回理論物理学会の席上で、アメリカの研究者たちに知らせた。このニュースは、またたく間に全科学界に広がった。核分裂に伴う質量欠損により膨大なエネルギーが生ずる事が実証されたのである。
ナチスがなぜ原子力を軍事目的に利用しなかったのか、いまでも謎とされている。世界中の科学者の半数が、原子物理学の発展やその利用法について討論していた。軍事面で応用できそうな発見には、いつでもすぐに飛びついていたナチスドイツが、核に関しては反応が遅かった。 第一の理由としてあげられるのは、幸いアドルフ•ヒトラーは原子力のもたらす現象にまるで興味がなかったという事だ。第一次大戦の伍長には原子力の重要性を理解する能力はなかったようだ。第二の理由は、ドイツの中心的な科学者たちが、故意に核分裂発見のニュースを隠したという点である。彼らは結果を見越して、ナチスにその秘密を敦えるべきでないと考えた。とくにハイゼンベルクの努力によって、ナチスは核兵器の開発で連合国に遅れをとった。
大事な事は、連合国側は核開発でドイツより優位に立っていることを、終戦の直前まで自覚していなかったことである。いつもナチスに先を超されているのではないかという強迫観念があったので、アメリカはマンハッタン計画を推進し、1941年から核兵器開発に莫大な投資をした(心の片隅には大戦後のソ連との軍事的対抗戦略の事もあった)。連合国の核兵器開発ブログラムを作るに当たってアインシュタインが果たした投割についてはすでに伝説化してしまったが、その背景に潜む事実はしばしばあいまいにされ、一連の計画推進への関与については甚だしく誤解されている。 連合国における核兵器開発プログラム推進の音頭を取ったのは、ハンガリー出身の物理学者レオー•シラードだった。彼は、核爆弾製造の競争でドイツに勝つ必要性があることをルーズヴェルト大統領に知らせなければならないと思った。だが、アインシュタインほどの大物でないと大統領を動かすことはできないことも分かっていた。シラードは1938年七月、アインシュタインを訪問することにした。その夏、アインシュタインはロングアイランドの友入のもとに滞在していた。シラードと彼の意見に共感したプリンストン大学物理学教授のユージン・ウィグナーは、アインシュタインの居場所をつきとめて突然に訪問し、この危険な状況を説明した。
アインシュタインは、核分裂を原子爆弾に利用するという考えに仰天したという。1930年代から40年代にかけての彼の研究テーマは物理学の主流からはかけ離れた統一場理論の研究をしていた。おそらく、核分裂の利用についてのホットな議論は追いかけていなかったのだろう。第二次大戦が終結した直後に、アインシュタインはシラードが待ちかけた話について雑誌記事のなかで言及している。「われわれの時代に、それが本当に実現するとは思いませんでした。理論的には可能だとは思いましたが」 アインシュタインは科学界の代表として発言することに同意し、シラードが起草した核分裂の利用について大統領に行動を呼びかける手紙に署名した。1939年8月2日付のルーズヴェルト大統領あての手紙は次のようなものだった。 『大統領閣下 エンリコ・フェルミとレオ・シラードの最近の研究の結果によりますと、近い将来ウランが重要なエネルギー源として利用される可能性があると思えます。ある意味でこの状況は警戒を要しますし、必要となれば政府の早急な対応が望まれます。したがって、これから述べる事実をお知らせし、ご注意を喚起させていただくのが私の任務だと考える次第です。 この四か月で、フランスのジョリオ、ならびにアメリカのフェルミ、シラードの研究によって分かったことは、大量のウランを用いて核分裂の連鎖反応を起こし、それにより強大なエネルギーと大量のラジウムのような新しい元素を発生させ得る可能性があるという点です。近く実行に移されることは、まず間違いありません。 この新しい現象は、爆弾の製造に結びつくかもしれません。そして確信は持てませんが、強力な新型の爆弾が作られることが十分に考えられます。この型の爆弾は、一つだけでも船で運ばれて港で爆発すれば、周辺部を含めて港全体を壊滅させる力を持っています。おそらくそのような爆弾ですから、重すぎて航空輸送には耐えないでしょう。 アメリカにもある程度ウラン鉱石はあるものの、品質は著しく劣っています。カナダや旧チェコスロヴァキア領からはかなり産出するものの、世界最大の鉱山はベルギー領コンゴにあります。 この状況にかんがみて、政府と密接な関係にある核連鎖反応の研究チームを組むことが望ましいというお考えに至るのではないでしょうか。そのためには、閣下が信用されるしかるべき人物に、非公式に仕事を委ねるのが賢明かと思われます。その人物は、次のような任務を果たすことになるでしょう。 (a)政府各省と連絡を取り、新しい発見を逐一知らせ、政府が取るべき行動を進言する。とくに、アメリカがウランを確保できるよう心がける。 (b)現在、大学研究室の予算内でおこなわれている実験を促進する。そのためには、当該の人物がこの目的のために進んで寄付をしてくれる個人と接触して必要な限りの資金を供給してもらい、必要な設備の整った企業の研究所の協力を仰ぐ。 ドイツは、占領したチェコスロヴァキアの鉱山のウラン輸出を禁じたと聞いています。このように迅速な行動に出るということは、ドイツ国務次官の息子フォン・ワイツゼッカーがベルリンのカイザー・ヴィルヘルム研究所と結んでいて、そこでアメリカと同様のウランの実験がいま繰り返されているためと推察されます。 敬具 A・アインシュタイン』
この手紙を仲介したのは大統領にかなりの影響力を持っていた経済学者のアレグザングー・ザックスだった。アインシュタインの手紙を読むと、ルーズヴェルトはすぐに対策を講じると発表した。その晩のうちに、核分裂の利用法について調査する小委員会を設置した。その瞬間に、ヒロシマヘの道が聞かれたと言われている。 シラードが核兵器開発プログラムで助力を求めてきたとき、アインシュタインは大きな道徳的ジレンマに陥った。二、三年のうちに、彼の政治的見解は極端な平和主義から核兵器推進へと変身した。だがこの心変わりも、単なる思いつきではなかった。もし連合国が原子爆弾を製造しなかったら、遅かれ早かれナチスが製造することになるだろう。その場合、消極的に抵抗しても効果はない。そう考えたために、彼は手紙に署名したのだった。アインシュタインはロマン•ローラン的な反戦主義を棄却して反ファシズム戦争の推進者となっていたので、当然の帰結であった。
署名したことによって、彼は後に「原爆の父」というありがたくない名前を頂戴することになったが、これはまったく事実に反する。アインシュタインは、E=mc2という方程式を作ったが、ヒロシマとナガサキに落とされた原爆を製造したマンハッタン計画にはまったく関与していなかった。核実験に立ち合ったことも、一度もなかった。マンハッタン計画を主導したのはユダヤ系アメリカ人で、当時、ロスアラモス国立研究所の所長であった物理学者ロバート・オッペンハイマー(J. Robert Oppenheimer, 1904年 - 1967年)であった。
1945年8月6日の朝、史上初の厚子爆弾がヒロシマに投下された。瞬時に七万人もの日本人が命を落とし、その後に火傷や放射線障害で亡くなった人は十万人にものぼった。連合軍の核兵器製造計画が、ついに実現したのだった。アインシュタインはそのニュースをラジオで知った。彼は茫然として、「なんと恐ろしいことを」と言ったといわれる。ドイツがまるで核兵器を製造できる状況になかったことを連合国側が知ったのは、終戦後になってからだった。世界で最初の実験原子炉であるシカゴ•パイル1号が臨界に達したのは、1942年12月2日で、ここで生成したプルトニュウムが長崎の原爆に利用されたと言われている。この原子炉もマンハッタン計画の一部であった。
第二次大戦後、冷戦のもとに核兵器が世界中に拡散していく状況を見て、アインシュタインは、世界が悲惨な核地獄への道を歩んでいることを懸念した。戦争終結から亡くなるまで、彼は核兵器の廃絶を訴え続けた。体調が許す限り、彼はどこにでも行って熱弁を振るった。めったにプリンストンを離れることはなかったが、彼が強く気にかけていた核兵器拡散の恐怖について講演をするために、ときに短期間ニューヨークを訪れることもあった。アインシュタインはためらうことなく戦前のように平和主義に逆戻りした。その目的を達成するために、彼はイギリスの友人である哲学者で数学者のバートランド•ラッセルとの親交を深めた。二人は平和主義を広めるために、さまざまな策を練った。そして第二次大戦の教訓を忘れて、またもや不条理を繰り返そうとする時流を、力を合わせて押しとどめようとした。
アインシュタインが最も貢献したのは、原子科学者緊急委員会という組織を通じた反核運動だった。彼はその理事会の会長兼議長であり、必要とされる一般大衆の興味を引く作戦のうえで、彼の知名度が大いに役立った。その組織の目的は核兵器の危険性を一人でも多くの人に知ってもらい、ひいてはその開発に力を注ぐ政府の非道徳的な行為に目を向けさせることだった。そのためにアインシュタインは講演を行い、ニュース映画やラジオ向けのインタビューに応じた。全国紙に寄稿したり、雑誌や緊急委員会の機関誌にも執筆した。核兵器廃絶を訴えたラッセル•アインシュタイン宣言(アインシュタイン没後で遺言と言われる)には湯川秀樹博士も共同宣言者として名前を連ねている。
このような活動を続けていたが、1955年4月12日、アインシュタインは大動脈瘤破裂のためにプリンストンの自宅で倒れ、18日に息を引きとった。享年76歳。世界最初の商用原子力発電所として、イギリスセラフィールドのコールダーホール原子力発電所が完成する1年前の事であった(ガロア)。
「人間性について決して絶望してはならない。なぜなら我々は人間なのだから(アインシュタイン語録より)
参考図書 マイケル•ホワイト、ジョン•グリビン「素顔のアインシュタイン」(仙名紀訳)新潮社,
より)この書には日本人がいかに”科学的好奇心”の旺盛な民族だったかが分かるエピソードが書yかれている。1922年11月アインシュタインは日本を訪問した。たいへんな歓迎をうけたが、最初の大衆を相手にした講演は4時間を超えるものであったが、聴衆は最後まで静粛に聞いていた。翌日の講演では、さすがに長すぎると考えてアインシュタインは2時間30分に短縮した。ところが、終わると主催者は、今日の講演時間は昨日よりも短かったと気を悪くして文句をいったそうだ。