
むかし、シモーヌ・ヴェイユとその名を舌頭に転がすだけで血圧が上がった人は、いま何歳ぐらいになっているのだろか?作家の須賀敦子(1929-1998)は「本に読まれて」(中公新書)のなかで、その熱病的没頭の時代を「ヴェイユは、50年代の初頭に大学院で勉強していた私たち女子学生の仲間にとって灯台のような存在だった」と書いている。
ヴェイユは1909年パリに生まれ、人類史でも稀な激動の時代を火の玉のように生き、1943年イギリスで客死した女性哲学者である。1966年発行の京都大学新聞 (13638号)に哲学者の長谷正当(当時京大研修員)が、彼女の著「労働と人生についての省察」についての書評を出している。その書き出しは「ヴェイユの著書が最近紹介されはじめている」で始まるので、この頃からかなり読まれるようになり、さらに少し時代がすすむと、全共闘の論客も関心を持つようになった(彼女はレーニンやトロッキーもおおいに批判した)。
ヴェイユは体験(「事実との接触」)を媒介にして「真理に対する飢餓、実存に対する渇き」をもって太く短い人生を歩んだ。彼女は工場に入り実際、労働することによりそれが奴隷労働であることを実感した。奴隷状態を生み出す原因は「速さ」と「命令」という二つの事であった(この本質は現在も変わっていない)。もう一つの体験はスペイン動乱であった。それぞれ「不幸の経験」と「集団の経験」としてその思想に刻みこまれた。
ヴェイユ家は「ヴェイユ」姓が示すようにユダヤ系であったが、両親はユダヤ教に服さず、二人の子供もユダヤ教に接触させないように教育していた。そしてシモーヌ自身は思想的にユダヤ教を厳しく批判する立場をとった。
「残虐、支配への意思、敗れた敵に対する非人間的な軽蔑、そして力への敬服などを表明するユダヤ経典が、キリスト教に持ち込まれたことは不幸なことだ」と述べている。シモーヌ・ヴェイユの論法によると、ヒトラーの反ユダヤ主義は、この残虐なユダヤ経典の教えをそのまま反転模倣したことになる。最近のイスラエルのパレスチナ人民への暴虐は、まさに、これを証明しているとしてしか思えないのである。
参考書
大木健 「シモーヌ・ヴェイユの生涯」勁草書房
フランシーヌ・デュ・ブレシックス・グレイ 「シモーヌ・ヴェイユ」岩波書店 2009
追記(2024/11/06)
青年ヘーゲル学派のブルーノ・バウワーは1843年に「ユダヤ人問題」で、ユダヤ人が空想上の民族性にしがみついている限りユダヤ人の解放はありえないと述べた。マルクスはやはり1843年に「ユダヤ人問題によせて」でバウワーの論を批判しながら、国家と宗教とのかかわりについて展開している。ただしこの頃はイスラエルはまだ建国されていなかった。
















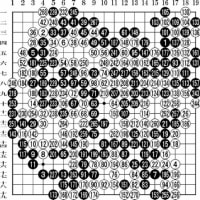









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます