
夕景のシダレザクラ↑ 冬桜である十月桜は満開に 子福桜もちらほら花を咲かせていた🌸
火となるのか吹雪となるのかおしら神 佐々木とみ子
「おしら神」つまりおしら様は柳田國男が『遠野物語』以来、養蚕の起源を説く異種婚姻譚としてよく知られるようになった。おしら様の一方が馬の顔であるのは、馬産地であることに関係しているという説もあるが、おしら信仰は古くは茨城あたりにも見られたというから、むしろ、馬が男性器のシンボルであったという梅原猛の説のほうが説得力がありそうだ。
また、おしら様は桑の木製とばかり限らないから、養蚕と結びついたのは後世になってからというのが今は通説となっているようだ。
二戸辺りは例外のようだが、おしら信仰はイタコと強く結びついている。オセンダクと言っておしら様の祭日にはイタコがやって来ておしら様を遊ばせる。子供がおしら遊びをする地方もあるが、これはイタコの代わりということだろう。イタコは死者を降霊するのみならず、その年の吉凶をも予言する。田植えの時期やその年に適した作物を語る。その家にもたらされるであろう慶事や忌み事も語る。その依代がおしら様なのだ。
梅原猛はおしら様が白木の神であることから、アイヌの神「シランバカムイ」にその原型を見ようとするが、それはひとまず於いておこう。ここでは、木でできた神の予言を聞く集いがおしら遊びであるということで十分だ。遊ばせるのはイタコでも子供でもいい。
私も四十五年前、このおしら遊びの真似事を見た記憶がある。昔話採集に遠野を訪れた時だ。農家の神棚に祀ってあったおしら様をとりだし、わざわざ遊ばせてくれた。「遊び」は「踊る」と同義である。おしら様はさまざまな布きれをまとっておいでだったが、白っぽかったと記憶している。鈴の音が伴っていた気もする。記憶違いかもしれない。おしら様のくるくる動くさまは、そのまま吹雪を連想させた。雪は厳しい寒さをもたらすが、豊作の予言でもある。雪の白さは、そのまま米の白さなのだ。
では、この句の火とはなんだろうか。吹雪は確かに炎をも連想させる。例年なら身の穢れを拭う清らかな火を連想することも可能だが、今年はやはり、原子炉の禍々しい火を連想してしまう。いや、「火となるのか吹雪となるのか」という緊迫した表現が、そう感じさせる。祈りは原初以来、自然を畏れ、自然に捧げられる営為なのだ。
マスクして墓標のごとく並びゐる 大場鬼奴多
風邪引きの集団を表現したのだろうが、福島の原子力発電所事故以来、放射能対策用のマスクも連想してしまう。そう読むとずいぶん怖い句になる。
霜柱関東耕土くすくすと 須崎 敏之
関東ロームは霜柱ができやすい粒子なのだそうだ。関東一円、朝日の光とともに耳には聞こえない笑い声が溢れる。
冬至かな血のみなぎれる耳ふたつ 上野まさい
冬空や地球の影は何処まで 増田 陽一
〈高野ムツオ主宰の好句鑑賞〉
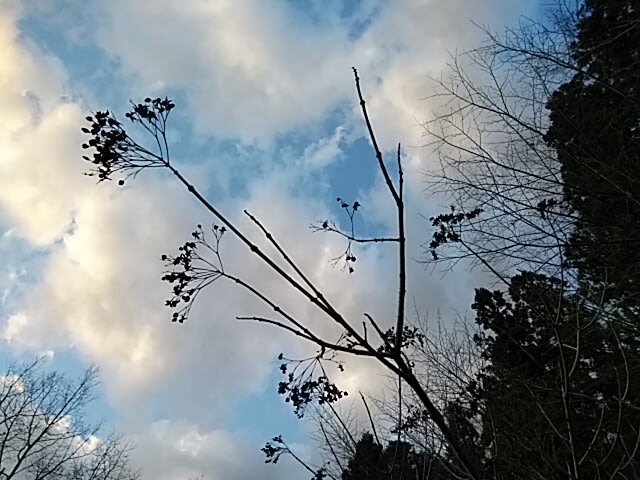
クサギの実の枯れたもの↑(ほとんどはその黒い実も失っていた)


























営業日を見ると来週の火曜日がラストで、あとは来年の11日まで長いお休みらしい。新しい小説月刊誌のお気に入り連載を読んで、ぐふぐふ笑い、午後6時の閉店までねばり、期せずして最後の客となった🥵
谷川民俗学の古い本が閉鎖書架に眠っていて、それを知り借り出した。やはり電子の世でも紙の本が一番である📚️電子ものは紙のものに比べてアタマに残りにくい、という統計結果も出ているのだという。
あ、あれはどこに出ていたかな?と本をパラパラめくるのも愉しいものである🥳
鶏モモひき肉でロールキャベツならぬロール白菜🥬を作ったら、ワタシにしてはとても旨くできた~🥘