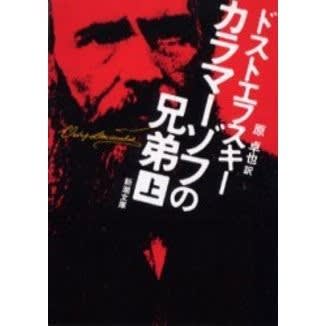
あ、前回本棚を見たら『カラマーゾフの兄弟』の上巻しかなかった……と書いたんですけど、あとからこの上巻をぱらぱら調べてみましたら、例のボルゾイ犬のエピソード、上巻の最後のほうに入ってました


その~、『カラマーゾフの兄弟』って、物語としてものすごすぎるので、わたし的にはあらすじですらうまく書ける自信ないので(というか、たぶんやたらと長くなる
 )、簡単にいうと好色で物欲の権化のような父親フョードル・カラマーゾフから生まれた、それぞれ個性の異なる三兄弟が、その後どのような運命を辿ったか……といった小説かなと思います。また、このしょうもない父親(笑)が、何者かに殺されたことで、その犯人が一体誰か――という、推理小説・犯罪小説としても読める、その他ドストエフスキーの哲学や宗教、思想がこれでもかとばかりに盛られた、世界文学屈指の超のつく名作でもあります。
)、簡単にいうと好色で物欲の権化のような父親フョードル・カラマーゾフから生まれた、それぞれ個性の異なる三兄弟が、その後どのような運命を辿ったか……といった小説かなと思います。また、このしょうもない父親(笑)が、何者かに殺されたことで、その犯人が一体誰か――という、推理小説・犯罪小説としても読める、その他ドストエフスキーの哲学や宗教、思想がこれでもかとばかりに盛られた、世界文学屈指の超のつく名作でもあります。それで、前回書いた「ボルゾイ犬に噛み殺された少年」の件に関して、ちょっと長くなるんですけど、すごく大切な箇所でもあるので、引用させていただきたいと思いますm(_ _)m
>>「将軍は二千人もの農奴を擁する領地に暮らし、威張りかえって、近隣の小地主たちを居候か、お抱えの道化みたいに見下していた。犬舎には数百匹の猟犬がいるし、ほとんど百人近い犬番がみな揃いの制服を着て、馬に乗っているんだ。ところがある日、召使いのせがれで、せいぜい八つかそこらの小さな男の子が、遊んでいるはずみに、なんとなく石を投げて、将軍お気に入りのロシア・ハウンドの足を怪我させちまったのさ。『どうして、わしのかわいい犬がびっこをひいとるんだ?』と将軍がたずねると、実はこの少年が石をぶつけて足を怪我させたのでございます、という報告だ。『ああ、貴様の仕業か』将軍は少年をにらみつけて、『こいつをひっ捕えよ!』と命ずる。少年は捕えられ、母親の手もとから引きたてられて、一晩じゅう牢に放りこまれた。翌朝、夜が明けるか明けぬうちに、将軍が狩猟用の盛装をこらしてお出ましになり、馬にまたがる。まわりには居候どもや、猟犬、犬番、勢子たちが居並び、みんな馬に乗っているし、さらにそのまわりには召使いたちが見せしめのために集められ、いちばん前に罪を犯した少年の母親が据えられているんだ。やがて少年が牢から引きだされる。霧のたちこめる、陰鬱な、寒い、猟にはもってこいの秋の日でな。少年を裸にしろという将軍の命令で、男の子は素裸にされてしまう。恐ろしさのあまり、歯の根が合わず、うつけたようになってしまって、泣き叫ぶ勇気もない始末だ……『そいつを追え!』将軍が命令する。『走れ、走れ!』犬番たちがわめくので、少年は走りだす……『襲え!』将軍は絶叫するなり、ボルゾイの群れを一度に放してやる。母親の前で犬に噛み殺させたんだよ。犬どもは少年をずたずたに引きちぎってしまった!……将軍は後見処分にされたらしいがね。さて……こんな男をどうすればいい?銃殺か?道義心を満足させるために、銃殺にすべきだろうか?言ってみろよ、アリョーシャ!」
「銃殺です!」ゆがんだ蒼白な微笑とともに眼差しを兄にあげて、アリョーシャが低い声で口走った。
「でかしたぞ!」イワンは感激したように叫んだ。「お前がそう言うからには、つまり……いや、たいしたスヒマ僧だよ!つまり、お前の心の中にも小さな悪魔がひそんでいるってわけだ、アリョーシャ・カラマーゾフ君!」
「ばかなことを言ってしまいましたけど、でも……」
「ほら、そのでもってのが問題なんだよ……」イワンが叫んだ。「いいかい、見習い僧君、この地上にはばかなことが、あまりにも必要なんだよ。ばかなことの上にこの世界は成り立っているんだし、ばかなことがなかったら、ひょっとすると、この世界ではまるきり何事も起こらなかったかもしれないんだぜ」
【中略】
「ああ、アリョーシャ、俺は神を冒瀆してるわけじゃないんだよ!やがて天上のもの、地下のものすべてが一つの賞讃の声に融け合い、生あるもの、かつて生をうけたものすべてが『主よ、あなたは正しい。なぜなら、あなたの道は開けたからだ!』と叫ぶとき、この宇宙の感動がどんなものになるはずか、俺にはよくわかる。母親が犬どもにわが子を食い殺させた迫害者と抱き合って、三人が涙とともに声を揃えて『主よ、あなたは正しい』と讃えるとき、もちろん認識の栄光が訪れて、すべてが解明されることだろう。しかし、ここでまたコンマが入るんだ。そんなことを俺は認めるわけにはいかないんだよ。だから、この地上にいる間に、俺は自分なりの手を打とうと思っているんだ。わかるかい、アリョーシャ、そりゃことによると、俺自身がその瞬間まで生き永らえるなり、その瞬間を見るためによみがえるなりしたとき、わが子の迫害者と抱擁し合っている母親を眺めながら、この俺自身までみんなといっしょに『主よ、あなたは正しい!』と叫ぶようなことが本当に起こるかもしれない。でも俺はそのとき叫びたくないんだよ。まだ時間のあるうちに、俺は急いで自己を防衛しておいて、そんな最高の調和なんぞ全面的に否定するんだ。そんな調和は、小さな拳で自分の胸をたたきながら、臭い便所の中で償われぬ涙を流して《神さま》に祈った、あの痛めつけられた子供一人の涙にさえ値しないよ!」
【中略】
「俺だって赦したい、抱擁したい、ただ俺はあらかじめ断わっておくけど、どんな真理だってそんなべらぼうな値段はしないよ。結局のところ俺は、母親が犬どもにわが子を食い殺させた迫害者と抱擁し合うなんてことが、まっぴらごめんなんだよ!いくら母親でも、その男を赦すなんて真似はできるもんか!赦したけりゃ、自分の分だけ赦すがいい。母親としての測り知れぬ苦しみの分だけ、迫害者を赦してやるがいいんだ。しかし、食い殺された子供の苦しみを赦してやる権利なぞありゃしないし、たとえ当の子供がそれを赦してやったにせよ、母親が迫害者を赦すなんて真似はできやしないんだよ!もしそうなら、もしその人たちが赦したりできないとしたら、いったいどこに調和があるというんだ?この世界中に、赦すことのできるような、赦す権利を持っているような存在が果たしてあるだろうか?俺は調和なんぞほしくない。人類への愛情から言っても、まっぴらだね。それより、報復できぬ苦しみと、癒やされぬ憤りとを抱き続けているほうがいい。たとえ俺が間違っているとしても、報復できぬ苦しみと、癒やされぬ憤りとを抱き続けているほうが、よっぽどましだよ。それに、あまりにも高い値段を調和につけてしまったから、こんなべらぼうな入場料を払うのはとてもわれわれの懐ろでは無理さ。だから俺は自分の入場券は急いで返すことにするよ。正直な人間であるからには、できるだけ早く切符を返さなけりゃいけないものな。俺はそうしているんだ。俺は神を認めないわけじゃないんだ、アリョーシャ、ただ謹んで切符をお返しするだけなんだよ」
(『カラマーゾフの兄弟』ドストエフスキー著、原卓也先生訳/新潮文庫)
この、カラマーゾフ家の次男、イワンくんは無神論者で、三男の弟の信仰深いアリョーシャくんに、「自分が神を信じない理由」、また「天国へ入る入場券をもらっても謹んでお返しする理由」というのを語る、これはほんの一部のエピソードに過ぎません。このボルゾイ犬に裂き殺された少年のエピソードの前にも、過酷な幼児虐待といったことをイワンくんは引き合いにだしていますし(このような罪のない小さな子が苦しむのを放っておく神など神ではない)、その他、戦争になればもっとひどい悲惨な状況が数限りなく起こりうる――という、大体のところそうした議論です。
一応先に書いておきますと、ドストエフスキーは同時代人であるトルストイと同じく、とても敬虔なクリスチャンでした。また、ドストエフスキー自身、「よくそれほどの苦しみに苛まれていながら、神さまを信じ抜けたものだ
 」というくらい、物凄い波乱の人生を送った方でもあります。でも、作品を読む限り、ドストエフスキー自身の信仰は揺るぎようのないものであり、イワンがいくつも並べ立てているように、「今まで歴史上にこれだけ酷いことが起きてるってのに、神の奴ぁ沈黙を決め込んでるんだぜ
」というくらい、物凄い波乱の人生を送った方でもあります。でも、作品を読む限り、ドストエフスキー自身の信仰は揺るぎようのないものであり、イワンがいくつも並べ立てているように、「今まで歴史上にこれだけ酷いことが起きてるってのに、神の奴ぁ沈黙を決め込んでるんだぜ 」ということなど、数限りなくあるわけです。
」ということなど、数限りなくあるわけです。イワンの主張というのは、誰が読んでもかなりのところ筋の通ったもので、このボルゾイ犬に関してのエピソードというのは、これでもまだまだ彼の主張のほんの序の口といったところで……でも、そこまですべて引用したり、そのひとつひとつについて「わたしはこう思った
 」的なことを書くと、誰も最後まで読めないくらい長くなってしまうので(汗)、今回はこのボルゾイ犬に噛み殺された少年に関してのみ、少し言及してみたいと思いますm(_ _)m
」的なことを書くと、誰も最後まで読めないくらい長くなってしまうので(汗)、今回はこのボルゾイ犬に噛み殺された少年に関してのみ、少し言及してみたいと思いますm(_ _)mその~、以前『神学的深遠』という記事のところでも書いたんですけど……イワンくんのこうした主張というのは、つづめて言えばようするに「悪というものが存在するのは何故か」、「また、神がもしいるならこうした悪を放置しておかれるのは何故か」という昔からある議論のことでもあるわけですよね。
それで、キリスト教でなくても、他の宗教でも結構「死後に裁きがある」ということは言われてたりしますし、あとは生まれ変わったあと、その悪い因業を背負ったままの魂は、次の世でろくな目に遭わないとか……人間がどうにか合理的に脳の中で「だからすべての人は最後、平等になるのだ」というのはかなりのところ無理がある――そうイワンは言いたいのだと思います。
何故かというと、これは実際にあった事件にかなり近い例なんですけど、ある女性がお金目的で突然車でさらわれて、ひどい暴行を受けて亡くなるという殺人事件がありました。母ひとり、子ひとりの家庭の若い女性だったのですが、裁判が終わって犯人が有罪になっても……娘さんは当然帰ってこないわけですし、その裁判に出席したりするのも、お母さんにとってはもう苦痛を通りこした地獄でしかありえない。こうした地獄を経験した方に「神を信じろだって?ハァ!?」と言われたとしたら――わたしだったらただ黙り込む以外ないような気がします。ただ、「娘さんのためにお祈りしています」ということ以上のことは、とても言えない気がする。
この場合、この娘さんが車の中で犯人に暴力を振るわれて感じた苦痛や恐怖というのが……ボルゾイ犬に噛み殺された少年の苦痛や恐怖に当たると思うんですよね。そしていつか、ボルゾイ犬に噛み殺された少年とお母さんが天国で再会し、永遠に幸福になるのだとしても――この八歳の少年が経験した苦痛や恐怖を贖ったことにはならないという、そうしたことです。だから「最後はみんな幸せ、ハッピーエンドになったんだからいいじゃないか」とか、「それ見よ。悪い奴らはみな地獄へいって今も苦痛に喘いでいる。しかもそれが永遠に続くのだ」というのが神だというなら……そんな神など自分には到底神だなどとは認められない、そうイワンは言いたいわけです。
割と最近あった事件でいうなら、ウクライナにおけるロシア軍の虐殺というのもそうだと思います。「今、彼/彼女は天国にいる」などと言われても……性的な暴行を受けて殺された女性、あるいはひどい苦痛の中殺された男性の苦痛、その時に感じたたとえようもない恐怖というのは――誰にも、何をもってしても贖えないものだ、ということです。それが仮に神であってさえ。
といっても、これは作中のイワンの考えであって、わたしもすべて頷きつつ読みましたが、結局のところ、わたし自身も帰結するところは、ドストエフスキー自身の信仰と同じということにはなります。つまり、そこまでのことを鋭く洞察して書くことが出来ていながら……イワンとは違い、ドストエフスキー本人は信仰を捨てる気はなく、さらにはその上で「神を信じる」ことの重要性を説いていると言っていいと思うわけです。
『カラマーゾフの兄弟』の中の有名なセリフに「もし神がいないのであれば、すべてが許されるはずだ」という言葉があります。わたしもカラマの中巻や下巻が今手許にないので(汗)、例によって頼りない記憶を元に書くのですが、下巻あたりでイワンは、ある人物から人を殺したという告白を受けます。しかも、それは無神論者の彼が「もし神がいないのであれば、すべてが許されるはずだ」というのを聞いて、「すべてが許されるのであれば、人殺しも許されるはずだ」との考えに行き着き、殺人を犯したというのです。
こうなると、イワンは間接的な殺人者ということになり……彼はこのことで苦悩し、ちょっと頭がおかしくなる――といった、カラマの下巻の最後のほうにそうした描写があったように記憶してます。
今回、『カラマーゾフの兄弟』を記事に取り上げたのはただの偶然ですが、ウクライナに攻め込んだロシアの生んだ文豪ドストエフスキーなら……このことについてどう思い考えることだろう――ふと、そう思わずにはいられませんでした。
本当に、ウクライナでの戦争が今すぐにでも終わることを心から願っています。
それではまた~!!


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます