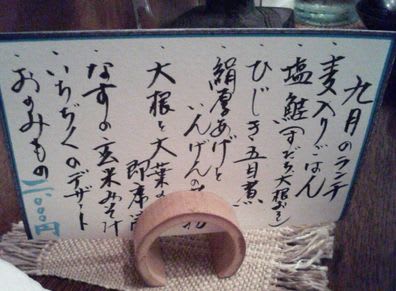2020年の東京オリンピックが決まって、
外国からの方々をどのように「おもてなし」するかが、
これからのオリンピックに向けての課題の一つになっています。
「おもてなし」の精神あふれるお茶に携わる一人としては、
友好の懸け橋になるべく、力を発揮したいところです。
「外国のお友達の茶道体験をお願いできますか」
そんな頼みをおひきうけして、昨日は楽しいひと時を過ごしました。
お客様はアメリカからいらした女性の方です。
とても日本に興味を持っていらして、
お茶を体験するにあたっては、いろいろとと勉強なさったそうです。
YouTubeの動画も見ていらしたとか。
入り口に正座して丁寧なお辞儀をなさったのは、こちらがビックリでした。
お連れしたお友達の事前のレクチャーもあったのでしょうね。
お部屋に入ると、まず「掛け軸を拝見するそうですね」
と床の前にすすみました。
その様子を拝見して私は、
初めての外国の方にはあまり説明しないことも、
詳しくお話しをすることにしました。
正座はOKということでしたが、それでも辛くなるといけませんから、
座布団には座っていただきました。
初めは薄茶を差し上げましょうと思っていましたが、
なんとぜひ「濃茶」を体験してみたいとのことで、
急きょ濃茶のお点前をすることになりました。
飲みやすく少し緩めに点てましたが、
はたして初体験の濃茶はどのような味に感じたでしょうか。
「美味しいです」とおっしゃっていたようですが、私はかなり心配しました。
きっと興味津々の気持ちが、なんでも美味しく感じさせてくれたとは思いますが。
名通訳のお友達のおかげで、
かなり深まった会話ができました。。
焼物のこと、道具のことなど、お茶の精神の部分まで、
五十代の大人の方ですから、一つ一つうなづいて、
嬉しそうに聞いてくださいました。
そして薄茶は、私が準備だけ整えて、
茶筅を振る部分だけを体験していただきました。
初めて茶筅を振ってお茶を点てる瞬間は、感動ものですものね。
何枚かベストショットも撮りました。
自国の文化を外国の方に、正しく伝えなくてはという気持ちと、
お茶を介して、初対面の人と、すぐにでもこんな和やかな時間が持てる幸せで、
お帰りになった後は、
「一期一会」「一座建立」の言葉を噛み締めながら、私も一服しました。
お・も・て・な・し、ちょっとはできたかしら。
いつも"ポチ"をありがとうございます。
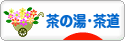 にほんブログ村
にほんブログ村