■沈黙の終わり 下/堂場瞬一 2021.8.2
『 沈黙の終わり 下 』 を読みました。
ぼくにとって興味深いのは、新聞社の内実です。
同じ新聞社の記者でありながら、社会部と政治部ではずいぶん体質が異なること。互いに反目しあうこともある。
現場記者としてスタートを踏み出した同期の者も、論説委員になったり、関連会社へ移ったりで、記者で定年を迎えるのはごく僅か。 「生涯一記者」を貫くことは難しい。
新聞記者は、週刊誌の記者をどう見ているかなど。興味津津。面白い話天こ盛り。
著者は、本郷響にこう語らせています。
「ル・カレは尊敬してます。八十歳を過ぎても取材して、時事ネタを作品に盛りこんでいますからね」
総理秘書官とか、官僚の忖度とか、政治部記者の話とか、今の日本の社会や政治の世界で生きる誰が実存のモデルか? と、想像をたくましくしてしまいます。
正義は行われなければならないんです。
でも、常軌から外れたことがあったら、伝説として残るんです。
本郷響 女性作家。ジャンルは警察小説。元警察官僚。
響は何か知っている。知っていて話さないスタンスだと古山は判断していた。彼女の話し方はいかにももったいぶった感じで、明らかに隠し事をしている人間に特有のものだ。記者が訊ねたら、誰でもすぐに事情を打ち明けてくれるものではない。秘密は、二律背反なのだ。誰かに明かしたいと思うと同時に、自分の中だけに秘めておきたいと考えるのも自然である。
森は、彼女は何かを知っていると断言した。彼の情報は信じたい。どこかに突破口があるはずだと古山は信じた。
「この前、気づきましたね」
「……メモですか。ありがとうございます」古山は頭を下げた。「正直、回りくどいやり方だと思いましたけど」
「ジョン・ル・カレ的な?」
「ああ」スパイ小説の大家だ。古山はスパイ小説は好きでよく読むのだが、ル・カレはあまり好みではない。「分かります」
「真似できそうにないけど、ル・カレは尊敬してます。八十歳を過ぎても取材して、時事ネタを作品に盛りこんでいますからね」
「この前のあれは、ル・カレの小説の真似事なんですか?」
「メールもメッセンジャーも便利ですけど、本当に大事な情報をやり取りする時には使えません」響が真顔になった。「直接会っている時に、証拠が残らない形でやり取りするのが一番安全です。もちろん、会っているところを誰かに見られたらアウトですけど」
「完全に安全な方法はない、ということですね。とにかく、あの情報は役に立ちました。構図が見えてきた感じがします。それで、倉……Kさんが黒幕だったんですか?」
イニシャルトークは面倒臭いものだが、響もすぐに受け入れることにしたようだ。真顔でうなずく。
「当時何があったか、私は正確に知りません。でも、常軌から外れたことがあったら、伝説として残るんです」
警察の捜査をストップさせた黒幕が、だんだんとあぶり出されてくる。
「倉橋さんですね」松島は指摘した。「当時、捜査二課長だった倉橋さん。今は総理秘書官」
「人によって、権力の捉え方は様々だ」突然飯岡が話を変えた。
「倉橋さんも、最初から政権中枢に入ろうと思っていたかどうかは分かりません。しかし今は、究極の権力の中枢にいますよね。政治家を裏から操るような仕事だ。黒子の方が本当の権力を行使できる----そんな風に考えていたんでしょうか」
「彼は、我々一般の警察庁職員とは、少し変わった考えの持ち主だった。そう、国家と国民に奉仕するという、警察庁職員に特有の考え方ではなく、権力に接近するための手段としてあの仕事を選んだのかもしれない」
「彼には、無茶な要求でも受け入れるだけの理由があったんですね? 見返りがあったから。違いますか?」
「育ちの悪い人間が権力を持つと、ろくなことにならない。彼の悪評は、あなたも聞いているのでは?」
黒幕は、総理秘書官の倉橋であることが分かった。
では、倉橋は誰のために、なぜ県警や事件に触れる者に圧力をかけるのか。
「政友党政権時代にも総理秘書官を務めていたというのが、よく分からないんですが……」
「官僚っていうのは、どんな人間が政権を握っても関係ないんだと思うよ。極端な話、日本が共産主義国家になっても、政権を支えると思う。日本の官僚は、共産主義政権でこそ真の力を発揮しそうな気もするけどな」
皮肉もたいがいにして欲しい……しかし、イデオロギー色がないという黒崎の説明には納得がいった。上にどんな政治家が来てもしっかりサポートし、自分の能力を全面的に提供する。そうしながらも、自分が理想とする筋をしっかり押し通す。日本の官僚はそういうものではないだろうか。もっとも今は、人事権を完全に握られているので、ただ上の顔色を窺い、ひたすら忖度しているだけだとよく批判されているが。古山は中央官庁の役人を取材したことがないから、本当かどうかは分からない。
いずれにせよ、倉橋が優秀で、政治家にも高く評価されているのは間違いない。しかし古山の頭には疑問が残った。
「倉僑さんは、基本的にずっと警察庁にいた人です。他の官庁への出向はなかった。桂木さんは、どこで倉橋さんを引っかけたんですかね? 桂木さんは、警察庁と何か関係があったんでしょうか」
それこそ、警察キャリアOBの政治家もいる。あるいは国家公安委員長として、警察庁に関わる政治家もいる。
「ウィキペディアで見た限り、直接の接点はないな」 一人納得したように、黒崎がうなずく。
「そうですか……」
「まあ、会うようにアレンジするのは難しいけど、倉橋さんのことを調べるぐらいはできるよ」
「お願いします」古山は頭を下げた。実際に会えるか、会えるとしてもいつになるかは分からないが、それまでにできるだけ情報を集めておいて損はない。
正義は行われなければならないんです。
「ふざけるな」松島は低い声で脅しにかかった。「お前は、指示は受けていないかもしれない。でも誰かに忖度して、俺を止めようとした。お前の大好きな政治家や官僚、それに会社の上層部に気を遣ってるんだろうが、大きなお世話だよ」
「おい----」
「お前はクソ野郎だ。何が一番大事なのか、分かっていない。仮にこれから民自党のクソ政権が戦争に突っ走っても、お前は止めないだろう。戦争に反対する人間を抑圧する側に回るよ。戦争が終わった後で何が起きるかも想像できないでな」
「言い過ぎだぞ」佐野の顔が紅潮する。
「ああ、言い過ぎだ」松島は認めた。「でもな、俺たちはずっと、クソみたいな仕事しかしてこなかった。権力の監視がマスコミの仕事なんて言いながら、実際には権力に取りこまれていた。俺だってそうだ。長く警察庁の担当をしていたのに、サツの不祥事を抜いたことは一度もない。むしろ、週刊誌に抜かれた。あの連中の取材力は、今や新聞より上かもしれない。ただ、奴らは正義感や義務感からやってるわけじゃない。問題は金だ。でかい見出しで週刊誌が売れるかどうかだけがポイントなんだ。どんなにいいネタでも、そういう姿勢である限り、俺は週刊誌の報道は認めない。俺たち新聞記者だからこそ、できることがある----青臭いだろうが、まだ信じてるんだ。それを、内輪から潰されたんじゃかなわない。お前は黙って引っこんでろ」
「俺は、お前のためを思って言ってるんだぞ」佐野の顔が強張った。
「それが本当ならありかたい話だけど、そもそもの考えが間違ってるんだから、受け入れられない」
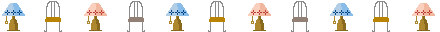
ぼくもブログで、料理店のつたない訪問記を書いています。
料理を紹介する文章を書くのは難しい。
美味しかった。旨かった。の連発になりがちです。
でも、ぼくの基本的な考えは、お店に足を運んで実際に食べてもらはなくては、始まらないと思っています。
小説でも料理の紹介場面は気になるので、勉強させてもらています。
口喧嘩になりかかったところで、最初の料理が運ばれてきた。ホワイトアスパラに薄い茶色のソースがかかったものと、プチトマトと青紫蘇を和えたものだ。食べていないと間が持たない感じがして、松島はすぐに料理に手を伸ばした。ホワイトアスパラにかかっているソースは、マヨネーズをベースに練りゴマを混ぜたもののようで、こってりした味わいがアスパラガスの淡白さに合う。プチトマトの方には酸味の効いたドレッシングがかかっていて、トマトの甘みが引き出されていた。
「お前、ここへ来たことあるのか?」松島は思わず訊ねた。
「いや、食ベログで点数が上の店を選んだ。あと、個室があるのが条件で」
「何だ、お前もネット頼りか」若い連中が、店選びでこういうロコミサイトを当てにしているのは、松島もよく知っている。自分の足で歩いて、時には失敗もしていい店を見つける方が楽しいと思うのだが、今は何より効率優先ということだろう。というより誰もが、失敗を恐れている。
『 沈黙の終わり(上・下)/堂場瞬一/角川春樹事務所 』
『 沈黙の終わり 下 』 を読みました。
ぼくにとって興味深いのは、新聞社の内実です。
同じ新聞社の記者でありながら、社会部と政治部ではずいぶん体質が異なること。互いに反目しあうこともある。
現場記者としてスタートを踏み出した同期の者も、論説委員になったり、関連会社へ移ったりで、記者で定年を迎えるのはごく僅か。 「生涯一記者」を貫くことは難しい。
新聞記者は、週刊誌の記者をどう見ているかなど。興味津津。面白い話天こ盛り。
著者は、本郷響にこう語らせています。
「ル・カレは尊敬してます。八十歳を過ぎても取材して、時事ネタを作品に盛りこんでいますからね」
総理秘書官とか、官僚の忖度とか、政治部記者の話とか、今の日本の社会や政治の世界で生きる誰が実存のモデルか? と、想像をたくましくしてしまいます。
正義は行われなければならないんです。
でも、常軌から外れたことがあったら、伝説として残るんです。
本郷響 女性作家。ジャンルは警察小説。元警察官僚。
響は何か知っている。知っていて話さないスタンスだと古山は判断していた。彼女の話し方はいかにももったいぶった感じで、明らかに隠し事をしている人間に特有のものだ。記者が訊ねたら、誰でもすぐに事情を打ち明けてくれるものではない。秘密は、二律背反なのだ。誰かに明かしたいと思うと同時に、自分の中だけに秘めておきたいと考えるのも自然である。
森は、彼女は何かを知っていると断言した。彼の情報は信じたい。どこかに突破口があるはずだと古山は信じた。
「この前、気づきましたね」
「……メモですか。ありがとうございます」古山は頭を下げた。「正直、回りくどいやり方だと思いましたけど」
「ジョン・ル・カレ的な?」
「ああ」スパイ小説の大家だ。古山はスパイ小説は好きでよく読むのだが、ル・カレはあまり好みではない。「分かります」
「真似できそうにないけど、ル・カレは尊敬してます。八十歳を過ぎても取材して、時事ネタを作品に盛りこんでいますからね」
「この前のあれは、ル・カレの小説の真似事なんですか?」
「メールもメッセンジャーも便利ですけど、本当に大事な情報をやり取りする時には使えません」響が真顔になった。「直接会っている時に、証拠が残らない形でやり取りするのが一番安全です。もちろん、会っているところを誰かに見られたらアウトですけど」
「完全に安全な方法はない、ということですね。とにかく、あの情報は役に立ちました。構図が見えてきた感じがします。それで、倉……Kさんが黒幕だったんですか?」
イニシャルトークは面倒臭いものだが、響もすぐに受け入れることにしたようだ。真顔でうなずく。
「当時何があったか、私は正確に知りません。でも、常軌から外れたことがあったら、伝説として残るんです」
警察の捜査をストップさせた黒幕が、だんだんとあぶり出されてくる。
「倉橋さんですね」松島は指摘した。「当時、捜査二課長だった倉橋さん。今は総理秘書官」
「人によって、権力の捉え方は様々だ」突然飯岡が話を変えた。
「倉橋さんも、最初から政権中枢に入ろうと思っていたかどうかは分かりません。しかし今は、究極の権力の中枢にいますよね。政治家を裏から操るような仕事だ。黒子の方が本当の権力を行使できる----そんな風に考えていたんでしょうか」
「彼は、我々一般の警察庁職員とは、少し変わった考えの持ち主だった。そう、国家と国民に奉仕するという、警察庁職員に特有の考え方ではなく、権力に接近するための手段としてあの仕事を選んだのかもしれない」
「彼には、無茶な要求でも受け入れるだけの理由があったんですね? 見返りがあったから。違いますか?」
「育ちの悪い人間が権力を持つと、ろくなことにならない。彼の悪評は、あなたも聞いているのでは?」
黒幕は、総理秘書官の倉橋であることが分かった。
では、倉橋は誰のために、なぜ県警や事件に触れる者に圧力をかけるのか。
「政友党政権時代にも総理秘書官を務めていたというのが、よく分からないんですが……」
「官僚っていうのは、どんな人間が政権を握っても関係ないんだと思うよ。極端な話、日本が共産主義国家になっても、政権を支えると思う。日本の官僚は、共産主義政権でこそ真の力を発揮しそうな気もするけどな」
皮肉もたいがいにして欲しい……しかし、イデオロギー色がないという黒崎の説明には納得がいった。上にどんな政治家が来てもしっかりサポートし、自分の能力を全面的に提供する。そうしながらも、自分が理想とする筋をしっかり押し通す。日本の官僚はそういうものではないだろうか。もっとも今は、人事権を完全に握られているので、ただ上の顔色を窺い、ひたすら忖度しているだけだとよく批判されているが。古山は中央官庁の役人を取材したことがないから、本当かどうかは分からない。
いずれにせよ、倉橋が優秀で、政治家にも高く評価されているのは間違いない。しかし古山の頭には疑問が残った。
「倉僑さんは、基本的にずっと警察庁にいた人です。他の官庁への出向はなかった。桂木さんは、どこで倉橋さんを引っかけたんですかね? 桂木さんは、警察庁と何か関係があったんでしょうか」
それこそ、警察キャリアOBの政治家もいる。あるいは国家公安委員長として、警察庁に関わる政治家もいる。
「ウィキペディアで見た限り、直接の接点はないな」 一人納得したように、黒崎がうなずく。
「そうですか……」
「まあ、会うようにアレンジするのは難しいけど、倉橋さんのことを調べるぐらいはできるよ」
「お願いします」古山は頭を下げた。実際に会えるか、会えるとしてもいつになるかは分からないが、それまでにできるだけ情報を集めておいて損はない。
正義は行われなければならないんです。
「ふざけるな」松島は低い声で脅しにかかった。「お前は、指示は受けていないかもしれない。でも誰かに忖度して、俺を止めようとした。お前の大好きな政治家や官僚、それに会社の上層部に気を遣ってるんだろうが、大きなお世話だよ」
「おい----」
「お前はクソ野郎だ。何が一番大事なのか、分かっていない。仮にこれから民自党のクソ政権が戦争に突っ走っても、お前は止めないだろう。戦争に反対する人間を抑圧する側に回るよ。戦争が終わった後で何が起きるかも想像できないでな」
「言い過ぎだぞ」佐野の顔が紅潮する。
「ああ、言い過ぎだ」松島は認めた。「でもな、俺たちはずっと、クソみたいな仕事しかしてこなかった。権力の監視がマスコミの仕事なんて言いながら、実際には権力に取りこまれていた。俺だってそうだ。長く警察庁の担当をしていたのに、サツの不祥事を抜いたことは一度もない。むしろ、週刊誌に抜かれた。あの連中の取材力は、今や新聞より上かもしれない。ただ、奴らは正義感や義務感からやってるわけじゃない。問題は金だ。でかい見出しで週刊誌が売れるかどうかだけがポイントなんだ。どんなにいいネタでも、そういう姿勢である限り、俺は週刊誌の報道は認めない。俺たち新聞記者だからこそ、できることがある----青臭いだろうが、まだ信じてるんだ。それを、内輪から潰されたんじゃかなわない。お前は黙って引っこんでろ」
「俺は、お前のためを思って言ってるんだぞ」佐野の顔が強張った。
「それが本当ならありかたい話だけど、そもそもの考えが間違ってるんだから、受け入れられない」
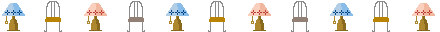
ぼくもブログで、料理店のつたない訪問記を書いています。
料理を紹介する文章を書くのは難しい。
美味しかった。旨かった。の連発になりがちです。
でも、ぼくの基本的な考えは、お店に足を運んで実際に食べてもらはなくては、始まらないと思っています。
小説でも料理の紹介場面は気になるので、勉強させてもらています。
口喧嘩になりかかったところで、最初の料理が運ばれてきた。ホワイトアスパラに薄い茶色のソースがかかったものと、プチトマトと青紫蘇を和えたものだ。食べていないと間が持たない感じがして、松島はすぐに料理に手を伸ばした。ホワイトアスパラにかかっているソースは、マヨネーズをベースに練りゴマを混ぜたもののようで、こってりした味わいがアスパラガスの淡白さに合う。プチトマトの方には酸味の効いたドレッシングがかかっていて、トマトの甘みが引き出されていた。
「お前、ここへ来たことあるのか?」松島は思わず訊ねた。
「いや、食ベログで点数が上の店を選んだ。あと、個室があるのが条件で」
「何だ、お前もネット頼りか」若い連中が、店選びでこういうロコミサイトを当てにしているのは、松島もよく知っている。自分の足で歩いて、時には失敗もしていい店を見つける方が楽しいと思うのだが、今は何より効率優先ということだろう。というより誰もが、失敗を恐れている。
『 沈黙の終わり(上・下)/堂場瞬一/角川春樹事務所 』

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます