2017年7月21日(晴れ)
さてさて葬儀を終えると、次にお金の工面が必要です。
主な支払いが伴う費用
①葬儀費用
・葬儀社への支払い
家族葬にして規模をなるべく縮小(配偶者の意思)で実施
※総額で約80万円
・僧侶への御布施
通夜前日:枕経
葬儀の朝:祠堂金、導師御布施、御布施、非時料、念誦料
葬儀の夜(お寺参り):初七日、五七日、満中陰、五重
自宅法要:初三日、初四日、初七日、二七日、三七日、四七日、初月忌、五七日、六七日、満中陰、百ヶ日)
※総額で約68万円
・地区の組内と付合先
代非時(13軒)
※総額 1万3千円
②入院費用
・保険分
診療費合計 2,312,910円
(初・再診料、医学管理料等、手術料、検査料、画像診断料、入院料等、包括)
※半分が手術料で1,203,350円、包括の554,070円、入院料等536,020円と続きます。
後期高齢者医療保険(月額最高額44,400円)のため患者負担は44,400円
・保険外
おむつ代 1,372円、文書料 3,240円、その他(死後処置)10,800円
私費合計額 15,412円
・入院診療費
合計(支払額)59,812円
③入居費用
敷金:50,000円 家賃合計(3ヶ月):93,600円 食材費:26,700円
入居時支払合計 170,300円
お金の工面
母の預金を引き落とし支払に回す事を選択した。
(母の年金2年分を超える金額が必要)
死亡届を提出すると口座が凍結されるのは、承知の事なので葬儀社と関係のない金融機関の口座を活用することとした。
葬儀の日から、3日かけてATMの一日の引落し限度額を引き出し4日目は残額を引落し残高を0円とした。
葬儀での香典を含め収支がほぼ一致して、無事に精算が終了しました。
ほっとしました。
昨年から親の万が一のことの対策を考えて行っていたことが少し役立ちました。
・車で出かけることが出来なくなっている。
・両親は金融機関のキャッシュカードを一切作成していない。
なので、金融機関の引落がとても不便となっていた。
対策
①定期預金を普通預金に変更しキャッシュカードを作成する。
定期預金の解約し全額を普通預金(新規作成)に移行する。
代理人(同居の家族でない場合はとてもシビアになる)での手続きを行う。
※詳細は2017-05-09のブログ参照
今回のお金は、このキャッシュカードが大活躍しました。
②通帳も印鑑も無くした通帳の再発行
代理での処理は難航した。
「喪失・発見届」「再発行依頼書」を作成するのですが、通帳がないので貯蓄種類と口座番号が分からない。
これでは、依頼書が書けない。
また、同じ印鑑で定期預金が複数あるとの行員の指摘でした。
それも依頼書に記入が必要ですとの説明。
更に、通帳および印鑑を無くした状況なので口座の利用停止を掛けますとのこと。
はてさて、どうしたら再発行できるやら。
※詳細は2017-05-11のブログ参照
③普通預金のキャッシュカードを作成(①の金融機関とは別なもの)
引落しのに不便さを解消のため。
このカードは、今後活用することになる。
その他
①遺産相続手続きの事前学習
被相続人の戸籍書類一式が必要なことと、その取得方法を事前に理解していたこと。
※詳細は2017-06-13のブログ参照
②葬儀社に対する事前学習
両親に対して、葬儀場についての意向を聞き出していた。
葬儀場における葬儀の流れ等のパンフを入手していた。
※配偶者の両親が昨年、今年と連続で逝去していて、身近な経験がある。
事前にやっておいた事が、これほどタイムリーに活用できるとは思ってなかった。
突然あれやこれやと行えないので、余裕をもって行えたのはとても良かったです。
特に時間のかかる手続きが、すでに済んでいたことは良かった。
やれやれでした。
さてさて葬儀を終えると、次にお金の工面が必要です。
主な支払いが伴う費用
①葬儀費用
・葬儀社への支払い
家族葬にして規模をなるべく縮小(配偶者の意思)で実施
※総額で約80万円
・僧侶への御布施
通夜前日:枕経
葬儀の朝:祠堂金、導師御布施、御布施、非時料、念誦料
葬儀の夜(お寺参り):初七日、五七日、満中陰、五重
自宅法要:初三日、初四日、初七日、二七日、三七日、四七日、初月忌、五七日、六七日、満中陰、百ヶ日)
※総額で約68万円
・地区の組内と付合先
代非時(13軒)
※総額 1万3千円
②入院費用
・保険分
診療費合計 2,312,910円
(初・再診料、医学管理料等、手術料、検査料、画像診断料、入院料等、包括)
※半分が手術料で1,203,350円、包括の554,070円、入院料等536,020円と続きます。
後期高齢者医療保険(月額最高額44,400円)のため患者負担は44,400円
・保険外
おむつ代 1,372円、文書料 3,240円、その他(死後処置)10,800円
私費合計額 15,412円
・入院診療費
合計(支払額)59,812円
③入居費用
敷金:50,000円 家賃合計(3ヶ月):93,600円 食材費:26,700円
入居時支払合計 170,300円
お金の工面
母の預金を引き落とし支払に回す事を選択した。
(母の年金2年分を超える金額が必要)
死亡届を提出すると口座が凍結されるのは、承知の事なので葬儀社と関係のない金融機関の口座を活用することとした。
葬儀の日から、3日かけてATMの一日の引落し限度額を引き出し4日目は残額を引落し残高を0円とした。
葬儀での香典を含め収支がほぼ一致して、無事に精算が終了しました。
ほっとしました。
昨年から親の万が一のことの対策を考えて行っていたことが少し役立ちました。
・車で出かけることが出来なくなっている。
・両親は金融機関のキャッシュカードを一切作成していない。
なので、金融機関の引落がとても不便となっていた。
対策
①定期預金を普通預金に変更しキャッシュカードを作成する。
定期預金の解約し全額を普通預金(新規作成)に移行する。
代理人(同居の家族でない場合はとてもシビアになる)での手続きを行う。
※詳細は2017-05-09のブログ参照
今回のお金は、このキャッシュカードが大活躍しました。
②通帳も印鑑も無くした通帳の再発行
代理での処理は難航した。
「喪失・発見届」「再発行依頼書」を作成するのですが、通帳がないので貯蓄種類と口座番号が分からない。
これでは、依頼書が書けない。
また、同じ印鑑で定期預金が複数あるとの行員の指摘でした。
それも依頼書に記入が必要ですとの説明。
更に、通帳および印鑑を無くした状況なので口座の利用停止を掛けますとのこと。
はてさて、どうしたら再発行できるやら。
※詳細は2017-05-11のブログ参照
③普通預金のキャッシュカードを作成(①の金融機関とは別なもの)
引落しのに不便さを解消のため。
このカードは、今後活用することになる。
その他
①遺産相続手続きの事前学習
被相続人の戸籍書類一式が必要なことと、その取得方法を事前に理解していたこと。
※詳細は2017-06-13のブログ参照
②葬儀社に対する事前学習
両親に対して、葬儀場についての意向を聞き出していた。
葬儀場における葬儀の流れ等のパンフを入手していた。
※配偶者の両親が昨年、今年と連続で逝去していて、身近な経験がある。
事前にやっておいた事が、これほどタイムリーに活用できるとは思ってなかった。
突然あれやこれやと行えないので、余裕をもって行えたのはとても良かったです。
特に時間のかかる手続きが、すでに済んでいたことは良かった。
やれやれでした。














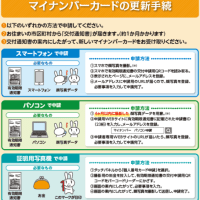
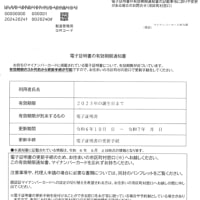










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます