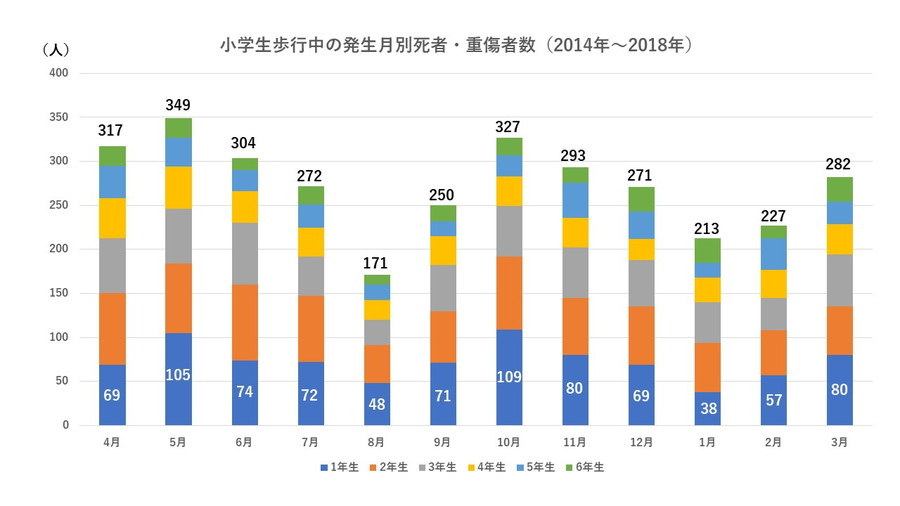必要な経済政策をめぐって話し合いがされたがあまり異論が出ないで近いような経済対策で纏っていました。
意外に取り上げられていないのが結局現実を見て組み立て行くスタイルの政策に共感する方が少ないのでしょう。
日銀の政策で全体の金利を低く抑えていますが、実際の市場金利は上昇しています。
また、インフレを抑えるにはそれなりの金利にする事が手法です。
円安の件でもそうなのですが、国民生活と隔った政策です。
そして賃上げにしてもされていない会社や足りない中小への支援が必要な訳です。
新型コロナでも対象を絞って支援して成功していました。
確かにその後に問題が残っていない訳でもないのですが。
その他にも非正規労働者への支援が必要です。
実質賃金が下がっている問題への検討も必要です。
反映されるかどうかが見えて来ません。
原因は政治家もそうなのですが政策秘書にしてもその辺りを意識しているのか見えて来ないのです。
それ以上に選挙対策の減税やら、財務省を意識しての話やら、経団連を意識しての法人税の件やらと見ている方向が国民生活ではなく選挙や官僚の方なのかと実感させられてしまいます。
個人消費の目がいかないのが何よりもGDP等への影響で大きいのかと思います。
更に中小での人手不足を解消する自動化やDX推進でもそれなりの効果が上げられるのにそう言う目の付け所がないのでしょう。
全政党がその点では現実的な視点で議論していかないとなかなか効果は出て来ません。
製造業の頑張りでインフレを抑えるような対策、コストダウンを検討させるにしてもそれをサポートするだけの資金支援は必要かと思います。
結局、単純モデルでの金融成果なんて古くて使えないのでしょう。
それなのに日銀を初めとして古典的な理論に縛られていたように思えてなりません。
分野毎で違うのですから、それに対応した金融政策が必要です。
また、お偉いさんの意向に忖度してしまうと必要な地域や分野への支援、投資が出来ないで国際的な競争力を失ってしまいます。
財政を守るようなフリをして現実には税収を見ていないのでは?
難しいのは国際的な競争に政治的な力が反対に規制されて外交的に国内産業の萎縮になっては失われた20年と同様の不信感しか持たれません。
政治だけでなく、経営者の能力開発もしないとダメです。
遅れているのもそうなんですが、若手のスタートアップが育たないのが一番の脆弱なのでしょう。