
■■■■■■90歳時代をどう生きる(2)■■■■■■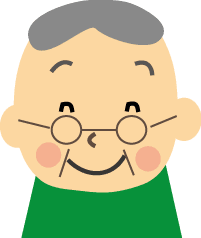
■「悔いなき我が人生」
●消費税25%で世界一幸せを謳歌するデンマークという国がある。
国際連合が調査した「人生の幸福度」では、日本は43位だった。
■「人生の満足度」調査
(順位) (国名) (10段階評価)
・1位 デンマーク 7,693
・2位 ノールウエ 7,655
・3位 スイス 7,650
・4位 オランダ 7,512
・5位 スエーデン 7,480
・6位 カナダ 7,477
・7位 フィンランド 7,389
・8位 オーストリア 7,369
・9位 アイスランド 7,355
・10位 豪 州 7,350
・43位 日 本 6,064●
●世界有数の先進国としては、残念というほかないが、国民性
として控えめな回答を選ぶ傾向があるという説もある。
また調査の専門家によると、日本と米国の所得と幸福感の関係
性は、両国とも所得が高い人ほど幸福感を強く抱く傾向がある
ようだが, 所得の高い人と低い人の幸福感のギャップ(開き)は、
米国より日本の方が大きいという。
やはり日本では、幅広い中間層の中でも、貧富の格差が相当
進みつつあると見ていいのではないだろうか。

●私の近辺で 最近こんな話をよく聞く。
・何かにつけ文句を言う高齢者が増えた。だが争うに足らない人が
多い。
・確かに自分が悪くても「ごめん」が言えない高齢者が増えてきた。
下流老人達の間違った「個」の主張でなければいいがと 危惧して
いる。
■「余後8万時間」
●スイス人作家のゾベティさんは、現役時代、現場でバリバリ陣頭指
揮をしていた、地位も名誉もある人が、いったん退職すると、見るも
無残に枯れた花みたいになってしまうのを見て、驚いているという。
定年は第2の人生というが、新しい人生が、すぐみつかるはずなど
ない。しかし、日本の定年者は、余後が気楽なパラダイスだと、思っ
ている人が多い。
●この人たちには、これからの自分たちの余後が、40年の現役時代
と変わらない長い時間だという認識が全くない。本当にこれでいいの
だろうか。、その啓発のために「旅立ちの季節]人生の最終章をいか
に生きるか、という本を上梓したという。

■「余後と現役時代は、同じ8万時間」
●次の数式は、ゾベティさんが言うように、人生の仕事期間(時間)
と定年後の予後の期間が,全く同じであることを実証したものである。
●「入社から定年まで」(週5日、休暇を除く)
1日12時間(通勤時間含む)X38年間(60歳―22歳)=114,000時間
●定年後の自分時間
・1日24時間―10時間(睡眠&入浴など)=14時間
・平均余命82歳―定年60歳=22年X年365時間 = 112,420時間
■「健康が余後最大の命題」
●定年後は、文字通り余後、殆どの人が気楽に暮らせると考えている。
しかも平均寿命は、益々のびる傾向にある。
しかし前章でもふれたように、現実には、健康で寿命年齢に到達する
人は、全体の約2割しかいない。
●殆どのひとは、途中で病に倒れたり介護生活を送ることになる。
全く予測はつかない。いかに健康で寿命を全うするか,余後の暮らしは、
定年後の高齢者によって最大の課題であると同時に,まさに自分との戦
いという事になる。 病に倒れると気楽な予後の夢は、一瞬にして吹っ
飛ぶことになる。
「健康」は予後を過ごす高齢者にとって、最大の課題といえる所以だ。![]()

■「欲張って生きよう」
●最後に慶応大学名誉教授米沢富美子先生の、高齢者の暮らしに取り
組む提言を紹介しておこう、
1)自分の可能性に限界を引かない
2)まずは行動に移す
3)めげない
4)優先順位をつける
5)集中力を養う
●有限の時間と能力の中で、なにはともあれ、欲張って生きるという
前向きのスピリットが、高齢者の健康を創るという。

■「健康という不滅のキーワード」
●「不調から見えて来た事」それはーーーー
ごく個人的な話で恐縮だが、昨年、私は、体調を崩して約1ヶ月程、
周辺の仲間に大変なご苦労をかけた。、
主治医や総合病院で総合診断を受けたが、異変は、見つからなか
った。しかし車と同様、古くなるといずこかに狂いが生じて、目に見
えない症状が少しずつ静かに進行していると考えたほうが正しい、
この歳にして自信と慢心がよくない事と、健康である事の素晴らしさ
を学んだ。

■「健康という実学」
●「健康」と言う言葉は、高齢者シニアにとっても企業にとっても、
はたまた国家にとっても、いまや不滅のキーワードになってきた。
確かに,「健康シニア」「健康企業」「健康国家」など、いずれの言
葉から何か健全なイメージが,ほのぼのと伝わったくるから不思議だ。
■「次回万国博の基本テーマは、健康と長寿」
●2020年東京オリンピックに続いて、2025年に開催される万
国博に大阪府が立候補することを宣言し、基本構想を発表した。
テーマは「健康と長寿」である。
高齢社会を迎え、安全な食と健康法、医療や福祉の最先端技術、体に
やさしい生活スタイルなどを大阪から全世界にアピールするという。
ここでも不滅のキーワード「健康」が、先端的な課題として決まった。
●戦後日本の英知を全世界にアピールした
1964年の東京オリンピックと1970年の大阪万国博から
2020年の東京オリンピックと2025年の大阪万国博まで
55年ぶり2度目の国際的な快挙が待たれる。
●かって戦後昭和の東京オリンピックと大阪万博を青春時代に体験し
た日本のシニアが,次の東京オリンピックと大阪博を体験するという
まさに健康の確証とい欲張りの快挙を,ぜひ実現して欲しいと願って
いる。ブロガーの私もその一人として、挑戦したい。
(因みに前回東京オリンピックの時、30歳の人は2020年次の東京オ
リンピックには86才になる。そして5年後の大阪万博には91才にな
る)
■「参考関連データ」
●第18回東京オリンピック (戦後昭和アーカイブス)
「昭和39年(1964年) 52年前の日本」
(項目) (実績) (付記)
・総人口 9718万人
・出生数 172万人 (出生率2,05%)
・死亡数 67万人
・婚姻数 96万件
・平均寿命 ・男性:68歳 ・女性:73歳
・経済成長率 11,2% 2桁 ●
・大卒初任給 2万1190円
・大学進学率 15,5% (現在52%)
・総理大臣 池田勇人 & 佐藤栄作
・当時30歳の青年現在82歳の後期高齢者
●当時の物価(昭和39年) (付記)
・葉書1枚 5円
・タバコ1箱 40円 (ピース)
・コーヒー 60円
・かけそば 50円
・エアコン普及率 1,7%
・テレビ普及率 87,8% (白黒)
・セリーグ優勝 阪神タイガース
・パリーグ優勝 南海ホークス (日本シリーズ優勝)

■■■戦後昭和の検証■■■
■「日本の人口の推移」
(昭和年次) (西暦) (人口)万人
昭和20年(1945) 7,218 終戦
昭和23年(1948) 7,810 ●団塊世代誕生
昭和25年(1950) 8,320
昭和30年(1955) 8,928
昭和35年(1960) 9,342
昭和40年(1965) 9,828 ●1964年 東京オリンピック
昭和45年(1970) 10,372 ●大阪万国博
昭和50年(1975) 11,194
昭和55年(1980) 11,706
昭和60年(1985) 12,104
昭和64年(1990) 12,278 ●昭和天皇崩御
平成28年(2016) 12,692 ●現在の日本
(出所;総務省)
■「日本の人口の推移」
→ http://www.bowlgraphics.net/tsutagra/03/
●上のURL→をタップして年代の推移グラフを左右に動かしてご覧ください、
■「戦後昭和の初任給の推移」
(年次) (大卒初任給) (公務員給与) (参考料金)
昭和25年 6,500円 ●入浴料 12円 はがき5
昭和30年 12,907円
昭和35年 16,115 12,900 ●豆腐 15円 日雇労賃494円
昭和40年 24,102 21,600
昭和50年 91,272 ●週刊誌 50円 日雇労賃972円
昭和55年 118,138 101,000 ●週刊誌 200円 日雇労賃
昭和60年 118,000
平成25年 198,000
■為替の動向と海外旅行の推移■
●「戦後昭和の海外旅行者数」 ■「円とドルの推移」
(年次) (西暦) (海外旅行者数) (円/ドル) 為替レートの動向
昭和25年(1950)-------- 360enn ●固定相場制で再開
昭和30年(1955)-------- 360
昭和32年(1952) 45,744 360
昭和35年(1960) 76,214 360
昭和40年(1965) 158,827 360 ●前の東京オリンピックの翌年
昭和45年(1970) 663,467 360
昭和46年(1975)-------- 349,33 ●変動相場制に移行
昭和50年(1980) 2,466,326 296,79
昭和55年(1985) 3,909,333 226,79
昭和60年(1990) 4,948,366 238,54
昭和63年(1993) 8,426,867 128,15
平成26年(2014) 16,903,388 121,04




























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます