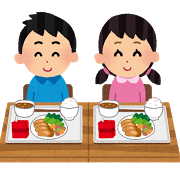六本木の東京ミッドタウンに姪二人とクリスマスイルミネーションを観に行った。


六本木は変わった。
高層ビルが林立して、六本木の交差点の目印のアマンドも新しくなり、「えええ? あれがアマンド?」と思った。
若いころに友達と行ったくらいしか六本木はよく知らないが、縁遠い感じはしていた。
いまは、若い姪たちは、六本木と言っても、別に臆することなく、フツウに歩いて、写真を撮りまくっていた。
クレープを食べに六本木ヒルズに移動。
そのあと、テレビ朝日にも行った。
その帰り、二人は、日本テレビの撮影クルーにつかまり、「ZIP」のモーションをする姿を撮影されていた。


六本木は変わった。
高層ビルが林立して、六本木の交差点の目印のアマンドも新しくなり、「えええ? あれがアマンド?」と思った。
若いころに友達と行ったくらいしか六本木はよく知らないが、縁遠い感じはしていた。
いまは、若い姪たちは、六本木と言っても、別に臆することなく、フツウに歩いて、写真を撮りまくっていた。
クレープを食べに六本木ヒルズに移動。
そのあと、テレビ朝日にも行った。
その帰り、二人は、日本テレビの撮影クルーにつかまり、「ZIP」のモーションをする姿を撮影されていた。