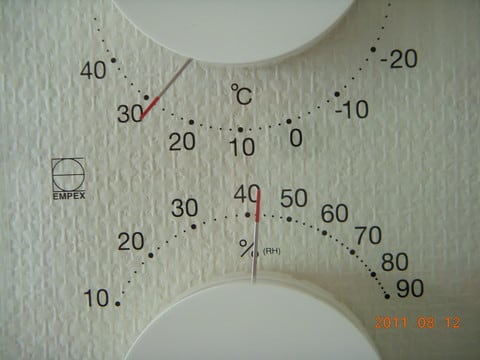前々回の 「782 輸出申告の保税搬入原則変更の実施迫る!」で、今年10月実施の同制度のための通達整備が8月10日付で行われたことを取り上げましたが、これに関する税関による説明会が始まるようです。
今回の制度は、輸出通関手続きの大変革で、特定の輸出者(たとえばAEO認定事業者)が対象ではなく、どの輸出者、貨物にも原則として適用されますので、通関業者、荷主など関係者の関心が高いものと思われます。
通達改正で、コンテナに輸出貨物を詰めたまま申告する場合に行われていた「輸出コンテナ扱い」の承認を受ける手続きがなくなりますし、税関の現品検査などの実処理についてざっと頭の体操をすると、どうするんかな?と疑問が出そうなことがいろいろ浮かびます。税関が説明する立場でない問題もありますが、どうやら説明会は盛況になりそうな感じで、暑いさなか、ご苦労さんです。
① 積出港のCYに向けての運送途上に輸出申告した場合、NACCSで区分「3」(検査)になったときの検査は、どこで行われるのか?この場合、CYに搬入する前に、税関の大型X線検査を経てからになるのか?
② ①の貨物がLCLで、10者の荷主の貨物が混載になっていて、検査は1社だけの貨物が対象の時の検査費用は、どの荷主の負担と考えるか?
③ また、この場合、10の荷主全部に検査がある旨通知すると、積み替えなどの要求が出るかもしれないが、その時の申告の訂正などはどうするのか?
④ さらに、LCLの混載の場合、検査を受ける以外の貨物の荷主に、他社貨物の検査がある旨を連絡することになっているがその意義は何か?
⑤ 荷主からは、保税地域に入れなくても通関できるということなら、工場~船積までのリードタイムが短くなるから、工場の出荷を後にずらしてもこれまでどおり輸出できるだろうと言われないか?
⑥ 輸出申告は、輸出貨物が実在することが前提と思われるが、生産、梱包、ラべリングなどのどの段階になれば申告可能なのか?
::::::::::::::::
この制度は荷主団体の経済界からの要請で導入されたものですので、輸出のリードタイム、経費、手続きなどの何かについて輸出者側にメリットがあるものと想定されているようで、それはどこに生じるのでしょう?
一方、本制度では、「輸出貨物の発生場所(工場など)から保税地域に入るまで」の倉庫や、作業場所、運送などは、すべて税関や関税法が管理・監督されていない状態の中で行われます。
この点は、AEO輸出者による輸出のように、「輸出貨物の発生場所(工場など)から保税地域に入るまで」が一貫してAEO制度の管理下でこれらの物流作業が行われるのとは異なります。
いわば、違法に輸出しようとする者からは、保税地域に入るまでは輸出申告をして税関の審査や検査の有無などの状況を知りながらの対策ができうるということになりますので、税関による輸出チェックの水準や防圧効果が低下しないようにする必要もあるため、実務上の対応ではいろいろ煩雑なことが出てくるかもしれないですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・
関西電力管内は、火力発電の事故で明日からが正念場とのこと。関西人も、交通機関の間引きが行われると、電力不足がとても身近になります。
むかし、電力がない時代の主な動力源は、水車や風車であり、牛や、馬でしたが、少なくとも、再生可能エネルギーへの依存度を高めることが要りそうな感じです。

今回の制度は、輸出通関手続きの大変革で、特定の輸出者(たとえばAEO認定事業者)が対象ではなく、どの輸出者、貨物にも原則として適用されますので、通関業者、荷主など関係者の関心が高いものと思われます。
通達改正で、コンテナに輸出貨物を詰めたまま申告する場合に行われていた「輸出コンテナ扱い」の承認を受ける手続きがなくなりますし、税関の現品検査などの実処理についてざっと頭の体操をすると、どうするんかな?と疑問が出そうなことがいろいろ浮かびます。税関が説明する立場でない問題もありますが、どうやら説明会は盛況になりそうな感じで、暑いさなか、ご苦労さんです。
① 積出港のCYに向けての運送途上に輸出申告した場合、NACCSで区分「3」(検査)になったときの検査は、どこで行われるのか?この場合、CYに搬入する前に、税関の大型X線検査を経てからになるのか?
② ①の貨物がLCLで、10者の荷主の貨物が混載になっていて、検査は1社だけの貨物が対象の時の検査費用は、どの荷主の負担と考えるか?
③ また、この場合、10の荷主全部に検査がある旨通知すると、積み替えなどの要求が出るかもしれないが、その時の申告の訂正などはどうするのか?
④ さらに、LCLの混載の場合、検査を受ける以外の貨物の荷主に、他社貨物の検査がある旨を連絡することになっているがその意義は何か?
⑤ 荷主からは、保税地域に入れなくても通関できるということなら、工場~船積までのリードタイムが短くなるから、工場の出荷を後にずらしてもこれまでどおり輸出できるだろうと言われないか?
⑥ 輸出申告は、輸出貨物が実在することが前提と思われるが、生産、梱包、ラべリングなどのどの段階になれば申告可能なのか?
::::::::::::::::
この制度は荷主団体の経済界からの要請で導入されたものですので、輸出のリードタイム、経費、手続きなどの何かについて輸出者側にメリットがあるものと想定されているようで、それはどこに生じるのでしょう?
一方、本制度では、「輸出貨物の発生場所(工場など)から保税地域に入るまで」の倉庫や、作業場所、運送などは、すべて税関や関税法が管理・監督されていない状態の中で行われます。
この点は、AEO輸出者による輸出のように、「輸出貨物の発生場所(工場など)から保税地域に入るまで」が一貫してAEO制度の管理下でこれらの物流作業が行われるのとは異なります。
いわば、違法に輸出しようとする者からは、保税地域に入るまでは輸出申告をして税関の審査や検査の有無などの状況を知りながらの対策ができうるということになりますので、税関による輸出チェックの水準や防圧効果が低下しないようにする必要もあるため、実務上の対応ではいろいろ煩雑なことが出てくるかもしれないですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・
関西電力管内は、火力発電の事故で明日からが正念場とのこと。関西人も、交通機関の間引きが行われると、電力不足がとても身近になります。
むかし、電力がない時代の主な動力源は、水車や風車であり、牛や、馬でしたが、少なくとも、再生可能エネルギーへの依存度を高めることが要りそうな感じです。