先日、鳥取県手話言語条例のCMについて書き込みました。
実はCMは公開後すぐに見ていて、ミスと指摘されている点にはすぐ気が付きました。
ただ、手話言語条例の制定は画期的なことであり、取り立てて言うほどのことではないんではないか、手話言語条例という大きなうねりのなかでむしろ水を差すことになるのではないかとも思い、書くこともしゃべることもしていませんでした。
しかし新聞報道がされた以上、発信すべきだと思い書き込みました。
ミスしたことを責め立てたり個人や団体を批判するというつもりは全くありませんでしたが、結果としてそう見えてしまう側面があったかもしれません。そして(影響力は少ないかもしれませんが)水をさしてしまったかもしれません。
また言葉足らずの面もあり、あえて再び書き込むことにしました。
何よりもまず、私自身が映像表現に関わる人間であり、手話を学び、学び続けている者だからです。
ある意味、全国のトップを走る手話言語条例を制定した鳥取県のCMをきっかけとして、いろいろ考えさせてもらう。
そういうことでもあります。
私が気になった点、というより関心を持った点は、どのようなコンセプトでこのCMが考えられ、そして何故ああいう手話表現が選ばれ、そのためにどういう演出がなされたのかという点です。
私にとってはCM内の、人によっては些末なことと思われる点が重要であったりするわけです。
一つずつ見ていきます。
まずコンセプトです。
広く言えば、手話言語条例を広く世の中に知らしめることです。
そしてCMのなかで間違いなく必要なものは手話です。大きく分ければ、3通りが考えられます。
ろう者が出演し、手話表現をする。
聴者が出演し、手話表現をする。
ろう者と聴者がともに出演し、それぞれ手話表現をする。
それぞれ一長一短はありますが、手話とは縁がなかった聴者が手話を学び始めた、そういった方向性が選ばれたわけです。
聴者である鳥取県出身の松本若菜さんに出演してもらい手話表現をしてもらうことで、県民の方々が親しみやすいような作りを狙ったのでしょう。
次の段階として、彼女にどういう手話表現をしてもらうのか?
その点は極めて重要で、様々な議論も必要でしょう。
誰が決めるのかという問題もあります。
日本手話なのか、しゃべりながらの日本語対応手話なのか、日本語対応手話であるが声は出さないのか、その他いろいろ考えられます。
日本語とは別の言語を強調するのであれば、もちろん日本手話が選ばれるべきでしょう。
一つの考え方として、彼女が鳥取県内の手話講習会で学んだ人と設定し、考えるのはありだと思います。
今ある現状から考えるということです。
例えば手話講習会で1年あるいは2年学んだ者の設定にして、そのことをもとに手話通訳者やろう者が手話表現を考える。
コンセプトが明解になれば手話通訳者やろう者も考えやすくなると思います。
CMでは、結果としてしゃべりながらの手話が選ばれていました。
何故かははっきりとはわかりません。鳥取県の手話講習会ではしゃべりながら手話を学んでいるのかもしれません。
でももし違うのであれば、少なくとも声は出さない方が良かったのではないかと思います。
手話は日本語とは違う言語であると言われてても、CMで日本語をしゃべっていたら
「なんだ日本語しゃべってんじゃん」
という印象を与えるからです。そういう印象も大切なのではないかと考えます。
もちろん、日本語をしゃべりながらであっても手話単語を織り交ぜる。
スタートはそこからでも構わない。
小さくとも、まずはその一歩を踏み出すことが、手話言語条例が理想とする社会への第一歩だ。
そういった考えもあると思いますし、このCMもそういうコンセプトで作られたのでしょう。
実は恥ずかしながら、手話言語条例の全文を読んでいませんでした。
遅ればせながらやっと読みましたが、感動的といってもいい内容でした。
そこに向かって進むんだ! そういう固い決意が見えるような内容です。
鳥取県のHPで読むことができます。
条例では、手話使用者としてのろう者という言葉は出てきますが、聴覚障害者、中途失聴者、難聴者という言葉は一切出てきません。
中途失聴者、難聴者にも配慮して、CMでは声を出すという風になったのかもしれません。
次にいきます。
彼女がその手話表現をおこなうために何がなされたのかという点です。(前述したことと多少だぶる点もありますが)
見た印象を一言で言えば、手話指導の方の手話を懸命に覚えて表現した、その違和感がありました。
手話は真似から始まりますが、うまい人の手話を真似しているだけで彼女の手話に見えない、そういった印象です。
自分としては、ミスと指摘されている箇所よりもむしろ気になった点です。
手話がたどたどしいから違和感があると言っているわけではありません。
CMのために映像を見て練習したふうにしか見えなかったということです。
もちろんそれが何か問題?と言われるかもしれませんが、私は気になってしょうがなかった。
自然には見えなかった。狙いがよくわからなかった。
それだけのことです。
例えば、予算と時間があれば、彼女が実際に手話をより学んで、彼女の手話で語る、そういったことも出来たかもしれません。
CMはミスが指摘された後、即座に訂正されたようです。
今後はミスがないように「今回の件を反省材料として、事前に関係団体で確認してもらうことを徹底する」そうです。
もちろんミスはない方が良いでしょうが、今後、ミスがあってはいけないという硬直的な議論ではなく、今回の件がもっともっと開かれた議論のきっかけになれば良いのではないでしょうか。
この件とは違いますが、制作サイドは充分に内容を理解し噛み砕いて作っていてミスではないにもかかわらず、監修者や関係団体の言うとおりにしなくてはならないことがあります。
まさかそうなることはないでしょうが。

















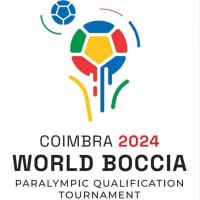

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます