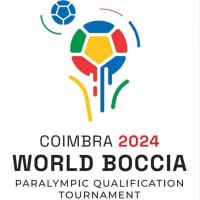前の記事の続編です。NHK「みんなの手話」に関してです。
2回目の放送も見てその後テキストも買い、目を通してみました。、
結論から言うと、手話を学び始める人、手話を既に学んでいる人にとって、かなりお勧めの番組になっています。
明らかに日本手話を教えていこうという方針になったようです。
昨年度の放送はまったく見ていませんから昨年との比較はできないのですが、テキスト第1課の冒頭に「手話は、聞こえない人や聞こえにくい人を主な話し手とする、日本語とは異なる文法を持つ一つの言語です。これから1年間、一緒に手話を学んでいきましょう。」と書いてあるからです。
これはまさしく日本手話のことです。
何故日本手話から学び始めたほうがよいかというと、聴者(聞こえる人)が日本語に近い日本語対応手話をある程度学んだ後に日本手話にステップアップしようと思ってもなかなかうまくいかないからです。多くの手話学習者がその時点で苦労、あるいは挫折しています。
逆に日本手話を学びその後必要に応じて日本語対応手話を身に付けるほうが、どちらかといえばスムーズに思えるからです。
日本手話から学び始めると日本手話以外に興味が持てなくなるということもあるかもしれませんが、もし通訳試験でも受けるのであれば両方できなくてはならないということになります。
私見ですが、これまでの公的な手話講習会はコミュニケーションツールとしての日本語対応手話をまず学び(別の言い方をすると手話に触れて)、やる気のある者や見込まれた者が地域のろう者たちから鍛えられるという図式だったのではないでしょうか。
(講習会が立ち上げられた初期段階はかなり事情は異なると思います)。
ろう者から鍛えられる段階というのが(日本語とは異なる文法を持つ一つの)言語としての手話を学ぶ時期だったのではないかと思われます。そういった意味では手話講習会で学んだ多くの手話学習者たちは(日本語とは異なる文法を持つ一つの)言語である日本手話に触れることなく終わったという人も多かったのではないでしょうか。教えるろう者側も“教え方”が確立していなかったという面もあったと聞きます。
ただ昨年から、講習会で使用するテキストに日本手話の文法を取り入れるようになったらしく、講習会で学ぶ手話も徐々に変わりつつあるようです。
番組の話に戻ります。
2回目の放送では、「千」を表す表現が「千」という字を空書する形ではなく、単に上下する形が紹介されていました。実際、ろう者間ではこちら(後者)の表現の方が使われます。以前は手話講習会では教えてくれませんでしたが教えるようになったでしょうか。前者の表現も番組内で説明されていました。
しかし番組及びテキストにも日本手話という言葉は一切出てきません。
日本手話という名称そのもの、また手話を日本手話と日本語対応手話に分けるということに異を唱えている人もいらっしゃるからだと思われます。そのあたりのことは、手話を知らない者からするととてもわかりにくい構図になっています。
テキストには、ろう文化に関するコラムがいくつか掲載されていて、とてもわかりやすくまとめられています。値段も362円+税ですので、なかなかお買い得です。
コラムのなかで脳科学からみた手話のことが取り上げられています。手話は脳のどの部分を使うのか?
答えは左脳の言語野です。脳科学の酒井先生の研究の成果ですね。映画「アイ・コンタクト」を作るため手話やろう者の世界を学んでいる際に脳科学からの知見を知り、本当に“目からうろこ”でした。
酒井先生とは公開前に一度対談させていただいたことがあります。対談後もいろいろと雑談になりましたが、印象的だったのは『手話を第二言語としてきちんと習得できれば脳で活動するのはほぼ言語野のみとなり、楽に会話や読み取りができるようになる』といった意味合いの内容。細かいニュアンスは忘れてしまいましたがおおよそそんな内容です。
英語を習得した人などが『英語が英語としてすっと頭に入ってくるようになった』などと言うのを聞いたことがあります。それと同じようなことでしょう。習得する前は脳のいろんな部分を使っていたのが、言語野のみで処理できるようになったということかと思います。
私はというと、今でもろう者の講演などに行くと頭のなかがパンクしそうになります。脳の様々な部分がフル稼働し走り回っている感じです。ただ時々、頭が手話脳になっているというか言語野しか動いていないのかも?と感じる時もあります。
本当に時々ですけどね。
ところでコラムのなかで一点間違いがありました。デフリンピックに関する情報ですが、競技種目として野球が挙げられていましたが間違いです。
世界的にはマイナーなスポーツである野球はデフリンピックでは行われていません。
ところでv6の三宅健さんは過去3年間手話を学んだことがあり、昨年から「みんなの手話」のナビゲーターになったようです。
前回ふれた彼の自己紹介に関してはもう何度もやっているということでしょうし、彼なりのやり方でやったのでしょう。
是非日本手話を学びそして理解し、発信していってほしいと思います。