昨年10月8日、鳥取県の県議会で手話言語条例が可決されました。
全国で初めてのことで、とても素晴らしいことですが、CMに手話の誤りがあったようです。
経緯は日本海新聞で知ったのですが、文末に記事を引用しておきます。
きちんとした検証も必要かと思い、CMの手話を書き出してみます。
というより、自分自身がどうなっているのか気になるので書き出してみます。自分の手話力はとりあえず棚にあげさせてもらいます。
CMの手話は日本語ををしゃべりながら、手で手話単語を表出しています。ですから当然日本手話ではありません。
具体的に見ていきます。
その前に手話を知らない方に最初におことわりしておきますが、手話単語は地方によって違ったりします。またろう者によってもかなり表現が違う場合もあります。まあこういう公式的なCMは教科書的な単語にした方が良いとは思いますが。
また(手の動き)のスラッシュ/とスラッシュ/の間が手話単語です。本来は手話単語でなくラベルと呼ぶべきでしょうが、ここでは手話単語と呼ぶことにします。
最初に音声日本語の部分を書き出してみます。
「私は手話を始めました。聞こえる人も聞こえない人も、手話でお話したり支え合うことが出来たら、もっと素敵な鳥取県になると思いませんか?私もがんばります」
「はじめまして、私の名前は」(この箇所に音声はありません)
次に手の動きも詳しくみていきます。
(音声) 私は手話を始めました。
(手の動き) 私/手話/始める/~ました
(音声)聞こえる人も聞こえない人も、
(手の動き)健聴者(=聞こえる人・聴者)/聾(ろう)/いっしょ
*記事によると以下の指摘があったそうです。
「聞こえる人」と表現する部分。口と耳の前に差し出した指を体から遠ざけて表現すべきところを、逆に外側から体に近づけて表現している。確かにそうなっています。
但し、流れで逆になる場合もあると思います。多くの人が意味は掴めると思います。私とてしてはむしろ、ろう/いっしょ の流れに違和感がありました。聾を表現した後に一度手を大きく広げるので幻惑されてしまいそうになりました。
(音声) 手話でお話したり支え合うことが出来たら
(手の動き)手話/お互い話す/助ける/助けられる/時
*お互い話すというのは、口話でしゃべっているという動きです。
*助ける/助けられる では、左手の親指は立っていません。それよりもむしろ右側の動きにメリハリがなく、するっと回転するので、そちらの方が気になってしまいました。
*時は、一瞬何か読み取れませんでした。
(音声)もっと素敵な鳥取県になると思いませんか?
(手の動き)もっと/良い/鳥取/県/なる/思う/~ですか?
*鳥取は、顔の前で親指と人差し指を2回合わている。鳥取の手話表現は、鳥と取るという手話の組み合わせです。
鳥はまだしも、取るはかなりわかりにくいです。私自身も音声を聞くか、口形を読まないと鳥取とはわからないかもしれません。むしろ岐阜と思ってしまうかもしれません。
県もわかりにくいと言えばわかりにくかったかもしれません。
(音声) 私もがんばります
(手の動き) 私/も/がんばる
(音声無し。発声はしているが、演出上別のナレーションに置き換えてある。口形は「はじめまして、わたしのなまえは」)
(手の動き)初めて/ あいさつ /私/名前
*普通は、初めましては、初めて/会う という単語で表現します。初めて/ あいさつは、普通に考えたら間違いだと思います。
初めてには、左手は添えてありませんでした。添えなくても通じます。ろう者は左手を添えていない場合も多いです。
教科書的に言えば、左手は添えます。
*名前は、関西というか東京とは違う表現の名前です。
以上。
単語の違和感について書き記しました。
ところでCMの手話を一番最初に見た時の正直な印象は、「しゃべりながらか…」でした。
以前は、手話講習会では喋りながら手話単語を表出するというものが多かったようですが、最近は声を出さないふうに変化してきています。もちろん最初から日本手話をナチュラルアプローチで学ぶということもあるわけですが。ちなみに、音声日本語とは違う言語である日本の手話は、日本手話です。
個人的には、しゃべりながらの手話はとってもむずかしく「名人芸」の世界だと思っています。例えば、しゃべりながら、尚且つ聞こえない人にも見やすい手話(間をおいたり、手話独特の文法を盛り込んだり…)だったり、とても今の私には出来ません。やるとすれば聞こえない人の読唇力に頼るしかありません。
手話がわからない人は、読んでいて何が何だかわからなかったかもしれません。
手話をめぐっては様々な考え方もあり、ここではこれ以上書きません。
またCMをめぐっての経緯は何となく想像は出来るのですか、憶測でしかないので書きません。
今後は監修をつけるとありますが、詳しい方にチェックを受けるべきなのは当然です。
しかし全体の方向性を決めるのは誰なのか?
このへんをごちゃ混ぜにしてはならないと思います。
しかしまあ制作サイド、つまりCMを作る側がある程度手話を理解していれば、過ちは防げるわけで。
啓発用DVDも制作されたようなので、手話に対する理解はある程度あったとほ思うのですが。
今後、全国の自治体でこういったCMを作る場合は、
「是非、私にCM撮らせてください!」
(以下 日本海新聞からの引用しておきます)
鳥取県が県手話言語条例の制定をPRするテレビCMで「手話の一部が誤っている」と、ろうあ団体などから指摘されていたことが6日、分かった。県は手話指導や収録を制作会社に任せており、放映前のチェックで間違いに気付かなかった。CMは県のホームページで閲覧可能で、県は注釈を加えるか公開を取りやめるか検討している。
CMは米子市出身の女優松本若菜さんが出演し、手話で条例の意義を呼び掛ける内容。昨年12月3~9日にかけ、山陰の民放3局が36回ずつ、計108回放映された。
間違いを指摘されたのは、松本さんが手話で「聞こえる人」と表現する部分。口と耳の前に差し出した指を体から遠ざけて表現すべきところを、逆に外側から体に近づけて表現している。「はじめまして」も「会う」が「あいさつ」になっていた。関係者によると「支え合う」や「鳥取」を表現する際の手の位置など、ほかにも違和感のある部分があるという。
CM制作費は790万円(啓発用DVD作成費含む)。県はコンペを経て米子市の制作会社に委託し、松本さんへの手話指導は同社が依頼した元手話通訳者が実施した。11月末に県の担当者が動画をチェックしたが、分からなかった。
県障がい福祉課は「収録までの時間がなかったのも一因。県ろうあ団体連合会の関係者に立ち会ってもらえば防ぐことはできた」と反省し、今後は同団体に監修してもらう。
県内のろう者の女性は、松本さんを擁護した上で「県だけが前に進むのではなく、手話を使う私たちに確認してほしい。一緒に進んでこそ意味がある」と指摘している。

















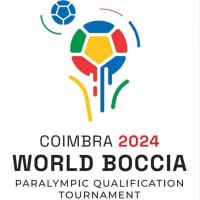

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます