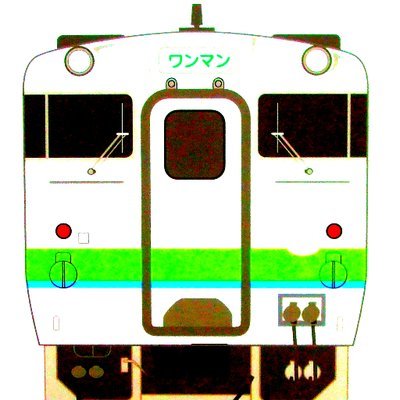JR北海道が、自社単独では存続と運行が難しく、さらに3年後には資金繰りの困難さから企業としての機能が停止すると発表して約1年が経った。
先日、JR北の再生推進会議の委員の一部が「有志による声明」という形で議論の推進を各方面に訴えると言う事態に至っている。
今後、1年という期限を区切って結論を出せという内容であった。
私としては、同会議の委員が言うように、この1年を無駄に過ごしたとは思っていない。先日のシンポジウムでも言われていたが、各沿線自治体では住民の意識調査・動態調査などを始め、首長や国会議員その他の関係者、有識者や学識者を招いての各種会合が開かれていた。
そのすべてが報道されているわけでもなく、事の重大性から、目立った進展も当然に無いので、委員の方々は実に歯がゆく感じたのであろう。
考えてみてもほしいが、一市町村ならともかく、広い北海道を多くの市町村に跨って走る2500㌔の二分の一の距離の路線に関した存続・維持の問題をわずか一年で検討、解決できるわけがないのは自明の理である。
JR北が言う上下分離は、財政状態が厳しいすべての自治体にとって、容易には受け入れることのできない提案であり、「はい、そうですか」と受け入れて、方向性を示すこができるわけはない。
しかし、そのような中、ここへきてようやく具体的な動きが、少しづつ顕在化してきた。
まずは、根室線(花咲線)沿線で、上下分離へ向けた検討の動きである。
財源としては、若桜鉄道を参考にいわゆる過疎債を活用しようというものであり、会合の中でJR北の西野副社長から示された。
上下分離自体に難色を示す北海道の幹部からは、真っ向から否定する声も出たと言うが、根室市としては検討に入ったようだ。
なお、過疎債は過疎地域自立促進特別措置法に基づいて発行される地方債で過疎地域に該当する市町村に限り発行が認められ、国からの地方交付税が増額されるため、元利償還の負担がは少なくなるというものである。
おそらくはJRが国交省から助言を受けた提案と思われるので実現性はある。北海道の189市町村のうち149市町村が過疎地域に指定されていることからすれば、一つの選択肢にはなる。

さらに、高橋道知事が鉄道運輸機構の特例業務勘定(いわゆる事業仕訳で明らかになった同機構の埋蔵金の一つで、国に返還され、機構経由で鉄道事業者に交付することになっている。JR北はすでに2800億円を貸与や基金積み増しの形で支援を受けている)を活用した支援の仕組みを策定するよう国に対して要請した。
ただし、これは上下分離ではなく、鉄道施設や車両への設備投資への支援を想定しており、JR北の提案とは大きな隔たりがある。
さらに各自治体にも財政負担の役割を持たせるという。
ただし、道を含む自治体が直接支援するのではなく、現存の北海道高速鉄道開発のような第三セクターに担わせることを念頭に路線維持の仕組みを詰めていくと言うものだ。
国からの支援が一時的なもので終わる懸念もあり、はたして、将来に渡って路線を維持できる継続性があるのかが問われる方策ではある。
さて、ここにきて動きが出てきたとは言っても、ほとんどが「鉄道の存続のための施策」だけが中心となっているのは、必ずしも良い展開とは思えない。
果たして利用者の利便性を前面に出したものかどうかは不明であるが、今年度末までに出るであろう、道の総合交通政策検討会議の答申によって、北海道の公共交通の体系が示される。
それによって、すべての鉄道路線が残るわけではないことは明らかな中、夕張市を除いては、いまだに代替交通などの検討が全くなされていないことに不安を覚える。
今までの廃止路線では、存続に動いた人たちも廃線が決まった途端に潮が引くように消えてしまい、雲散霧消してしまったという。
残ったのは乗合タクシーと小型バス。
たとえば、江差線廃線後のバスも廃線当初は便利になったと乗客でにぎわったが、利用客の減少が続いているそうだ。
やはり、ただ代替バスを走らせればよいと言うものではないことの教訓にはなっている。先日も留萌・増毛間の乗合タクシーにまばらな乗客しか乗らない様子が報道されていた。
廃線が決まってから、あわてて代替交通の確保に動き出しても、行き当たりばったりの不完全な交通体系が残るだけであり持続性に不安が残る。
それでは、大きな犠牲を払って鉄道を廃止した意味が失われてしまうではないか。
本当に必要な鉄道路線か、別の交通手段で良いのか、そうならばバスなのか、デマンドタクシーなのかライドシェアなのか、北海道民が一丸となって考える時が来ていると思う。国も地域公共交通活性化再生法でそれを求めている。
知事や地元選出国会議員を頼ったり責める前に、自らが考える時だ。新聞やテレビで報道された内容や、シンポジウムで識者が語ったことに反発して、反論ばかりしていても何も進まない。
今回、過疎債や特例業務勘定を活用すると言う案が出ているが、「国民のお金」を使う事なのだから、北海道民として公共交通を維持するという明確な意思表示をしなければ国民の理解を得ることはできないだろう。
このJR北海道の問題に札幌圏の住民が少し、無関心なのではないか。先日の札幌のフォーラムは、道が用意した会場の関係もあろうが、網走の会合と同程度の350人の参加であったし、多くは「自治体関係者か公共交通関係者」とみられる様子で、とても「オール北海道」などとは言えない。参加の申し込みを開催前に打ち切ったというのは、当初から参加人数を少なく見積もっていたのは間違いない。当日、コンベンションセンターや教育文化会館などは空いていた。
本来、多くの「一般市民」が事前申し込みなしで自由に参加できる会場を確保すべきであったのではないか。
また、開催の広報が期日が迫ってからであったことにも併せて疑問が残る。
やはり知事のアリバイ造りだったのか・・・・・。
さて、札幌市民の話に戻る。JR北海道が万一立ち行かなくなった時はもちろんだが、地方あっての札幌経済だと言うことを忘れていはいけない。
真冬に稚内、網走に車で出張するのか。バスの予約が取れなかったら出張はしなくて良いのか。
そして年間230万人にもなるインバウンド観光客の半数は、札幌から道内各地に向かう時は鉄道で移動している実態があることも忘れてはならない。
ジャパンレールパスは昨年度10万枚の需要があったそうだ
私は鉄道廃止論者ではない。江差線などは廃止すべきでなかったと今でも考えている。高台の駅からのアクセスに無関心だった地元自治体に責任があったと思うと無念の極みである。
営業マンのころ中度も走った江差までの国道は必ずしも優しい道ではない。
とは言っても、残念だが、現在の北海道のすべての路線が存続することは非現実的であると私は考えている。
以上、一部内容は何度かのフォーラムやシンポジウムで講演を伺えた名大の加藤先生、北大の岸先生のお話を引用させていただいたことを、心からの感謝を込めてお断りしておく。