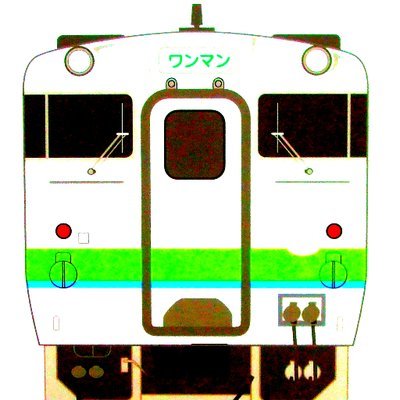桑園駅ホームからのJR北海道本社

先日、JR北海道再生推進会議のメンバーでもある高向巌北海道商工会議所連合会会頭が、「JR北海道の合理化の内容(廃線や駅廃止)は自治体から漏れ聞こえてくるだけで、JRからの公表がないのは疑問」とコメントされたようだ。
しかし、相変わらずJR北は口をつぐんだままで、廃止、減便についての情報は「最後通牒・ハルノート?」を受けた関係自治体関係者から報道機関に伝わるのみとなってる。
12月に公表するとしているが、これだけ大きな問題を、「決まりました」ということだけでは利用者不在、無視としか受け取ることは出来ない。
さて、現時点で漏れ伝わってきたところによると以下のようになる。
1.石北線、普通列車7便減。さらに2便は運行区間を 短縮する方針。要するに区間によっては9便減となる。
2.釧網線については6便減。東釧路―川湯温泉間、網走発着便など計6本の減便方針を伝えている。
3.室蘭線の苫小牧―長万部間を運行する普通列車で乗客数が平均20人以下の計7便について、区間短縮や廃止。私が良く利用する17時39分東室蘭発長万部行きは豊浦行きに短縮するという。
4.札沼線は浦臼・新十津川間を6便から2便に減便することはかなり以前に報じられた。
以上を合計すると現時点では26便の減便が判明したことになる。

上記以外にも、現在一日18便運行している夕張支線がこのまま維持されることは考えられない。
私は8便減の10便程度になるのではと予想する。
また、日高線は本来24便のところを現在、苫小牧・鵡川間の17便の運行になっており、このままの形で当面は固定することになるだろう。
この2線を合計すると15便、判明した26便と合わせて41便である。
JR北としては80便の減便を計画しているようなので、これだけでも、やっと半分。
今後、また「リーク」されるだろうが、第一に宗谷本線の名寄以北、山線の倶知安以南、根室本線の釧路・根室間、新得・滝川間も減便は避けられないものと見られる。さらに函館本線の長万部・森間、さらに留萌線全区間。
これらの区間では合計20便は減便となるのではと見られる。
そのほか、旭川・帯広近郊なども考慮すると70便にはなってしまう。判明した石北その他も追加される可能性もある。
80便の減便にはいさりび鉄道に移管する江差線は入っていないのかが不明確だが、それを除外したとしても、80便という数は、意外と実行可能な数字に感じてしまう。
国鉄民営化以来、漫然と放置してきたのが原因だと、もっともらしいことを副社長は語ったようだが、これは地方の足を確保したいとする企業の姿勢と努力だったからのことではないのか。
大都市圏を中心に「その通りだ」という方もいらっしゃるが、公共交通は単に損得だけでは成り立たない。現にバスでも交付金が出ているのだが、突然、鉄道だけに厳しい態度を取るのは時に阿るだけだ。
近年の、新自由主義的な風潮の側面を感じる。
なお、今のところは滝川発釧路行き2429Dと遠軽発旭川行き4626Dは噂が上がってこないが、「20人以下」という利用客を基準とするなら安心は出来ない。
2429Dはともかくも、4626Dは白滝・上川は空気輸送の状態なのだから・・・・。
間合い回送便の特殊性に期待しよう。
話が変わって、先日新幹線の料金が発表されたが、「値ごろ感」という言葉を無理して使うことはなかったであろうという印象だ(笑)。
値段とその商品の品質が釣り合っている、と消費者が判断する価格を「値ごろ」とか「お値打ち」というのであって、他の新幹線と比較して明らかに割高なあの料金では逆に「値ごろ」というより「高い」というイメージを持ってしまう。今までの在来線と比較するなら分かるが・・・。
ちなみに、東京―新函館北斗間の運賃と特急料金を合わせた普通車指定席の総額は2万2690円。「グランクラス」を使う場合は総額3万8280円。
東京―函館間の現行料金は2万200円だから、開業後2千円以上高くなる。所要時間は5時間半から「約4時間」に短縮されることを考えると、まあこんなものかなとは思う。
でも、函館から親函館の乗換えで30分は必要だから、実質「4時間半」なので、3時間も違うと、全く「値ごろ」とは思えない。
競合する航空各社の羽田―函館間は片道普通運賃が「大手」で3万5千円台で、鉄道事業本部営業部長は「競争力を十分保てる」と強調したそうだ。
航空機の各種割引の「実勢価格」で比較すると、やはり「高い」といわざるを得ない。
第一、1時間半と4時間半では勝負にならない。函館空港は市街地に近いことが特徴でもあるのだから。
さらに、青函を行き来するビジネスパーソンにとって、現在は青森弘前フリー切符8130円と言うものが良く利用されている。
これに類似したような切符が片道4350円往復8700円で設定されるのは「値ごろ感」は確かにある。
問題は使い勝手であり、早期割引との説明があったのが気になる。観光と違って、当日、明日で動くビジネスパーソンがどれほど利用できるだろうか。
私はフェリーにかなり流れると予測している。間違いなく割引価格を設定してくるだろうから。特に宿泊出張の場合は利用しやすいかも知れない。
いずれにしても当初はご祝儀で一定の利用客は望めるだろうし、そうあって欲しい。
気が付いたら空席だらけでは「我田引鉄整備新幹線」の汚名を晴らすことは出来ないだろう。
結局のところ新幹線は割引切符に期待したいところだな。
最後に母の家の近くの鷲別駅について一言、鷲別駅の無人化が決まったが、あの地域は人口も多いのでこの措置に疑問も感じるかもしれない。
しかし、ほとんど同じ地域に東室蘭駅があるので、実質的な不利益はほとんどないだろう。
あえて言うなら、遅い時間に高校生のたまり場のようになっている事実だ。監視カメラは彼らを守るというより彼らの非行を防止するのでは・・と母の知り合いが笑っていた。正直、駅員がいることを知らなかったそうだよ(笑)



















 。
。