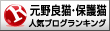熱燗の最初の一口が喉を通った瞬間に、高志は落ち着かぬ気持ちの出処に気が付いた。
高里久美その名は過去の時の中に、置いてきたつもりだったのに、再び胸の奥で囁き始めていた。
「私、高志と会うのはこれきりにするわ」
ある日、久美は映画の後の喫茶店を出る時に言った。
こともな気に「じゃあね」と、いつもの別れの時の口調だ。
思わず「じゃあ」と向けかけていた背を戻した。その眼につい今し方までコーヒーを飲みながら
向かい合っていた、平静な顔があった。
聞き間違いかと思って、その眼を覗きこんだ。
「残念だけれどそれしかないの」
表情と同じく静かな声、動かない黒い瞳。
ただっ広い劇場のような教室で、初めて見た時の驚きが高志の心に甦った。
その静かな美しさに囚われてから半年が過ぎていた。
初めて恋というものを知った。
それからの久美は高志にとって、生活の全ての中心だった。
決して口には出さなかったが、特にそぶりには見せなかったが、彼女と会っている時は煌く光の
中にいた。
二人の関係は不変の光りに包まれていると思った。その光りがしゃぼん玉のように、ポンと弾け
て消えてしまった。
見廻せば辺りは冬枯れの荒野だ。