それにしてもあの時何故、もっと言葉を尽して話しかけることが出来なかったのか。
「何故」と問いかけ続けることが出来なかったのか。
まるで絶対の力の前に打ち倒されたように、彼女の言うがままだった。
別れた後で延々と繰り返される疑問と、怨みとも怒りともつかぬ自問の嵐に、仕舞には疲れ果て何
も判らなくなってしまった。
その後で彼女が告げた最後の言葉だけが、深い淵のように彼を呑みこんでいった。
「あなたが解らないの」
時として聴こえるその言葉は、最初に呑みこまれた淵の底から、今度は瘴気のように湧き上が
り、彼を内側からじわじわと腐食し続けた。
忘れることが一番、そう思っていたのに再び目の前に現れた女は、いやでも彼の女を思い出させ
た。
顔や姿ではない、その迷いのない物言いと明瞭な性格、うかつにも洋食屋でカレーとハヤシのミ
ックスライスを食べるまでは気付かなかった。
その上もう一つ気付いたことは、美奈子のことが嫌いではないことだ。
塩辛を突っつきながら、一本の銚子が空になる頃、高志は美奈子には近付き過ぎないように注意
しなければならないと思った。
「懲りもせず」
自嘲気味に嗤(わら)いながら彼は、熱燗の追加を注文した。
雪かきというものが、どんなに骨の折れる仕事であるか初めて知った。










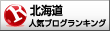


 がサクっと木の枝に刺した。
がサクっと木の枝に刺した。







