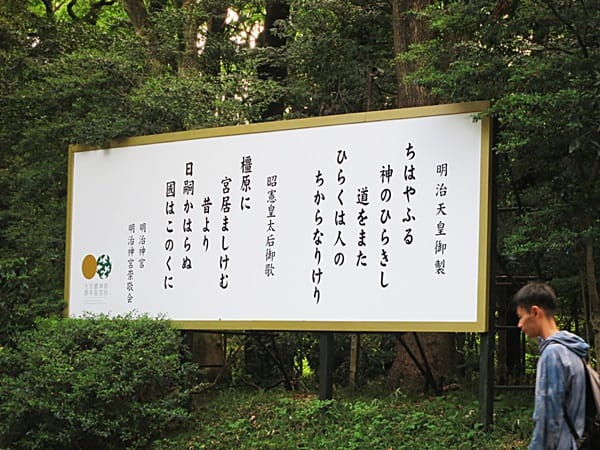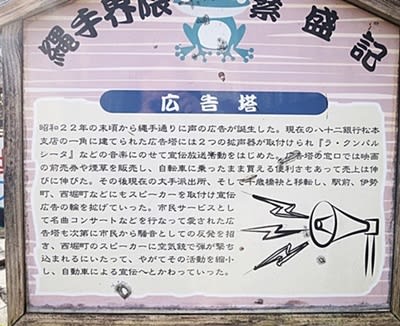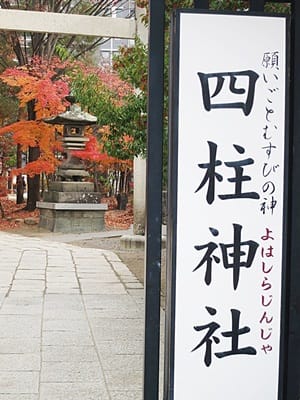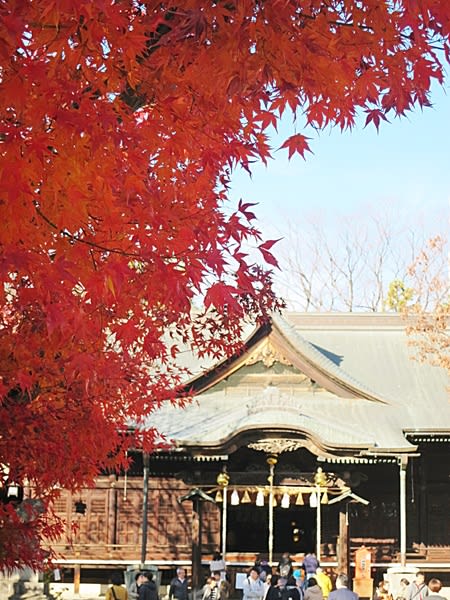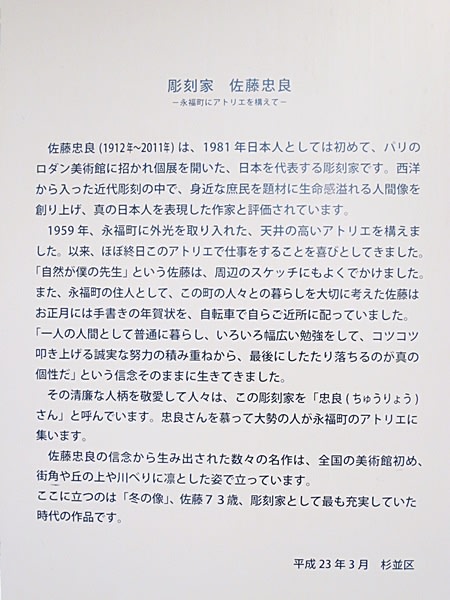大悲願寺
2019-12-01 | 寺社
Hi!みんな元気?引き続き過去の記録をUPしていくよ。これはまだ9月末の出来事。ということは、まだ2ヶ月分残っているということか。う~ん。がんばるぞ(何もそこまで・・・という声がきこえてきそうだね。笑)
この日はとても暑かった。JR五日市線、武蔵増子駅から徒歩15分、という情報だけで、線路沿いに延々歩いた。平日だったせいか、途中誰もいなくなり、一瞬不安になる時もあった。五日市線に乗るとたまに、車窓からチラットみえる山門のようなもの、お寺か?ずっと気になっていたお寺さん、大悲願寺、一本道でも何度か確認しながら、やっとたどり着いた。
長く西に続く土塀、お山に沿った造りなんだろうね。

長屋門(右から)

本堂に続く山門

仁王門

仁王門の前には金色山大悲願寺の寺名とその足元には季節の彼岸花が。(大きすぎて1枚には納められず)


とりあえずオープンな長屋門から潜入。入るとすぐこんな感じ。里山の寺って感じ濃厚。

右側に「お砂踏霊場」の説明がある。関東には四国霊場をまねた霊場が結構あちこちにある。

萩で有名だと聞き、遅れないようにと気を使ったが、もう、すでに散りかけていた。(涙)

石畳を歩いて左右を白萩に囲まれた本堂(東京都指定文化財)に到着。ひっそりと閉ざされている。
銅像の僧は誰だ?おそらく(確かめ忘れてゴメン)開山の祖と言われる洛陽出身の澄秀と思われる。

寺の縁起
大悲願寺は源頼朝が壇越となり、澄秀を開山として、平山季重が建久2年(1191)に創建した。その後四世澄遍が延文5年(1360)に再開、関東管領足利尊氏、氏満父子から寺領20石の寄進をうけ、徳川家康が関東入国した天正19年(1591)にも20石のご朱印状を受領、近隣に末寺32ヶ寺を擁していた。多摩88か所霊場59番、武蔵五日市七福神の大黒天。
さらに「五日市町史」によると、大悲願寺は真言宗豊山派、金色山吉祥院と号し、本山は大和の長谷寺である。開山の澄秀が醍醐の三宝院に関係あったため、長く同院末であったが、明治29年2月長谷寺に変わった。とある。

萩と像、なんて上品でエレガント!

本堂のお向かい山門から本堂までが参道になっている。萩が美しい。


この萩には言い伝え(?)がある。伊達政宗がここの萩の美しさに萩を所望したという手紙が存在するらしい。(東京都指定文化財)

説明なしで読める人いる?

本堂を通り過ぎると左手に鐘楼。

右手に、観音堂に続く坂道 そして五日市物語ロケ地の標識。五日市物語って??

あきるの市HPによると
五日市は、かつて江戸の暮らしを支えるエネルギーや材木の供給基地として発展しながら、豊かな文化圏を形成していた。幕末から明治初期には、五日市憲法草案を起草した千葉卓三郎や、看護師として国内外で活躍し、世界初のナイチンゲール記章を受けた萩原タケを輩出した。また、五日市には、歴史的価値のある寺社も多く、森林や里山に抱かれた折々の美しい装いは私たちの宝である。豊かな歴史や自然に恵まれた五日市は、まさに「東京のふるさと」といえる。そして古き良き時代の風情が残るまちの素晴らしさを発信すると共に、自然愛や郷土愛を育んでもらうため「市制15周年記念事業」として、「五日市物語」を映画製作することにした。(中略)なるほどあきる野市PR映画というわけなのだ。
観音堂 このお堂は「無畏閣」とも呼ばれ1794年建立。中には、国指定重要文化財「木造伝阿弥陀如来及脇侍 千手観音菩薩・勢至菩薩坐像」が安置されているそうだ。


観音堂の彫刻が素晴らしい。正面欄干の彫刻は地獄と極楽を表している。右、中央、左の順



堂宇

観音堂の周囲は霊場巡りコースなど、樹木やお山の形状を生かしたお庭造りがなされている。深淵な雰囲気と温かさが同時に伝わってくる。観音堂の方に足を踏み入れて、このお寺の様子がとても好きになった。地味だと思ったこのたたずまいが、心の扉を開いてくれた感じがする。


最後に山門

山門、天井の彫刻がまた素晴らしい。kinoppyの経験では、東京近辺には全国的に有名ではないと思われるお寺さんでも、素晴らしい彫刻に行き当たることが少なくない。それは、おそらく家康が江戸入部の際京都、奈良などから宮大工も一緒に上京して働いたためではないだろうか。

山門から見た観音堂

昔日本には中国から仏教が、韓国から陶器が伝来し、中国の人も韓国の人も日本人となった。京都から仏師や宮大工と呼ばれる人々が江戸に渡り、東京の人になった。そうやって文化が広く発展、真藤していったものと思われる。しかしながら、現在はどこの国も自国のことしか考えず、一発触発って感じ。なんだか、寂しいね。鑑真のように失明し6度めにやっと渡日した人もいるのにね。
こんなこともやっているらしいよ。お寺も努力しているんだね。

最後まで見てくれてどうも有難う。じゃ、みんな、またネ



この日はとても暑かった。JR五日市線、武蔵増子駅から徒歩15分、という情報だけで、線路沿いに延々歩いた。平日だったせいか、途中誰もいなくなり、一瞬不安になる時もあった。五日市線に乗るとたまに、車窓からチラットみえる山門のようなもの、お寺か?ずっと気になっていたお寺さん、大悲願寺、一本道でも何度か確認しながら、やっとたどり着いた。
長く西に続く土塀、お山に沿った造りなんだろうね。

長屋門(右から)

本堂に続く山門

仁王門

仁王門の前には金色山大悲願寺の寺名とその足元には季節の彼岸花が。(大きすぎて1枚には納められず)


とりあえずオープンな長屋門から潜入。入るとすぐこんな感じ。里山の寺って感じ濃厚。

右側に「お砂踏霊場」の説明がある。関東には四国霊場をまねた霊場が結構あちこちにある。

萩で有名だと聞き、遅れないようにと気を使ったが、もう、すでに散りかけていた。(涙)

石畳を歩いて左右を白萩に囲まれた本堂(東京都指定文化財)に到着。ひっそりと閉ざされている。
銅像の僧は誰だ?おそらく(確かめ忘れてゴメン)開山の祖と言われる洛陽出身の澄秀と思われる。

寺の縁起
大悲願寺は源頼朝が壇越となり、澄秀を開山として、平山季重が建久2年(1191)に創建した。その後四世澄遍が延文5年(1360)に再開、関東管領足利尊氏、氏満父子から寺領20石の寄進をうけ、徳川家康が関東入国した天正19年(1591)にも20石のご朱印状を受領、近隣に末寺32ヶ寺を擁していた。多摩88か所霊場59番、武蔵五日市七福神の大黒天。
さらに「五日市町史」によると、大悲願寺は真言宗豊山派、金色山吉祥院と号し、本山は大和の長谷寺である。開山の澄秀が醍醐の三宝院に関係あったため、長く同院末であったが、明治29年2月長谷寺に変わった。とある。

萩と像、なんて上品でエレガント!

本堂のお向かい山門から本堂までが参道になっている。萩が美しい。


この萩には言い伝え(?)がある。伊達政宗がここの萩の美しさに萩を所望したという手紙が存在するらしい。(東京都指定文化財)

説明なしで読める人いる?

本堂を通り過ぎると左手に鐘楼。

右手に、観音堂に続く坂道 そして五日市物語ロケ地の標識。五日市物語って??

あきるの市HPによると
五日市は、かつて江戸の暮らしを支えるエネルギーや材木の供給基地として発展しながら、豊かな文化圏を形成していた。幕末から明治初期には、五日市憲法草案を起草した千葉卓三郎や、看護師として国内外で活躍し、世界初のナイチンゲール記章を受けた萩原タケを輩出した。また、五日市には、歴史的価値のある寺社も多く、森林や里山に抱かれた折々の美しい装いは私たちの宝である。豊かな歴史や自然に恵まれた五日市は、まさに「東京のふるさと」といえる。そして古き良き時代の風情が残るまちの素晴らしさを発信すると共に、自然愛や郷土愛を育んでもらうため「市制15周年記念事業」として、「五日市物語」を映画製作することにした。(中略)なるほどあきる野市PR映画というわけなのだ。
観音堂 このお堂は「無畏閣」とも呼ばれ1794年建立。中には、国指定重要文化財「木造伝阿弥陀如来及脇侍 千手観音菩薩・勢至菩薩坐像」が安置されているそうだ。


観音堂の彫刻が素晴らしい。正面欄干の彫刻は地獄と極楽を表している。右、中央、左の順



堂宇

観音堂の周囲は霊場巡りコースなど、樹木やお山の形状を生かしたお庭造りがなされている。深淵な雰囲気と温かさが同時に伝わってくる。観音堂の方に足を踏み入れて、このお寺の様子がとても好きになった。地味だと思ったこのたたずまいが、心の扉を開いてくれた感じがする。


最後に山門

山門、天井の彫刻がまた素晴らしい。kinoppyの経験では、東京近辺には全国的に有名ではないと思われるお寺さんでも、素晴らしい彫刻に行き当たることが少なくない。それは、おそらく家康が江戸入部の際京都、奈良などから宮大工も一緒に上京して働いたためではないだろうか。

山門から見た観音堂

昔日本には中国から仏教が、韓国から陶器が伝来し、中国の人も韓国の人も日本人となった。京都から仏師や宮大工と呼ばれる人々が江戸に渡り、東京の人になった。そうやって文化が広く発展、真藤していったものと思われる。しかしながら、現在はどこの国も自国のことしか考えず、一発触発って感じ。なんだか、寂しいね。鑑真のように失明し6度めにやっと渡日した人もいるのにね。
こんなこともやっているらしいよ。お寺も努力しているんだね。

最後まで見てくれてどうも有難う。じゃ、みんな、またネ