





以下、amazonよりストーリーのコピペです。
=====ここから。
宗教裁判が激化している中世のヨーロッパで、イタリアの修道院での会議にイギリスの修道士ウィリアム(ショーン・コネリー)と、見習いのアドソ(クリスチャン・スレーター)が参加していた。そこで不審な死を遂げた若い修道士の死の真相解明を任された二人が謎を探るうちに、再び殺人事件が発生する……。
=====ここまで。
ちゃんとあらすじを書くと長くなるので、amazonさんのをお借りしました。
☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜
Eテレの「100分de名著」で9月に取り上げた名著がウンベルト・エーコの『薔薇の名前』でした。この中で時折引用されていたのが本作の映像。原作は難しいと聞いていたので手に取ることさえなかったけれど、番組内で使われていた映像を見て、映画はなかなか雰囲気とか面白そうだと思ったので見てみることにしました。
◆笑っちゃダメなのよ。
サスペンスとして見ても十分面白いと思うけれども、キリスト教の歴史を知らないと、多分面白さ半減なんだろうな、と感じた。
本作でも終盤の見所は“異端審問”なんだけれども、異端審問というと、やはり私はDDL主演の『クルーシブル』を思い出す。こちらは、魔女裁判だったけど、中身は似たようなもんで、神の教えに逆らったか否かを審判される。信仰を持たない人間から見れば狂気の沙汰なんだけど、神を信じる者の前では、「不合理」なんて言葉は何の意味もないのが、見ていて虚無感を覚える。
本作における連続殺人の鍵は、この修道院の属するベネディクト会の厳しい戒律「いかがわしい話、ばかばかしいおしゃべりはいけない。むやみに笑ってはいけない」という、“笑いの禁止”である。なぜ?? と思うけれども、笑いが堕落を招くという、ものすごくおかしな思考回路の下にできた戒律らしい。しかし、アリストテレスの著書「詩学」には、笑いの重要性が説かれており(つまり、笑いとは“知”への探求、考えることなくして笑いは起き得ないということ)、この「詩学」が修道院の宝である図書館に納められていることから、この本を読んだ者が次々に死んでいった、ということなわけ。
何で本を読んだだけで死ぬのか、というと、その本には図書館長のホルヘが毒(ヒ素)を塗り込めていたから。指を舐めてページをめくる度に、ヒ素を舐めることで、その本を読んだ者は死へと至るという次第。ホルヘは、戒律に忠実だったのだ。
でも、異端審問と連続殺人事件は、実は直截的にはほとんど絡み合っていない、ってのもまたミソである。連続殺人事件を縦糸に、宗教のいかがわしさをヨコ糸にした、なかなか入り組んだ構造。ただ、異端審問も連続殺人も、神への冒涜が断罪されるという意味では通底している。
『クルーシブル』の裁判官もそうだったが、本作の異端審問官も、見ていて吐き気を催すほどの邪悪さで、どうしてこの人たちが異端を裁けるのか、この自己矛盾を、なぜ皆黙って見過ごしているのだろうと、見ていてイライラしてくる。こんな人たちが権力の座にあること自体が、おぞましい。まあでも、本作ではこの異端審問官は最期に悲惨な末路を辿るので、多少溜飲が下がるというもの。
詰まるところ、当時の(今もか?)キリスト教とは、信者に思考を禁じているのである。笑いの禁止なんて、その最たるものだと思うが、宗教の怖ろしさはココにある。考えることを許さないのだ。神の教えが第一、それさえ守っていれば良いと。なぜそのような教えを説くのかと考えてはいけないわけ。考えたら疑問が湧き、神の存在が脅かされるからだろうけど、まあ、今の世の中でも、宗教界以外でも、考える人間が厄介者扱いされるという現実は、本作の舞台である中世とあまり変わっていないのでは?
ちなみに、「100分de名著」で原作の解説をしていた和田忠彦氏は、原作は、「人間の知への驕りへの警告や、言語に翻弄され続ける人間の宿命」が隠れたテーマだと言っていた。最終回には、中沢新一がゲスト出演してイロイロ喋っていたが(「反知性主義」とか話していたように記憶しているが)、正直なところ、中沢新一の話なんかよりも、和田氏の解説をもっと聞きたかったわ。
思えば、権力者が最も恐れるものが、笑いかもね。風刺画とか、権力を笑うものだし。笑いの的にされたんじゃ、権威もへったくれもあったもんじゃない。
ただ、この映画を見る限りは、そこまで読み取るのは少々難しいと感じる。宗教の持ついかがわしさは十分伝わるけれども、原作を読んだ上で見れば、また違う印象を持つのかも知れない。
◆その他もろもろ
とにかく、本作の見所は、その世界観でしょう。ロケはドイツだったらしいけど、修道院の建物といい、図書館の構造といい、衣裳といい、ちょっと小汚い雰囲気とか中世の感じ(って、中世の修道院なんて見たことないんだが)が出ていて、さぞや美術担当の方々は大変だっただろうなぁ、と感心。
“笑い”が厳禁だから、登場人物たちの笑顔がほとんどないのも、また印象的。でも、その剃髪した頭部は、いけないとは分かっていても笑えてしまう、、、。まあ、日本の時代劇に出てくる武士の頭部も、外国の人から見れば十分笑えると思うけど。
ショーン・コネリーは、なかなか渋くてgoo。邪悪の化身みたいな異端審問官を演じていたのは、『アマデウス』でサリエリを演じていたフランク・マーレイ・エイブラハム。こういう屈折した悪役がハマる貴重な俳優さんだわ。
クリスチャン・スレーターが、可愛くてビックリ。私の中では、『告発』のイメージが強いけれど、ゼンゼン違う雰囲気でありました。途中、村の娘とのセックスシーンは、かなり激しい描写で時間も長く、あれは撮影が大変だっただろうなぁ、、、などと見ながら思ってしまった。
あと、連続殺人の死体が、これまた印象的。樽の中に逆さに入れられて『犬神家の一族』みたいに脚がニョキッと天に向かって出ていたり、浴槽の中に目を見開いたまま沈んでいたり、画的にも面白かった。もしかして、マジで『犬神家~』からインスパイアされたんじゃない? って思うほどそっくりだったんだけど、原作でもああいう殺され方していたのかしらん??
何となく敷居の高いイメージのあった本作&原作だけど、映画は、見てみたら意外にそうでもなかったので、原作にも挑戦してみようかな、と思った次第。
ヒ素は古くからの毒なのね、やっぱり。
★★ランキング参加中★★
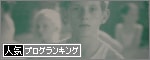
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます