
旅の準備その4はタイヤ交換編です。一万二千キロも走りきった現在のタイヤでは旅に不安がありますので交換を試みました。
今までのタイヤは前後ともミシュランのアナキー2というもの。大型のオフロードツアラーに使われることの多いタイヤです。購入価格ははっきりと覚えてはいませんがチト高かったように思います。
この「アナキー2」は後輪はラジアルですが前輪はラジアルではありません。その為かは知りませんが前輪の方が早く減ってしまっていました(乗り方にもよるんでしょうが)。ですがオフ車用のタイヤとしては長持ちのする方でした。
以前に250CCのオフ車にダンロップのD604という銘柄のタイヤを履かせたことがありましたが約6000キロで寿命に達してしまいました。高速道を1000キロも走ったら消しゴムのように減っていったのには驚きました。
その点、このこのミシュランは長持ちしました。長野県菅平に行ったり東京を経由しての名古屋までの長旅などの脚としては申し分ない働きをしてくれました。
高速道で100キロ+αでの2時間以上の連続走行でも(気温が30度ぐらいの時)トレッドのゴムが必要以上に柔らかすぎることも無く高速コーナーでもよく踏ん張りその上、丈夫でしたので安心していられました。
というわけで、今回もミシュランにしたのですがでもアナキーより価格の安い「シラック」を選んでみました。何より価格が安いということがまず第一。ダンロップやブリジストンのものより安かったのです。
タイヤのサイズは純正の指定通りの90/90-21。
このシラックと言うタイヤはメーカーの位置づけは次のようです。
「オン&オフのマルチ派に。舗装路面、ダート路面それぞれのパフォーマンスを高いレベルで確保。特に舗装路面でのグリップ性能とロングライフ性能を追求。」と謳っているように(ミシュランのホームページよりの引用)、ツーリング先で未舗装路に出会った場合でも引き返すことなくその道路を走破して旅を続けられる頼もしいタイヤなのです。
さて、今回タイヤ交換には次の工具類を使用しました。


左側の画像のものがフロントを持ち上げるための専用スタンドです。三又の下部の穴に差込みテコの原理で前輪を浮かせます。右側の画像のものはタイヤの空気注入口に挿入されている「ムシ」を外すための「ムシ廻し」です。
その他にはここには写ってはいませんがタイヤレバーとナットを緩めるのに使ったレンチなどです。
まずは前輪を浮かせるためにフロント部を専用スタンドを用い持ち上げます。
 持ち上がった状態です。
持ち上がった状態です。
次にフロント周りの部品を外していきます。


デイスクローターの保護カバーとブレーキキャリパーを外してるところです。
それらが外れたならいよいよ前輪の取り外しです。
フロントアクスルナットの割りピンをプライヤーなどで引き抜きます。

次にフロントアクスルシャフトの22mmのナットを緩めるわけですが硬く締まっていてなかなか緩んでくれません。
レンチの柄にパイプを差込んで柄を長くすることで少ない力で緩めることが出来ました。
次にアクスルシャフトを引き抜きます。アクスルシャフトのナット側からシャフトより細い棒やパイプを使いハンマーでコツコツと叩いてやりますと次の画像のようにシャフトが出てきます。このとき潤滑スプレーなどを吹きつけシャフトを手で回しながら引っ張るとシャフトが出やすいです。
その後、取り外した前輪を床に置き、いよいよタイヤの脱着に取り掛かリます。
そのとき床にはゴム板や厚手のシートなどを敷きホイールの側面やデイスクローターを傷つけないようにしなければなりません。
タイヤの取り外しのまず最初の工程はエアーバルブよりムシを取り外しチューブ内の全部の空気を排出させます。次はビード落としです。これは足でタイヤ側面を踏んづけただけであっけなくビードが落ちました。

ここまでは余裕です。カメラ片手に鼻歌交じりで作業が出来ました。
次の工程はホイールからのタイヤの取り外しです。これは鼻歌交じりというわけにはいきませんでした。
3本のタイヤレバーと両手両足を使っての悪戦苦闘でしたので写真を撮る余裕などはありませんでした。
このようにして取り外したのが次の画像です。

次の段階は新しいタイヤの組付けです。が例によって3本のタイヤレバーと両手両足を使いましたのでこれまた作業途中の写真は撮れませんでした。
何とかしたくみ上げた前輪をバイクに装着した画像が次のものです。
以前のタイヤより溝が細かいのが特徴です。溝の幅もいくらか狭いようです。シッラクはアナキー2より「オフ寄り」な設計なのでしょうか。
その後の新タイヤでの試走とそれにまつわる後日談はまた日を改めまして、ということにして本日はおしまい。
 にほんブログ村
にほんブログ村
今までのタイヤは前後ともミシュランのアナキー2というもの。大型のオフロードツアラーに使われることの多いタイヤです。購入価格ははっきりと覚えてはいませんがチト高かったように思います。
この「アナキー2」は後輪はラジアルですが前輪はラジアルではありません。その為かは知りませんが前輪の方が早く減ってしまっていました(乗り方にもよるんでしょうが)。ですがオフ車用のタイヤとしては長持ちのする方でした。
以前に250CCのオフ車にダンロップのD604という銘柄のタイヤを履かせたことがありましたが約6000キロで寿命に達してしまいました。高速道を1000キロも走ったら消しゴムのように減っていったのには驚きました。
その点、このこのミシュランは長持ちしました。長野県菅平に行ったり東京を経由しての名古屋までの長旅などの脚としては申し分ない働きをしてくれました。
高速道で100キロ+αでの2時間以上の連続走行でも(気温が30度ぐらいの時)トレッドのゴムが必要以上に柔らかすぎることも無く高速コーナーでもよく踏ん張りその上、丈夫でしたので安心していられました。
というわけで、今回もミシュランにしたのですがでもアナキーより価格の安い「シラック」を選んでみました。何より価格が安いということがまず第一。ダンロップやブリジストンのものより安かったのです。
タイヤのサイズは純正の指定通りの90/90-21。
このシラックと言うタイヤはメーカーの位置づけは次のようです。
「オン&オフのマルチ派に。舗装路面、ダート路面それぞれのパフォーマンスを高いレベルで確保。特に舗装路面でのグリップ性能とロングライフ性能を追求。」と謳っているように(ミシュランのホームページよりの引用)、ツーリング先で未舗装路に出会った場合でも引き返すことなくその道路を走破して旅を続けられる頼もしいタイヤなのです。
さて、今回タイヤ交換には次の工具類を使用しました。


左側の画像のものがフロントを持ち上げるための専用スタンドです。三又の下部の穴に差込みテコの原理で前輪を浮かせます。右側の画像のものはタイヤの空気注入口に挿入されている「ムシ」を外すための「ムシ廻し」です。
その他にはここには写ってはいませんがタイヤレバーとナットを緩めるのに使ったレンチなどです。
まずは前輪を浮かせるためにフロント部を専用スタンドを用い持ち上げます。
 持ち上がった状態です。
持ち上がった状態です。次にフロント周りの部品を外していきます。


デイスクローターの保護カバーとブレーキキャリパーを外してるところです。
それらが外れたならいよいよ前輪の取り外しです。
フロントアクスルナットの割りピンをプライヤーなどで引き抜きます。

次にフロントアクスルシャフトの22mmのナットを緩めるわけですが硬く締まっていてなかなか緩んでくれません。
レンチの柄にパイプを差込んで柄を長くすることで少ない力で緩めることが出来ました。
次にアクスルシャフトを引き抜きます。アクスルシャフトのナット側からシャフトより細い棒やパイプを使いハンマーでコツコツと叩いてやりますと次の画像のようにシャフトが出てきます。このとき潤滑スプレーなどを吹きつけシャフトを手で回しながら引っ張るとシャフトが出やすいです。
その後、取り外した前輪を床に置き、いよいよタイヤの脱着に取り掛かリます。
そのとき床にはゴム板や厚手のシートなどを敷きホイールの側面やデイスクローターを傷つけないようにしなければなりません。
タイヤの取り外しのまず最初の工程はエアーバルブよりムシを取り外しチューブ内の全部の空気を排出させます。次はビード落としです。これは足でタイヤ側面を踏んづけただけであっけなくビードが落ちました。

ここまでは余裕です。カメラ片手に鼻歌交じりで作業が出来ました。
次の工程はホイールからのタイヤの取り外しです。これは鼻歌交じりというわけにはいきませんでした。
3本のタイヤレバーと両手両足を使っての悪戦苦闘でしたので写真を撮る余裕などはありませんでした。
このようにして取り外したのが次の画像です。

次の段階は新しいタイヤの組付けです。が例によって3本のタイヤレバーと両手両足を使いましたのでこれまた作業途中の写真は撮れませんでした。
何とかしたくみ上げた前輪をバイクに装着した画像が次のものです。

以前のタイヤより溝が細かいのが特徴です。溝の幅もいくらか狭いようです。シッラクはアナキー2より「オフ寄り」な設計なのでしょうか。
その後の新タイヤでの試走とそれにまつわる後日談はまた日を改めまして、ということにして本日はおしまい。














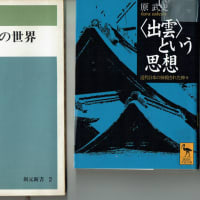






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます