
タイヤ交換の記事の後編です。前回の前編には実は後日談がありまして、今回はそのお話です。
いや、正確には記事の投稿日が同じ日なので後日談ではなく「当日談」なのですが、とにかくえらいミスをしでかす処だったというお話です。
昨日の日曜日にタイヤ交換が終わったばかりのバイクで秋田市より100キロほどの距離にある鳥海山まで出掛けてきました。市内を抜け郊外を走行中のことです。時速が60キロを越えたあたりから前輪の部分より今までと違った振動がハンドルを伝わって感じられました。
走行中のフロントフォークの下部にに目をやると、細かく上下動をしているように見えるのです。タイヤが新しいせいでタイヤバランスが良く取れてないのかとも思いながら、無料の高速道(正確には高規格自動車専用道というらしい。)に入り80キロ以上のスピードで走行すると振動も消えるのでそのまま走行を続けました。高速道を仁賀保で降りてからの一般道や鳥海山の山岳路を走行した時には、先ほどの振動の違和感は感じられませんでした。100キロほども走ったので新しいタイヤもなじんできたのだろうと勝手に思い込み帰路につきました。
秋田市内に戻ると60キロ以内の速度でやはり前輪からの振動が発生しているようなのです。
家に着きフロントタイヤを良く点検してみると、重要な不具合を発見しました。
なんと、タイヤリムにビードの嵌り具合が不適切な箇所があったのです。タイヤを組み上げる時の作業のミスです。
タイヤリムにタイヤのビードが完全にはまってない状態で200キロ以上を走ってきたことになります。
タイヤは正確にリムに組みつけられて初めて真円になりますが、リムにちゃんと組まれていない状態では真円ではなく卵型の形状になってしまいます。
実はバイクのタイヤが真円で無い状態で走行を続けていたことに青くなりました。次の画像をご覧ください。

タイヤリムの外周にタイヤがちゃんと装着されているのかを示す円周上のラインを見ることが出来ると思いますが、そのラインが途中からリムの中に入り込み見えなくなっているではありませんか。
たとえその数値がほんの数ミリであってもタイヤ外周のラインはあくまでもリムの外周と平行になっていなければタイヤの真円度が取れていないことになります。
今まで何本ものバイクタイヤを自分で組みつけてきましたが、こんなことは初めてです。
今までダンロップやブリジストンのタイヤではこんなことはありませんでした。
組み付け作業時にも「随分このタイヤは硬いタイヤだ」とは思っていましたが、それはタイヤが新しいせいとか、しばらくタイヤ交換もやってないので腕も落ちたかななどと思ったりしましたが、実はそうではなくミシュランはすごく剛性の高いすなわち側面とビード部の延びの少ない硬いタイヤだったのでした。
それゆえ、手持ちの軽便空気入れではビード上げに必要な充分な空気圧をあげれなかったわけでした。
タイヤのリムとビードとの摩擦を軽減する「ビードワックス」を用意して本日午後よりエアー入れの再挑戦を行いました。
 ビードワックスです。
ビードワックスです。
今度は充分な高圧エアーを使える知り合いの金属加工屋にタイヤを持ち込み作業をしました。
まず始めはエアーバルブにムシを装着しないで一気に高圧の空気を入れる方式でやってみました。4キロほどの空気圧を一気に入れると見事にビードは広がり(ビード上げと言う)リムに密着させることが出来ました。
ですが、ムシをエアーバルブにつけるためにエアーの接続を外しムシを取り付けた状態で再度空気を入れるとやはりビードはあがりません。
こんなことを3回ほど繰り返し、思い切って充填する空気の圧を高くしてやってみると、見事ビードも上がりました。今度は成功です。
やっと空気入れ作業の完成です。しばらく高い空気圧のままにしておいてビードをリムになじませて、走るときに空気圧を調整することにして、そのままの状態でバイクにホイルを組み付けてタイヤ交換の終わりとします。
ホイルの組み付け時についでにスピードメータギアにグリスを充填しました。

ここの箇所は雨の中の走行や洗車などで中に水が入りやすい箇所です。ギアに水が入り込むとグリスが乳化して歯車の磨耗を早めますので。
最後に、装着したシラックのアップ写真をご覧になっていただきたい。

新品のタイヤには必ず「ヒゲ」と呼ばれる、製造時に出来るゴムの細い毛らしきものがあります。
この「ヒゲ」がミシュランのタイヤにはかなり多いように思いました。ダンロップやブリジストンのタイヤにはひげはありますがこんなには多くはありません。こんなところにもミシュランタイヤには製造時のノウハウがあるのでしょうか。
二回にわたりタイヤ交換の悪戦苦闘ぶりを見ていただき有難うございました。この記事をお読みになり自分でバイクタイヤの交換にチャレンジしようとお考えの方に少しだけでも参考になれば幸いです。
 にほんブログ村
にほんブログ村
いや、正確には記事の投稿日が同じ日なので後日談ではなく「当日談」なのですが、とにかくえらいミスをしでかす処だったというお話です。
昨日の日曜日にタイヤ交換が終わったばかりのバイクで秋田市より100キロほどの距離にある鳥海山まで出掛けてきました。市内を抜け郊外を走行中のことです。時速が60キロを越えたあたりから前輪の部分より今までと違った振動がハンドルを伝わって感じられました。
走行中のフロントフォークの下部にに目をやると、細かく上下動をしているように見えるのです。タイヤが新しいせいでタイヤバランスが良く取れてないのかとも思いながら、無料の高速道(正確には高規格自動車専用道というらしい。)に入り80キロ以上のスピードで走行すると振動も消えるのでそのまま走行を続けました。高速道を仁賀保で降りてからの一般道や鳥海山の山岳路を走行した時には、先ほどの振動の違和感は感じられませんでした。100キロほども走ったので新しいタイヤもなじんできたのだろうと勝手に思い込み帰路につきました。
秋田市内に戻ると60キロ以内の速度でやはり前輪からの振動が発生しているようなのです。
家に着きフロントタイヤを良く点検してみると、重要な不具合を発見しました。
なんと、タイヤリムにビードの嵌り具合が不適切な箇所があったのです。タイヤを組み上げる時の作業のミスです。
タイヤリムにタイヤのビードが完全にはまってない状態で200キロ以上を走ってきたことになります。
タイヤは正確にリムに組みつけられて初めて真円になりますが、リムにちゃんと組まれていない状態では真円ではなく卵型の形状になってしまいます。
実はバイクのタイヤが真円で無い状態で走行を続けていたことに青くなりました。次の画像をご覧ください。

タイヤリムの外周にタイヤがちゃんと装着されているのかを示す円周上のラインを見ることが出来ると思いますが、そのラインが途中からリムの中に入り込み見えなくなっているではありませんか。
たとえその数値がほんの数ミリであってもタイヤ外周のラインはあくまでもリムの外周と平行になっていなければタイヤの真円度が取れていないことになります。
今まで何本ものバイクタイヤを自分で組みつけてきましたが、こんなことは初めてです。
今までダンロップやブリジストンのタイヤではこんなことはありませんでした。
組み付け作業時にも「随分このタイヤは硬いタイヤだ」とは思っていましたが、それはタイヤが新しいせいとか、しばらくタイヤ交換もやってないので腕も落ちたかななどと思ったりしましたが、実はそうではなくミシュランはすごく剛性の高いすなわち側面とビード部の延びの少ない硬いタイヤだったのでした。
それゆえ、手持ちの軽便空気入れではビード上げに必要な充分な空気圧をあげれなかったわけでした。
タイヤのリムとビードとの摩擦を軽減する「ビードワックス」を用意して本日午後よりエアー入れの再挑戦を行いました。
 ビードワックスです。
ビードワックスです。今度は充分な高圧エアーを使える知り合いの金属加工屋にタイヤを持ち込み作業をしました。
まず始めはエアーバルブにムシを装着しないで一気に高圧の空気を入れる方式でやってみました。4キロほどの空気圧を一気に入れると見事にビードは広がり(ビード上げと言う)リムに密着させることが出来ました。
ですが、ムシをエアーバルブにつけるためにエアーの接続を外しムシを取り付けた状態で再度空気を入れるとやはりビードはあがりません。
こんなことを3回ほど繰り返し、思い切って充填する空気の圧を高くしてやってみると、見事ビードも上がりました。今度は成功です。
やっと空気入れ作業の完成です。しばらく高い空気圧のままにしておいてビードをリムになじませて、走るときに空気圧を調整することにして、そのままの状態でバイクにホイルを組み付けてタイヤ交換の終わりとします。
ホイルの組み付け時についでにスピードメータギアにグリスを充填しました。

ここの箇所は雨の中の走行や洗車などで中に水が入りやすい箇所です。ギアに水が入り込むとグリスが乳化して歯車の磨耗を早めますので。
最後に、装着したシラックのアップ写真をご覧になっていただきたい。

新品のタイヤには必ず「ヒゲ」と呼ばれる、製造時に出来るゴムの細い毛らしきものがあります。
この「ヒゲ」がミシュランのタイヤにはかなり多いように思いました。ダンロップやブリジストンのタイヤにはひげはありますがこんなには多くはありません。こんなところにもミシュランタイヤには製造時のノウハウがあるのでしょうか。
二回にわたりタイヤ交換の悪戦苦闘ぶりを見ていただき有難うございました。この記事をお読みになり自分でバイクタイヤの交換にチャレンジしようとお考えの方に少しだけでも参考になれば幸いです。



















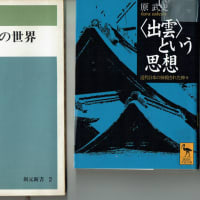









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます