
本日の作業開始前に昨日の不具合の件の報告です。
下記の画像をごらんあれ。

フロントのステップのホルダーのボルトのピッチが合いません。前期型と後期型ではステップホルダーの形状が微妙に違っていました。前期型はフロントのステップとリヤのステップはおのおの単独で装着されていますが、後期型ではリヤのステップもフロントステップと同じホルダーに装着されていました。
後期型のステップホルダーは二人乗車を考慮し強度を上げるためと思われますがボルトのピッチを幅広く取ってありました。
これはこれで、設計上は良い構造だとは思いますが、今現在ステップが装着できなければ車体は完成しません。
前期型のステップを調達することにしました。後期型のリヤフレームには後部のステップが単独で付くようにはなっていませんが後部ステップはタンデムをしなければ必要はありませんのであっさりと一人乗車と割り切ります。
さて、本日の作業はエアクリーナーボックスの取り付けからです。ボックスの蓋を開けてみてエアフィルターのスポンジの確認しました。
次の画像を見てください。

スポンジはボロボロの状態です。手で持ち上げただけで崩れ落ちる状態です。まるで、数千年の時を経た包帯で巻かれたミイラが、新鮮な空気に触れたとたんに風化して崩れ落ちるようなものでした。
このスポンジは、後日、対処することにして、次は後部のフェンダーの装着をしました。
こちらはほとんどが樹脂製の部品ということもあって清掃のみできれいになりました。
それを車体に装着したのが下記の画像です。

その後、一度取り外した後輪部の装着です。組み立てにあたって後輪ホイール周りの清掃と点検。
リヤスプロケットの磨耗の状態はと見るともうしばらくは使用可と判断。
再使用することにしました。スプロケットの刃先が尖ってしまうまでには磨耗してないようです。

リヤのフェンダー周りの部品も取り付けできましたので、後輪の取り付けを施工。
取り付け後の画像が表題のものです。
本日は、その後に各電装品もおおむね取り付けが完了してきましたのでもはやケーブルの取り回しの変更は無いだろうとの判断でワイヤーハーネスの固定をインシュロックで行いました。
可動部分に配線が触れないようにとか無理な引き回しが無いようにとか眼に見えない作業でした。
次に続く
 にほんブログ村
にほんブログ村
下記の画像をごらんあれ。

フロントのステップのホルダーのボルトのピッチが合いません。前期型と後期型ではステップホルダーの形状が微妙に違っていました。前期型はフロントのステップとリヤのステップはおのおの単独で装着されていますが、後期型ではリヤのステップもフロントステップと同じホルダーに装着されていました。
後期型のステップホルダーは二人乗車を考慮し強度を上げるためと思われますがボルトのピッチを幅広く取ってありました。
これはこれで、設計上は良い構造だとは思いますが、今現在ステップが装着できなければ車体は完成しません。
前期型のステップを調達することにしました。後期型のリヤフレームには後部のステップが単独で付くようにはなっていませんが後部ステップはタンデムをしなければ必要はありませんのであっさりと一人乗車と割り切ります。
さて、本日の作業はエアクリーナーボックスの取り付けからです。ボックスの蓋を開けてみてエアフィルターのスポンジの確認しました。
次の画像を見てください。

スポンジはボロボロの状態です。手で持ち上げただけで崩れ落ちる状態です。まるで、数千年の時を経た包帯で巻かれたミイラが、新鮮な空気に触れたとたんに風化して崩れ落ちるようなものでした。
このスポンジは、後日、対処することにして、次は後部のフェンダーの装着をしました。
こちらはほとんどが樹脂製の部品ということもあって清掃のみできれいになりました。
それを車体に装着したのが下記の画像です。

その後、一度取り外した後輪部の装着です。組み立てにあたって後輪ホイール周りの清掃と点検。
リヤスプロケットの磨耗の状態はと見るともうしばらくは使用可と判断。
再使用することにしました。スプロケットの刃先が尖ってしまうまでには磨耗してないようです。

リヤのフェンダー周りの部品も取り付けできましたので、後輪の取り付けを施工。
取り付け後の画像が表題のものです。
本日は、その後に各電装品もおおむね取り付けが完了してきましたのでもはやケーブルの取り回しの変更は無いだろうとの判断でワイヤーハーネスの固定をインシュロックで行いました。
可動部分に配線が触れないようにとか無理な引き回しが無いようにとか眼に見えない作業でした。
次に続く














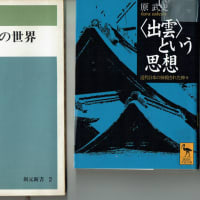






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます