9月の初旬のことです。ZZR250で青森県の海沿いをミニツーリングしてきました。
行先は西津軽の千畳敷です。秋田市からは片道150キロ以上あります。
秋田県の最北に位置する八峰町から北の日本海沿いの国道101号は景色が良くて、適度なコーナーやアップダウンがありその上、交通量の少ないこともあって、バイク乗りにとっては隠れた人気コースです。
秋田県の八峰町の北隣の町は旧岩崎村(現在は深浦町岩崎)にはちょっと変わった岩があります。国道からは直に見ることができませんので気が付かないで通り過ぎてしまいがちです。賽の河原という場所を目指してゆけば数分で森山海岸につきます。

この岩には名前が付けられていました。その名もずばり「象岩」です。象が頭を水面上に出しているかのようです。
ドライブチェーンの交換
さて、本日の話題はこの「象岩」がメインではありません。そのツーリングでバイクを運転中、気が付いたことがあります。
それは走行中の雑音です。一定の速度域でドライブチェーンのジャラジャラ音が耳障りなのです。時速80キロも出せばエンジン音や風切り音の音量が大きくなり気にならなくなりますがいつでも80キロで走るわけにはいきません。集落を通過する時や進行方向の前方に車が連なっているときなど、前車の速度に合わせておとなしく追随して走らなければなりません。そんな時にこのジャラジャラ音が気になりました。
このZZR250を中古で入手した時からわかっていたことですがドライブチェーンが使用限界にきていることは明白です。
ドライブチェーンの価格にはメーカーや種類によってかなりの幅があるようです。
有名メーカーの国産品の高級品は一万円近くもするものもあったりその反面、海外製のメーカー名も記載されていないものなどは2000円以下で買えるものなど様々です。
ドライブチェーンには大きく分けて二つの種類があります。シールチェーンとノンシールチェーンとの二種があります。
シールチェーンはピンとローラーの間にグリスが封入されていてそのグリスが漏れ出すのを防ぐためにゴムのОリングで密閉状態を保つような構造をしています。一方、ノンシールチェーンはそのОリングがありません。グリスも封入されておりません。ピンとローラーの潤滑はオイルを塗付することによって行います。
シールチェーンはグリスが封入してあるのでチェーンの潤滑に手間をかけなくて済みます。チェーンの寿命も長いと言われています。大型車の市販車ではすべてシールチェーンが採用されています。
100馬力を超えるような大排気量、大馬力車のチェーンに掛かる負担はかなりのものです。
もし大馬力車で、ピンとローラーとの潤滑がない状態で数百キロを一気に走ったとしたらピンとローラーの摩耗が進みチェーンの破断を招き事故につながる危険性もあります。シールチェーンはその点メンテナンスに気を使わなくてもよいと言う利点がありますが、一方シールの役目をしているОリングを挟みこんでいることによる摺動抵抗も無視できないものがあります。
これに対してノンシールチェーンはОリングがありませんのでそれによる摩擦抵抗はありません。さらに利点を挙げるならばチェーンの潤滑はピンとローラーとの間に、しみこみやすい柔らかいオイルを使うのが一般的なので、グリス潤滑に比べるとさらに抵抗が少ないと思われます。このような利点がある一方、チェーンへの注油を頻繁に行わなければならないわずらわしさがあります。
チェーンの特性をおさらいしたところで、小生は手間のかかるノンシールチェーンを今回は選択しました。
購入したのは次の物。

サイズは520の110コマのもの。
KMCというのがメーカー名です。聞いたことのないメーカー名ですが自転車用チェーンでは名の通った台湾にある会社だそうです。日本のシマノをはじめ様々な自転車メーカーへOEMで供給しているとのことです。
このメーカーの製品は数年前250CC単気筒車に使ったことがありましたのと、シマノへOEM供給しているくらいだから品質には間違いはないだろうとの判断で選択をした次第です。
それに第一、価格が安い。国内メーカーの同等品の価格の半額程度。アマゾンで送料込みで3000円ですこしお釣りがきました。
ZZR250は純正のスプロケットを使用している場合、チェーンの長さは108コマですので購入したチェーンは2コマ余ります。所定の長さに切断しなければなりません。本来ならばチェーンのピンのカシメ専用のチェーンカットツールというのを使うのだそうですが、そんなものはあいにく持ち合わせておりません。それで、ベビーグラインダーでカシメの頭部を削り、ポンチでピンを叩いて取り外しました。古いチェンを取り外すときにも同じ方法で取り外します。
チェーン交換の小技をひとつ。古いチェーンを取り外すときには完全に引っ張りだしてしまうのではなく、古いチェーンの端部に新しいチェーンの端部をクリップジョイントでジョイントして古いチェーンを引き出しますととエンジン側のスプロケットカバーなどを外すことなく新規のチェーンを前スプロケットに掛けることができます。
その後、付属してきたクリップジョイントで新規のチェーンの端部どうしを繋げれば完成です。
サスペンションオイルの交換
先日の西津軽へのミニツーリングでもう一点気になった点がありました。それはフロント周りの挙動にしっくりこないものがあることでした。道路の継ぎ目や荒れた路面を通過する時にハンドルに伝わってくるフロントフォークの突き上げ感です。
この原因はフロントフォークそのものにありそうです。そこでフォークオイルを交換してみることにしました。
今回その作業のために用意したのは次の物です。

サスペンションオイルG-10、計量に使うメスシリンダー、それにフォークチューブにオイルを入れるのに使うジョウゴです。これには15センチぐらいに切ったホースを付けておきます。
作業の手順は次のようにおこないました。
① センタースタンドを掛けてバイクを直立させます。その後フロントスタンドで前輪を地面から浮かせておきます。これはフロントフォークのスプリングに荷重をかけないためです。フロントスタンドがない時には車体のエンジン下部をパンタグラフジャッキなどで支えて前輪を地面から浮かせるようにしてください。

② フォーク上部のキャプボルトを緩めて取り外します。これにはラチェットハンドルの対辺12.7mmの四角の部分がそのまま入ります。
取り外すときの注意点。フォークスプリングの荷重をかけない状態でも少しのイニシャル荷重がスプリングに掛かっていますのでフォークチューブ上部のキャップボルトが不意に飛び出すのを防ぐた為、手で押さえながら作業してください。

③ フォーク下部にオイルを抜くためのドレンビスがありますので+ドライバーで緩めて取り外すとオイルが出てきます。
初めのうちは勢いよくオイルが真横に飛び出しますので、下に置いたバケツなどにうまく受けるために段ボールの切れはしなどを使ってオイルの勢いをバケツに導いてやるとい良いかと思います。

オイルには粘度があり、抜けきるにはしばらく時間がかかります。滴となってからもしばらくはそのままにしておきましょう。
排出されたオイルの色は黒に近い灰色といったところです。オイルの中には細かい金属の粉が混じっているように見えます。おそらくフォーク内部のブッシュ類などの摩耗も進行しているのでしょうね。排出されたオイルの量を測ってみました。右側フォークからは315CCが、左側フォークからは360CCほどがでてきました。左右の量にかなりの開きがあるのが不思議なところですね。左右のフォークにはオイルにじみや漏れの痕跡は見当たらなかったのでこんなにも左右でのオイル量に差があるのはなぜなのか気になります。
前回注入時に左右の量を測り間違えたのでしょうか。
新旧のオイルの色はつぎの画像。

④ オイルの排出が終わりましたらドレンビスを元通りに締めて新しいオイルを入れてやります。
メーカーのメンテナンスデーターによるとオイルの粘度は10番でその容量は350CCとなっていますのでそれに従い350CC+αの量を計量して容器に入れておきます。その後ジョウゴを使ってフォークのインナーチューブの上部よりゆっくり注入します。ちなみに新品オイルの色は次の通り。

⑤ フォークのトップキャップを元通りに締めこめば作業は完成となります。
ドライブチェーンとサスペンションオイルの交換後の変化を次に述べます。
チェーンの交換後はジャラジャラ音はなくなりました。それと同時に燃費の向上が見られたのが大きな変化です。数値的にはそれまでの最高の燃費が25キロぐらいだったのが、先日の100キロほどの走行では27キロに届こうという数値を記録しました。走り方にもよりますので一概には言えませんがチェーン交換の効果は燃費向上に寄与しているようです。
サスペンションオイルの交換後の大きな変化はフロントフォークの動きにしなやかさを実感できました。
以前あった継ぎ目を通過した時のゴツゴツとした動きがなくなり、スムーズな動きになりました。
ドライブチェーンとサスペンションオイルの交換を紹介したわけですが、古いバイクでメンテナンスを長く行っていない車体では実感できる効果がありました。ぜひお試しあれ。
 にほんブログ村
にほんブログ村
行先は西津軽の千畳敷です。秋田市からは片道150キロ以上あります。
秋田県の最北に位置する八峰町から北の日本海沿いの国道101号は景色が良くて、適度なコーナーやアップダウンがありその上、交通量の少ないこともあって、バイク乗りにとっては隠れた人気コースです。
秋田県の八峰町の北隣の町は旧岩崎村(現在は深浦町岩崎)にはちょっと変わった岩があります。国道からは直に見ることができませんので気が付かないで通り過ぎてしまいがちです。賽の河原という場所を目指してゆけば数分で森山海岸につきます。

この岩には名前が付けられていました。その名もずばり「象岩」です。象が頭を水面上に出しているかのようです。
ドライブチェーンの交換
さて、本日の話題はこの「象岩」がメインではありません。そのツーリングでバイクを運転中、気が付いたことがあります。
それは走行中の雑音です。一定の速度域でドライブチェーンのジャラジャラ音が耳障りなのです。時速80キロも出せばエンジン音や風切り音の音量が大きくなり気にならなくなりますがいつでも80キロで走るわけにはいきません。集落を通過する時や進行方向の前方に車が連なっているときなど、前車の速度に合わせておとなしく追随して走らなければなりません。そんな時にこのジャラジャラ音が気になりました。
このZZR250を中古で入手した時からわかっていたことですがドライブチェーンが使用限界にきていることは明白です。
ドライブチェーンの価格にはメーカーや種類によってかなりの幅があるようです。
有名メーカーの国産品の高級品は一万円近くもするものもあったりその反面、海外製のメーカー名も記載されていないものなどは2000円以下で買えるものなど様々です。
ドライブチェーンには大きく分けて二つの種類があります。シールチェーンとノンシールチェーンとの二種があります。
シールチェーンはピンとローラーの間にグリスが封入されていてそのグリスが漏れ出すのを防ぐためにゴムのОリングで密閉状態を保つような構造をしています。一方、ノンシールチェーンはそのОリングがありません。グリスも封入されておりません。ピンとローラーの潤滑はオイルを塗付することによって行います。
シールチェーンはグリスが封入してあるのでチェーンの潤滑に手間をかけなくて済みます。チェーンの寿命も長いと言われています。大型車の市販車ではすべてシールチェーンが採用されています。
100馬力を超えるような大排気量、大馬力車のチェーンに掛かる負担はかなりのものです。
もし大馬力車で、ピンとローラーとの潤滑がない状態で数百キロを一気に走ったとしたらピンとローラーの摩耗が進みチェーンの破断を招き事故につながる危険性もあります。シールチェーンはその点メンテナンスに気を使わなくてもよいと言う利点がありますが、一方シールの役目をしているОリングを挟みこんでいることによる摺動抵抗も無視できないものがあります。
これに対してノンシールチェーンはОリングがありませんのでそれによる摩擦抵抗はありません。さらに利点を挙げるならばチェーンの潤滑はピンとローラーとの間に、しみこみやすい柔らかいオイルを使うのが一般的なので、グリス潤滑に比べるとさらに抵抗が少ないと思われます。このような利点がある一方、チェーンへの注油を頻繁に行わなければならないわずらわしさがあります。
チェーンの特性をおさらいしたところで、小生は手間のかかるノンシールチェーンを今回は選択しました。
購入したのは次の物。

サイズは520の110コマのもの。
KMCというのがメーカー名です。聞いたことのないメーカー名ですが自転車用チェーンでは名の通った台湾にある会社だそうです。日本のシマノをはじめ様々な自転車メーカーへOEMで供給しているとのことです。
このメーカーの製品は数年前250CC単気筒車に使ったことがありましたのと、シマノへOEM供給しているくらいだから品質には間違いはないだろうとの判断で選択をした次第です。
それに第一、価格が安い。国内メーカーの同等品の価格の半額程度。アマゾンで送料込みで3000円ですこしお釣りがきました。
ZZR250は純正のスプロケットを使用している場合、チェーンの長さは108コマですので購入したチェーンは2コマ余ります。所定の長さに切断しなければなりません。本来ならばチェーンのピンのカシメ専用のチェーンカットツールというのを使うのだそうですが、そんなものはあいにく持ち合わせておりません。それで、ベビーグラインダーでカシメの頭部を削り、ポンチでピンを叩いて取り外しました。古いチェンを取り外すときにも同じ方法で取り外します。
チェーン交換の小技をひとつ。古いチェーンを取り外すときには完全に引っ張りだしてしまうのではなく、古いチェーンの端部に新しいチェーンの端部をクリップジョイントでジョイントして古いチェーンを引き出しますととエンジン側のスプロケットカバーなどを外すことなく新規のチェーンを前スプロケットに掛けることができます。
その後、付属してきたクリップジョイントで新規のチェーンの端部どうしを繋げれば完成です。
サスペンションオイルの交換
先日の西津軽へのミニツーリングでもう一点気になった点がありました。それはフロント周りの挙動にしっくりこないものがあることでした。道路の継ぎ目や荒れた路面を通過する時にハンドルに伝わってくるフロントフォークの突き上げ感です。
この原因はフロントフォークそのものにありそうです。そこでフォークオイルを交換してみることにしました。
今回その作業のために用意したのは次の物です。

サスペンションオイルG-10、計量に使うメスシリンダー、それにフォークチューブにオイルを入れるのに使うジョウゴです。これには15センチぐらいに切ったホースを付けておきます。
作業の手順は次のようにおこないました。
① センタースタンドを掛けてバイクを直立させます。その後フロントスタンドで前輪を地面から浮かせておきます。これはフロントフォークのスプリングに荷重をかけないためです。フロントスタンドがない時には車体のエンジン下部をパンタグラフジャッキなどで支えて前輪を地面から浮かせるようにしてください。

② フォーク上部のキャプボルトを緩めて取り外します。これにはラチェットハンドルの対辺12.7mmの四角の部分がそのまま入ります。
取り外すときの注意点。フォークスプリングの荷重をかけない状態でも少しのイニシャル荷重がスプリングに掛かっていますのでフォークチューブ上部のキャップボルトが不意に飛び出すのを防ぐた為、手で押さえながら作業してください。

③ フォーク下部にオイルを抜くためのドレンビスがありますので+ドライバーで緩めて取り外すとオイルが出てきます。
初めのうちは勢いよくオイルが真横に飛び出しますので、下に置いたバケツなどにうまく受けるために段ボールの切れはしなどを使ってオイルの勢いをバケツに導いてやるとい良いかと思います。

オイルには粘度があり、抜けきるにはしばらく時間がかかります。滴となってからもしばらくはそのままにしておきましょう。
排出されたオイルの色は黒に近い灰色といったところです。オイルの中には細かい金属の粉が混じっているように見えます。おそらくフォーク内部のブッシュ類などの摩耗も進行しているのでしょうね。排出されたオイルの量を測ってみました。右側フォークからは315CCが、左側フォークからは360CCほどがでてきました。左右の量にかなりの開きがあるのが不思議なところですね。左右のフォークにはオイルにじみや漏れの痕跡は見当たらなかったのでこんなにも左右でのオイル量に差があるのはなぜなのか気になります。
前回注入時に左右の量を測り間違えたのでしょうか。
新旧のオイルの色はつぎの画像。

④ オイルの排出が終わりましたらドレンビスを元通りに締めて新しいオイルを入れてやります。
メーカーのメンテナンスデーターによるとオイルの粘度は10番でその容量は350CCとなっていますのでそれに従い350CC+αの量を計量して容器に入れておきます。その後ジョウゴを使ってフォークのインナーチューブの上部よりゆっくり注入します。ちなみに新品オイルの色は次の通り。

⑤ フォークのトップキャップを元通りに締めこめば作業は完成となります。
ドライブチェーンとサスペンションオイルの交換後の変化を次に述べます。
チェーンの交換後はジャラジャラ音はなくなりました。それと同時に燃費の向上が見られたのが大きな変化です。数値的にはそれまでの最高の燃費が25キロぐらいだったのが、先日の100キロほどの走行では27キロに届こうという数値を記録しました。走り方にもよりますので一概には言えませんがチェーン交換の効果は燃費向上に寄与しているようです。
サスペンションオイルの交換後の大きな変化はフロントフォークの動きにしなやかさを実感できました。
以前あった継ぎ目を通過した時のゴツゴツとした動きがなくなり、スムーズな動きになりました。
ドライブチェーンとサスペンションオイルの交換を紹介したわけですが、古いバイクでメンテナンスを長く行っていない車体では実感できる効果がありました。ぜひお試しあれ。














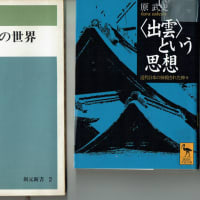






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます