


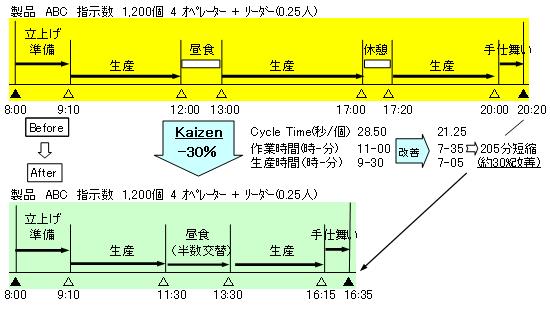


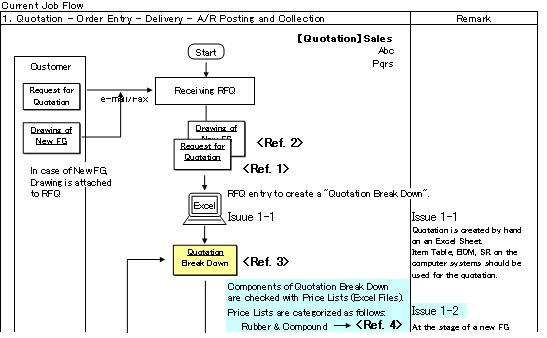
当時、日本の海外進出の目的は途上国の安い人件費だった。他方、アメリカの目的は地球(グローブ)を見渡す経営視界の改善だった。安い人件費を求める日本の製造業と海外拠点の集中管理を目指すアメリカ、両者の目的は本質的に違っていた。しかし、ここでは、世界をカバーするコンピュータシステムと業務管理の観点から両者の比較を試みる。
2000年頃のタイ王国では、約550の日系工場が稼動していた。そこで、日系工場が多いバンコクで、コンサルティングの仕事を見つけた。その目的は、タイに進出した日本の製造業をタイの工場から観察し、そこに日本の製造業の将来像を描く手掛かりを得ようと考えた。
遠い将来、日本の製造業もアメリカ型のグローバルシステムを実現するのだろうか、あるいは、まったく別の日本独特のビジネスモデルを展開するのか、またその時の日本はどのような姿になっているのかと疑問は尽きない。その疑問は、今も続いている。
あの時から今日までの10年間に、繊維、機械、自動車関連の5社の工場に関わった。5社の規模は、従業員200から3,000人程度、日本人社長と数人から十数人の日本人が常駐する工場だった。工場のコンサルタントとして働くうちに、日本の製造業は「郷に入っては郷に従え」、言い換えれば、柔軟な分散型の工場管理だと分かった。アメリカの強力な本社集中管理とは対象的だった。
工場管理以外でも、英語は世界の標準語、人々が英語を話すのは当り前と考えるアメリカ人、英語を外国語の一つと考える日本人、世界の政治・経済・治安のリーダーはアメリカと考えるアメリカ人、国際政治の檜舞台で英語をしゃべれない自国の政治家に違和感を持たない日本人など、両者の考え方には大きな違いがある。
アメリカの10年間で2社、タイの10年間で5社という限られた見識で判断すると、両者には次のような違いがある。
1.使用言語
1)アメリカの集中管理
標準語=英語
ローカル言語(現地語)=日本、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、オランダ語など
e-mailの言語=英語
通訳=従業員は英語を理解するので通訳は不要(英語のできない人は採用しない)
2)日本の分散管理
標準語とローカル言語=現状維持、標準語をあえて定義しない。
ただし、5社の内1社は、英語を公用語(標準語ではない)として公式文書や報告書に使用
使用言語=日本では日本語と英語、タイでは日本語、タイ語、英語(会議案内など)
e-mailの言語=使用言語に同じ。必要に応じて日本語/タイ語の翻訳版をオリジナルメールに添付
通訳=タイ工場では、1人から数人の通訳または大学で日本語を専攻したタイ人社員を採用・・・重要な会議ではプロの通訳を利用、しかし、技術系/IT系/専門語を正確に通訳できないこともある。
2.業務システム
アメリカの場合は、世界の業務を統合システムで管理しているので問題はない。ここでは、説明を省く。
日本企業の場合は、国ごとに業務を管理する。このため国が異なると同じ企業グループでも互いにいろいろな問題が発生する。極端な例では、一つの製品コードが国によって異なるケースもあった。
1)コンピュータシステム
日本は日本、タイ工場はタイでそれぞれが独自にシステムを調達している。
どこの会社でも、IT部門は日本だけで手一杯、海外まで手が届かないのが実情である。このためバンコクには日系ソフトハウスが多く、日系工場の弱点を補足している。しかし、ローカルのソフトハウスに依存しすぎるとシステムの中身がブラックボックス化するという危険性がでてくる。
ちなみに、筆者が訪問したバンコクのアメリカ系工場では、システムはアメリカ本社で集中管理、タイ工場はシステムを利用するだけだった。これは、世界に共通な基幹業務の信頼性と継続性を確保すると同時に、各国のITコストを削減するためだった。
会計システムは、5社とも日系パッケージソフトを導入、画面は英語/タイ語併用である。
2)業務管理
受注・出荷、在庫、生産、購買、会計の業務は、国の法規と商習慣にもとづいて管理している。違反のペナルティーは大きい。品質管理は例外なく日本人管理職が管轄している。自社に限らず、外注先や原材料の品質管理も重視している。
業務管理については、次回、現状分析と幾つかの結果を支障をきたさない形で紹介する。
1.概要設計
業務システム、たとえば、生産管理システムを開発したいとき、先ずシステムの構想から始める。
1)構想設計
システムの目的、対象、物理的な範囲、構造、開発方法、完成時期を大まかに描く。これは、システムのラフスケッチの段階である。
2)現状分析と要件定義
次に、システム構想を実現するために、業務の現状を分析する。たとえば、工場の現状調査では、管理職からではなく業務担当者からありのままの作業内容を聞取り調査する。
調査の結果を分析して、現状とシステム構想とのギャップを明らかにする。そのギャップを解消して、さらにシステムの目的を達成するためには何が必要かを明確にする。これを要件定義と言う。この要件定義を技術、運用、経済性、3つの観点でシステムの実現性を検証する。
日本の場合、なぜか現状分析が甘く、システム稼動後に「想定外の事故」で重大なトラブルを招くことが多い。
アプリが業務の合理化システムの場合、下(業務担当部門)から上(経営陣)にシステム開発の承認を求める。メリットが開発費より大きいとき、開発は承認される。
戦略システムの場合、開発費の見積りは可能だが、メリットの推定が困難な場合がある。無理にメリットをはじいても机上の空論のケースがある。このような場合はトップダウンの形でシステムを開発する。ただし、日本の大企業では、経営陣のリーダーシップが必要なトップダウンのシステムは極めて稀である。この道40年で、日本で2件だけ経験したが、いずれも成功した。
2.システム開発と導入
システム開発は、主にシステムエンジニア、プログラマー、業務改善担当者(コンサルタント)の仕事になる。
1)基本設計
ハード、コンピュータ技術、プログラミング言語、データベースソフト、通信技術などを具体的に決定、システムの論理構造とデータベースの論理構造を設計する。このとき、再びシステムの技術、運用、経済性を正確にチェックする。
この段階でシステムの出来不出来が決まる。もし問題があれば、躊躇せず振り出しから検討する。躊躇すると運用とコストの両面に禍根を残す。分かっているが、失敗するケースは意外に多い。
2)詳細設計
基本設計(書)にもとづき、プログラムを詳細に設計する。データ入力画面や帳票を詳細に設計する。これらの設計書をプログラム仕様書と言う。
3)プログラム作成
仕様書にもとづいて、プログラムを作成する。この作業を、プログラミングまたはコーディングと言う。この作業は、社外や海外のプログラマーに委託することもできる。1990年代から、在宅フリーのプログラマー(経験のある主婦など)や海外に委託するケースが目立ち始めた。正しい日本語、または正しい英語で仕様書を書かなければプログラマーが誤解する。逆に、曖昧な仕様書はプログラマーに嫌われる。
プログラマーは、自分が作成したプログラムをテストして仕事を完了する。このテストを単体テストと言う。
プログラム作成と平行して、業務の改善と新システムの操作マニュアルを準備する。同時に、新システムに必要なデータを整備する。
業務改善は、たとえば工場の場合は、工程と運用ルールといったハードとソフト両面の改善を意味する。また、これらは自社だけでなく取引先も含む改善である。
最後に、単体テストを終えたシステムの連動させてチェックする。これを連動テストと言う。
4)導入
連動テストを終えて、新システムを実地に導入する。「一斉切替え」「新旧システムの平行切替え」またはこれらの組合せで新システムを導入する。「平行切替え」は、新旧システムを運用するので業務担当者の負担は大きい。
大きなシステムや金銭処理がからむシステムでは、危険な「一斉切換え」を避ける。会計処理がからむ場合、新旧システムの月末と年度末の決算結果を検証するため、数年にわたる移行も珍しくない。何があっても、トラブル回避が最優先事項である。
ユーザー教育とシステムの検証を終えて、新システムへの移行を完了する。
次回は、約1ヶ月後にグローバルシステムの概要とメリットを紹介する。
ここでは、コンピュータシステムの基礎知識を整理する。
コンピュータはハードウェア(略してハード)とソフトウェア(ソフト)でできている。言い換えれば、
コンピュータ=ハード+ソフト
といえる。
上の式で、ハードは、コンピュータそのものである。ノート型パソコンでは、パソコン本体、あるいは液晶画面やキーボード、また、パソコン内部の電子部品がハードである。ハードは手に取ったり、触って認識できる物である。
他方のソフトは、ワープロソフトやインターネットソフト、また液晶画面を制御するプログラムなどである。ソフトは手に取ったり、触って認識できないものである。
次にソフトについて、少し詳しく説明する。
2.ソフトウェア
コンピュータのソフトは、次のようなものに分けることができる。
ソフト=オペレーティングシステム+プログラミング言語+アプリケーションシステム
上の式で、オペレーティングシステムとプログラミング言語を総称して、コンピュータ言語という。量的に見て、プログラミング言語は代表的なコンピュータ言語といえる。アプリケーションシステムは、ワープロや表計算ソフトやゲームである。
1)オペレーティングシステム(OS)
オペレーティングシステムはOSと略称する。OSはコンピュータのハードを制御システムである。大型汎用コンピュータやサーバー(比較的小型の汎用機)やパソコンにもそれぞれのOSがある。Windowsは、マイクロソフト社のパソコン用のOSである。
OSは、プログラミング言語の命令をハードに伝えたり、ハードを制御するソフトである。OSの説明は専門的になるので、ここでは省略するが、詳細はWikipedia(ウイキペディア---フリー百科事典)などを参照されたい。
2)プログラミング言語
プログラミング言語は数式や人間の言語に近い言語で、人間の考えをOSを介してコンピュータに伝えるソフトである。
1958年頃に開発されたプログラミング言語、FORTRANは今日も利用されている。1960年代には、10種類程度だった言語も、今日ではJava(ジャバ)、C言語、C++、Basic(ベーシック)など、200種類以上に増大した。もちろん、プログラミング言語も人間の言語と同様に、ハードの進展と共に世代交代があり、すでに使われなくなった言語や新しい言語に吸収されたものもある。
1980年頃からFORTRANやCOBOLで漢字などの日本語処理が可能になった。1990年代には、国、地域、言語、習慣の違いを反映する世界共通語としてのプログラミング言語の国際規格が充実した。日本の漢字や¥記号などのコード体系の標準化もプログラミング言語の国際規格と同時に進展した。
3)アプリケーションシステム(応用システム/業務システム)
アプリケーションは応用という意味の英語である。アプリケーションシステムは、単にアプリケーションまたは「アプリ」と略称する。
アプリはコンピュータ言語で書かれたソフトで、その種類は数え切れない。表計算ソフト、ワープロソフト、お絵書きソフト、ゲーム、あるいは企業の給与計算、会計処理、販売や生産管理システム、銀行のATMや金融システム、交通機関や電気ガスなどの公共システムなどはアプリである。アプリは、個人使用、企業内使用、企業間や国際的な使用など、その範囲は広い。
特に、給与、会計、販売・生産管理システムなどのアプリを業務システムと呼ぶ。業務システムは、自社で開発するケースが多いが、会計システムなどは、市販ソフトを購入するケースもある。ワープロ、表計算、ゲームなどは市販ソフトを購入するのが一般的である。
3.データ
コンピュータには、ハードとソフトが必要とよく言われる。しかし、ハードとソフトだけでなく、データがあってはじめてコンピュータは役に立つ。
給与システムでは、社員名、社員番号、所属、現在の給与などのデータがあってはじめて給与の計算や振込みができる。また、メールソフトにメールアドレス(データ)や文章(データ)を入力すれば、e-mailを送信できる。
コンピュータの中身で一番大切なものはデータであり、さらに、コンピュータやパソコンに蓄積したデータの機密保護とバックアップも必要になる。
次回は、システムの開発、特にアプリの開発手順と管理を説明する。さらに、アプリの開発手順を踏まえてグローバルシステムの開発に進む。
2.英語
1)大学の英語教育
商船大学は4年半制で船乗りを養成する。船乗りに語学は必須、英文学と英会話はそれぞれ4年間、英会話は試験好きなスイス人の先生だった。気象学の教科書は、なぜか英語だった。
航海士としてほのるる丸(商船)に乗組むと、航海日誌(Logbook)や操船号令は英語だった。
ちなみに、航海日誌は公文書で、国内外の事故などでは重要な証拠物件になる。したがって、航海日誌の訂正や書直しは禁止されている。
船内は英語の世界、食事もナイフとフォークだった。テーブルクロスは純白の厚い木綿地、これには理由がある。食事中に船が揺れ始めると、サロンに待機中のスチュワードはすかさず水差しでテーブルクロスに水を注ぐ。湿った厚手のテーブルクロスの上の食器は滑ることなく、平然と食事ができる。これは大航海時代からの習慣と聞いた。安定性の悪い茶碗やお椀ではこうはいくまい。
大学で耳にした唯一の日本語の専門語、「前進微微速」(ゼンシンビビソク=Dead Slow Ahead)は旧日本海軍の用語である。ただし、これは死語、明治から戦時中も日本の商船の航海日誌は英語だったと思う。
2)アメリカの国語教育(英語)
これは、1960年中ごろの話である。アメリカの大学に入学した外国人は、4年制や大学院生に関わりなく、English for International Student(国際学生への英語)が必須になる。実習では毎回作文のテーマを選び、書きたい内容をコンピュータプログラムのようにフローチャートに展開する。その論理の流れ(フローチャート)に先生の添削を受け、OKならば文章にする。日本の国語では習わなかった句読法(項分け、括弧や;や:などの用法)も詳しく教わった。
文章は、32語(Word)以下の短文、かつ、Straightforward(単刀直入な)文章を書くことを指導された。当然、Ambiguous(両義に取れる)文章も「ダメ」だった。
3)専門科目のTerm Paper
工学部の大学院で学んだが、殆どの専門科目では、Term Paper(20ページ程度の小論文)を学期末に提出しなければならなかった。
小論文の評価は、文章の構造(Mechanics)と内容(Content)を合せて100点、90点以上はA、89-80点はB、79点以下はCになる。
文章の構造では、文法、スペリング、文章の形式とスタイル、各10点で合計40点。たとえば、ある科目でやや大風呂敷を広げた内容の論文、「ネットワークの制御論」を提出した。その論文の文章スタイルの評価は、A little high flown for the purpose, but good. 9点(-1点)(やや飛躍しているが、良かろう)と先生のコメントが返ってきた。
内容の評価は、選択したテーマの妥当性とテーマへの理解度、分析の独創性、完成度と深さに分かれ、合計60点だった。
Term Paperでも、Short SentenceとStraightforwardな作文を頭に叩き込まれた。工学部では、独創的な論理の展開力と文章力の養成に力を入れていた。
4)宿題(Home Work)
科目にもよるが、毎週の宿題と3~5冊の専門書の読書を求められる。
言葉の不自由な日本人は、図書館に入り浸りになる。実際には、英和辞典を引く手間は省き、次々とページを読み進まなければ時間が足りない。どうしても分からない単語は、図書館のあちこちに備えてある英英辞典を後で引く、この方が効率的だった。結果として、英語の意味は分かるが、日本語は分からない単語が増えていった。
この点では、船乗りの専門語も同じだった。英語の航海用語は分かるが、その日本語は知らない。また、実務では日本語を使わないので知る必要もない。
将来、日本ビジネスも同様に、英語のビジネス用語しか知らない若者が増えると思う。その時、日本の横書き文章は、カタカナ英語交じりから英文交じりの横書きになる。
次回のフランス語とスペイン語は「ことば(3)」に続く。
当然、その間にいろいろな言葉に接してきた。今回は、地球の思い出から話題を変えて、今までに出会った外国語に話を進める。
ここでは、母国語の日本語を含めて、英語、フランス語、スペイン語、ラテン語、タイ語および世界共通語(数式、楽譜、コンピュータ言語など)について、その言語との関わりや印象を思いつくままに書き記す。
1.日本語
生れてから70年以上も使っている母国語である。幸い、長年の国語教育のお陰で日本語には不自由は感じない。しかし、日本語の将来について、気掛かりな点があるのでここに書き記す。
1)横書きと縦書き
ビジネス文書は横書き、文学作品やお役所の法令などは縦書き、新聞・雑誌は縦書き・横書き混淆である。世界共通のe-mailには、縦書きはありえない。このような現状のもと、将来の日本語の書式はどの様に進化するのだろうかと気掛かりである。
「枕の草子」や「源氏物語」に見る縦書き毛筆は、世界に誇れる文学作品であると同時に、繊細な芸術品である。縦書きは古くから日本文化の基本的な書式であるが、数式や横文字交じり(カタカナの横文字ではない)の文章では使いづらい。
将来、すべてが横書きになるときは日本人が「日本のこころと精神」を忘れ去るのではないかと気掛かりである。
2)日本人の文章力
国語の専門家ではないので、他人の文章を評価することはしない。しかし、多くの文章に接していると、われわれ日本人が書く文章の傾向が見えてくる。システムの開発チームが作成する仕様書など、さまざまな書類から気掛かりな点を独断と偏見で帰納的に要約すると、次のことが言える。
◇用語の標準化に慣れていない・・・組織的な文章化作業に弱い
◇長文が多い・・・句読法(項分け、括弧、:、;、.など)など、横書きの文法に弱い
◇言語明瞭・意味不明が多い・・・論理構造が曖昧、政治には好都合だがビジネスでは不可
この様な傾向から、頭の中で考えたことを効率よく表現する技術、言い換えれば文章力の強化が必要と考えている。特に、将来は自動翻訳に耐える文章力も必要である。この点で、日本の国語教育と大学教育には、改善すべき点が多い。
日本では終身雇用制が長く、職場には必ず生き字引のような社員がいた。あの時代では、分からないことはベテランに聞けば良い、文章化より「あうんの呼吸」で日常業務が回る時代だった。終身雇用制では、社員の文章力や業務の文書化はあまり重視されなかった。しかし、時代は大きく変わった。
なお、参考だが、30年以上も昔から国連職員の業績評価には、使用言語(国連公用語)での文章力と口頭表現力が含まれていた。当時の日本企業にはこの評価項目はなかった。
次回のテーマ、英語は「ことば(2)」フランス語とスペイン語は「ことば(3)」ラテン語とタイ語は「ことば(4)」世界共通語は「ことば(5)」に続く。














