みんな一度は習ってきた萬葉集。
何首くらいの歌を覚えていらっしゃるでしょうか。
また、ご贔屓の作者はおられましたでしょうか。
ここでは、ごく簡単に「萬葉集」の説明をしましょう。
〈 名前の由来〉
5つの説がありますが「万(よろず)の言の葉を集めた」の意であるとの説が有力です。
〈成り立ち〉
いつ、誰によって編纂されたかという動かぬ証拠はまだありませんが、 大伴家持説が有力となっています。編者は「古事記」「日本書紀」「古歌集」 「柿本朝臣人麿歌集」「笠朝臣金村歌集」「高橋連虫麿歌集」などを参考にして 編纂したのではないかと言われています。
」
〈収録された歌の数〉
全二〇巻
短歌…四一七三首
長歌………二六二首
旋頭歌………六一首
合計……四四九六首
〈収録されている時代〉
仁徳天皇の時代(五世紀前半)~天平宝宇(七五九)までのおよそ四〇〇年間に亘ってます。このうち斉明天皇から淳仁天皇にいたる十一代、約一〇〇年間に作られたものが大部分です。
最古の歌…16代仁徳天皇の皇后、磐姫皇后(いわのひめのおおきさき)
「君が行きけ長くなりぬ山尋ね 迎へか行かむ待ちにか待たむ」
最新の歌…27代淳仁天皇の天平宝字3年正月1日(759年)の大伴家持
「新しき年の始(はじめ)は初春の 今日ふる雪の いや重け吉事」
〈時代の区分と作者たち〉
第一期 成立期<大化飛鳥時代>
舒明元年(629年)から壬申の乱(672年)の44年間。
代表歌人には、天智天皇、天武天皇、持統天皇、額田王など。
第二期 完成期<藤原京時代>
壬申の乱以降(673年)から奈良遷都(710年)の38年間…
代表歌人には、柿本人麿、高市黒人、大伯皇女、石川郎女など。
第三期 展開期<奈良朝前期>
奈良遷都以降(711年)から天平5年(733年)の22年間。
代表歌人には大伴旅人、山上憶良、山部赤人、高橋虫麿など。
第四期 衰退期<奈良朝中期>
天平6年(734年)から天平宝字3年(759年)の25年間。
代表歌人には大伴家持、田辺福麿、狭野弟上娘子、笠女郎など。















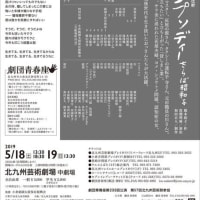
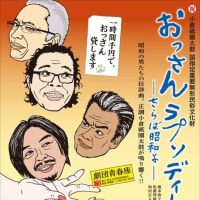
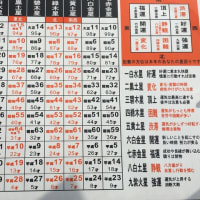









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます