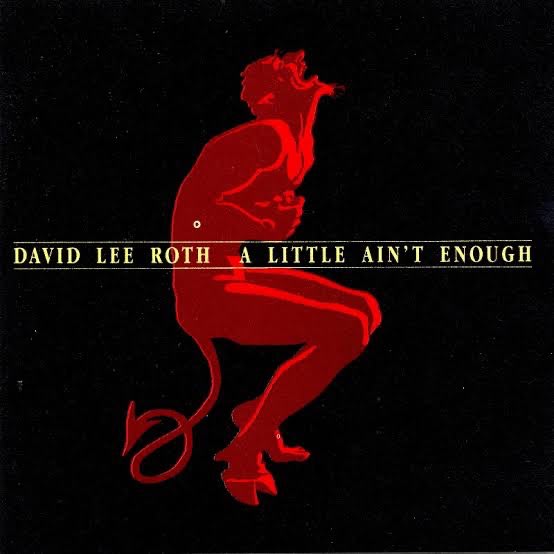2023年2月28日(火)

#468 高中正義「GAPS!」(東芝EMI/Eastworld CT32-5520)
ギタリスト高中正義の16枚目のオリジナル・アルバム。89年リリース。高中自身とエミリオ・エステファン、ジョルジ・カサス、クレイ・オストワルド(いずれもマイアミ・サウンド・マシーン)によるプロデュース。東京、マイアミ録音。
高中については過去にも何枚かで触れてきたので説明不要だろう。日本を代表するトップ・ギタリストのひとりである。
筆者は特別に彼のファンではないが、その卓越した才能、それもギター・テクニックだけでなく、作曲・編曲、プロデュースの才能においても、わが国のトップ・クラス・ミュージシャンであることは間違いないと思っている。
「The Party’s Just Begun」はアップ・テンポのダンサブルなナンバー。作曲はウィル・ペレス=フェリア、ビル・ダンカン。アレンジはダンカン、カサス、オストワルド。
つまり、本盤での約半分、マイアミ録音のパートでは、ダンス・ミュージックのトップ・グループ、マイアミ・サウンド・マシーン(以下MSM)の面々とタッグを組んでいるのだ。
サウンドのノリの良さはさすが、必殺ヒット請負人MSMの仕事であるな。
「Tell It Like It Is」はバラード・ナンバー。バックグラウンド・ボーカルとしてクレジットされているが、実質的にリード・ボーカルをとっているのは、後年グラミー賞も獲得することになる実力派シンガー、ジョン・セカダ。MSMの一員として、作詞・作曲も彼が関わっている。
少し高めで繊細なセカダの歌声に、おなじみの高中のオーバードライブ・ギターが絡むと、実にいいムードになる。
「Out Of Touch」からの4曲は、東京での録音で高中自身の作曲・アレンジだ。ギターだけでなく、共同作業ではあるがシンセサイザー&ドラムスのプログラミングも高中が手がけている。
その「Out Of Touch」はラテン・フュージョンっぽさとダンス・ナンバーっぽさが程よくブレンドされた曲調で、ギターも泣きまくる一曲。女性外人シンガーふたりのコーラスに、80年代の「シティ・ポップ」を感じるね。
「Messa Boogie」はギター・アンプの名前と、めっさ(めちゃくちゃ)+音楽スタイルのブギを引っ掛けた洒落をタイトルにもつナンバー。シャッフルのリズムが心地よい。
高中がそれまで演奏して来た、さまざまなスタイルのギターを、手を変え品を変えして聴かせてくれる。ギターをたしなむ人なら、絶対楽しめるはず。個人的には一番気に入っている。
「Colada」は賑やかなダンス・ナンバー。ディスコ・ビートに乗って、ひたすら陽気なソロを繰り広げる高中。気分はアゲアゲであります。
「Give It Up」は、MSMの連中をバック・コーラスに従えたロック色の強いアップ・テンポのナンバー。ラテン・ロック風のスクウィーズ・ギターがフィーチャーされ、高中節を堪能出来る。
「City Is A Jungle」は再び、MSMとのコラボによるナンバー。ノエル・ウィリアムズの作詞・作曲。
MSMのプロデュースだと、どうしても高中のギターは前面に出てきにくい。主役というよりは、他のパートと似たような扱いになりがちで、よくてソロ・パートを優先して振ってもらえる程度だ。「とにかく高中のギターが聴きたいんじゃあああぁぁぁ!!」というコアなファンには物足りないかもね。
「Say Scratch」は高中作曲・アレンジのナンバー。スティーヴン・アージーのラップをフィーチャーしたファンク・サウンドが全面的に展開される。ギターはリズム楽器扱いという感じで、ソロは期待しない方がいい一曲。
「So Exited」は三たびMSMとのコラボ。セカダのボーカルをフィーチャーしたワイルドなダンス・ナンバー。ランディ・バーロウのアレンジ。
後半、堰を切ったように高中のギターが暴れまくるが、おおむねボーカルがメインの作りだ。
「Suite “Keys”」は高中作曲・アレンジ。これがなかなかいい曲だ。かつてのリゾート・サウンドを再現するかのような、オーソドックスなエイト・ビートのバラード。
メロディアスなフレーズを重ねて次第に盛り上がっていくさまが、なんともいえずいいんだよな。こういう曲を今後もキボン。
ラストの「City Is A Jungle(Extended Club Mix)」はCDのボーナス・トラック。ジョン・ハーグによる同曲のリミックス・バージョンだ。
全編を通して、ドラムスはすべてプログラミングによるもので、これが好みの分かれるところだろうな。
個人的には、若干表現に揺れ、ブレがあっても生ドラムスの方が味があって好きなのだが、サウンドの統一感の方を優先すると、こちらを選ぶのだろう。
MSMとコラボすることにより、ギター・インスト一辺倒でなく、サウンドにもバラエティを持たせ、適宜ボーカルも配した内容で、リスナーを飽きさせない。なかなかうまい構成だと思う。
ソツなくまとめられていて、安心して聴ける一枚。名盤とかマスターピースとかそういう評価はおそらくされないだろうが、常に一定以上のクオリティをキープしてリスナーに提供する高中は、やっぱりプロ中のプロだ。
要するに、音の選び方に試行錯誤とか、迷いがないのだな。
まぁ、人はこれを「才能」と呼ぶのでありましょう。凡人の筆者には一生かかっても到達できない境地であります。
最近の高中正義はアルバム制作を10年以上お休みしている。どちらかといえばDVD制作に力を入れているが、それよりはやはり新しいアルバムを聴きたいものだ。
熱烈ファンとは言えない筆者でさえ、そう思っているんだから、ファンならなおのことだろう。
ぜひ、今年3月に70歳になる記念に、新作をリリースしていただきたい、高中殿。
<独断評価>★★★☆
ギタリスト高中正義の16枚目のオリジナル・アルバム。89年リリース。高中自身とエミリオ・エステファン、ジョルジ・カサス、クレイ・オストワルド(いずれもマイアミ・サウンド・マシーン)によるプロデュース。東京、マイアミ録音。
高中については過去にも何枚かで触れてきたので説明不要だろう。日本を代表するトップ・ギタリストのひとりである。
筆者は特別に彼のファンではないが、その卓越した才能、それもギター・テクニックだけでなく、作曲・編曲、プロデュースの才能においても、わが国のトップ・クラス・ミュージシャンであることは間違いないと思っている。
「The Party’s Just Begun」はアップ・テンポのダンサブルなナンバー。作曲はウィル・ペレス=フェリア、ビル・ダンカン。アレンジはダンカン、カサス、オストワルド。
つまり、本盤での約半分、マイアミ録音のパートでは、ダンス・ミュージックのトップ・グループ、マイアミ・サウンド・マシーン(以下MSM)の面々とタッグを組んでいるのだ。
サウンドのノリの良さはさすが、必殺ヒット請負人MSMの仕事であるな。
「Tell It Like It Is」はバラード・ナンバー。バックグラウンド・ボーカルとしてクレジットされているが、実質的にリード・ボーカルをとっているのは、後年グラミー賞も獲得することになる実力派シンガー、ジョン・セカダ。MSMの一員として、作詞・作曲も彼が関わっている。
少し高めで繊細なセカダの歌声に、おなじみの高中のオーバードライブ・ギターが絡むと、実にいいムードになる。
「Out Of Touch」からの4曲は、東京での録音で高中自身の作曲・アレンジだ。ギターだけでなく、共同作業ではあるがシンセサイザー&ドラムスのプログラミングも高中が手がけている。
その「Out Of Touch」はラテン・フュージョンっぽさとダンス・ナンバーっぽさが程よくブレンドされた曲調で、ギターも泣きまくる一曲。女性外人シンガーふたりのコーラスに、80年代の「シティ・ポップ」を感じるね。
「Messa Boogie」はギター・アンプの名前と、めっさ(めちゃくちゃ)+音楽スタイルのブギを引っ掛けた洒落をタイトルにもつナンバー。シャッフルのリズムが心地よい。
高中がそれまで演奏して来た、さまざまなスタイルのギターを、手を変え品を変えして聴かせてくれる。ギターをたしなむ人なら、絶対楽しめるはず。個人的には一番気に入っている。
「Colada」は賑やかなダンス・ナンバー。ディスコ・ビートに乗って、ひたすら陽気なソロを繰り広げる高中。気分はアゲアゲであります。
「Give It Up」は、MSMの連中をバック・コーラスに従えたロック色の強いアップ・テンポのナンバー。ラテン・ロック風のスクウィーズ・ギターがフィーチャーされ、高中節を堪能出来る。
「City Is A Jungle」は再び、MSMとのコラボによるナンバー。ノエル・ウィリアムズの作詞・作曲。
MSMのプロデュースだと、どうしても高中のギターは前面に出てきにくい。主役というよりは、他のパートと似たような扱いになりがちで、よくてソロ・パートを優先して振ってもらえる程度だ。「とにかく高中のギターが聴きたいんじゃあああぁぁぁ!!」というコアなファンには物足りないかもね。
「Say Scratch」は高中作曲・アレンジのナンバー。スティーヴン・アージーのラップをフィーチャーしたファンク・サウンドが全面的に展開される。ギターはリズム楽器扱いという感じで、ソロは期待しない方がいい一曲。
「So Exited」は三たびMSMとのコラボ。セカダのボーカルをフィーチャーしたワイルドなダンス・ナンバー。ランディ・バーロウのアレンジ。
後半、堰を切ったように高中のギターが暴れまくるが、おおむねボーカルがメインの作りだ。
「Suite “Keys”」は高中作曲・アレンジ。これがなかなかいい曲だ。かつてのリゾート・サウンドを再現するかのような、オーソドックスなエイト・ビートのバラード。
メロディアスなフレーズを重ねて次第に盛り上がっていくさまが、なんともいえずいいんだよな。こういう曲を今後もキボン。
ラストの「City Is A Jungle(Extended Club Mix)」はCDのボーナス・トラック。ジョン・ハーグによる同曲のリミックス・バージョンだ。
全編を通して、ドラムスはすべてプログラミングによるもので、これが好みの分かれるところだろうな。
個人的には、若干表現に揺れ、ブレがあっても生ドラムスの方が味があって好きなのだが、サウンドの統一感の方を優先すると、こちらを選ぶのだろう。
MSMとコラボすることにより、ギター・インスト一辺倒でなく、サウンドにもバラエティを持たせ、適宜ボーカルも配した内容で、リスナーを飽きさせない。なかなかうまい構成だと思う。
ソツなくまとめられていて、安心して聴ける一枚。名盤とかマスターピースとかそういう評価はおそらくされないだろうが、常に一定以上のクオリティをキープしてリスナーに提供する高中は、やっぱりプロ中のプロだ。
要するに、音の選び方に試行錯誤とか、迷いがないのだな。
まぁ、人はこれを「才能」と呼ぶのでありましょう。凡人の筆者には一生かかっても到達できない境地であります。
最近の高中正義はアルバム制作を10年以上お休みしている。どちらかといえばDVD制作に力を入れているが、それよりはやはり新しいアルバムを聴きたいものだ。
熱烈ファンとは言えない筆者でさえ、そう思っているんだから、ファンならなおのことだろう。
ぜひ、今年3月に70歳になる記念に、新作をリリースしていただきたい、高中殿。
<独断評価>★★★☆