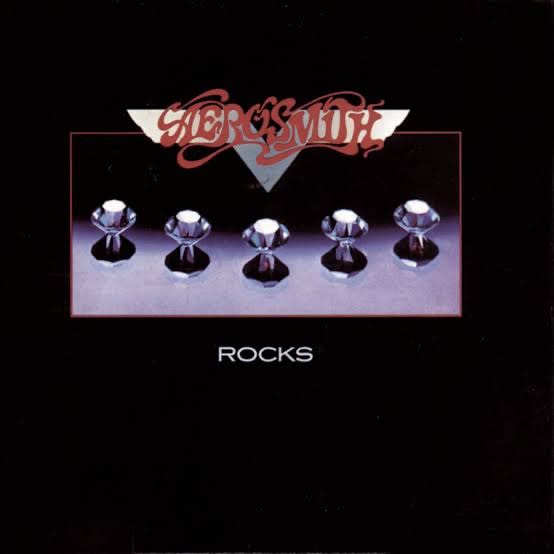2007年3月18日(日)

#351 エリック・クラプトン「UNPLUGGED」(Reprise 9362-45024-2)
エリック・クラプトン、92年のアルバム。ラス・タイトルマンによるプロデュース。
MTVの人気ライブ番組「アンプラグド」より生まれた本盤、日本にもアンプラグド=アコースティックな音楽のブームを起こす牽引役となった一枚である。
まずはEC作、ロハスな雰囲気の瀟酒なインスト・ナンバー「SIGNE」からスタート。
続く「BEFORE YOU ACCUSE ME」は、ご存じボ・ディドリーの代表曲。CCRのカバー以上に、ECはこの曲を世間に知らしめたといえるだろう。
マーティンのアコースティック・ギターから紡ぎ出されるサウンドは、大音量のエレクトリック・サウンドに慣れ切ったリスナーには、とても新鮮に感じられたはず。
三曲目の「HEY HEY」は、ビッグ・ビル・ブルーンジーの作品。もうひとりのギタリスト、アンディ・フェアウェザーとの息の合ったギター・アンサンブルが、格好よろし。
お次はある意味「アンプラグド」の企画に参加する切っ掛けともなったといえる、当時最新のヒット曲「TEARS IN HEAVEN」。私生活での悲劇を昇華させ、超スタンダードなバラードにまで高めた一曲。
変に感情過多にならず、さらりと悲しみを歌うECに、「漢」を感じファンになったひとも多かろう。
五曲目の「LONELY STRANGER」もEC作。ブルースを隠し味にしたバラード、ゆったりとした雰囲気で淡々と歌うEC。実にいい感じだ。
続く「NOBODY KNOWS YOU WHEN YOU'RE DOWN AND OUT」は名盤「いとしのレイラ」にも収められていたジミー・コックスの作品。アンプラグド化されることで、よりオールド・タイミィでブルーズィな味わいが深まったと思うが、いかがであろうか。
次は、泣く子も黙る、極め付きの名曲「LAYLA」。
激情に溢れたオリジナル・バージョンももちろん最高だが、あえてシャウトせずしみじみと歌うアンプラグド・バージョンにも、大人の音楽の魅力を感じる。
ドミノス・バージョンは激しい恋の渦中でこそ歌えたものであろうし、その恋が彼方に去ってしまった現在は、それを懐かしさ、そしてほろ苦い思いで眺望するバージョンもまたあり、ということですな。
「RUNNING ON FAITH」はジェリー・リン・ウィリアムスの作品。カントリー・スタイルのバラード。
ブルースとならぶアメリカ人の「こころの歌」といえばカントリー。ECは「どカントリー」みたいなのは余り歌わないほうだけど、やっぱり白人、実はお好きなんでしょうな。曲作りでも、かなりカントリーの影響がうかがえるし。
一転、九曲目は「どブルース」な一曲。ロバート・ジョンスンの「WALKIN' BLUES」なり。
ここでのギター・アレンジは、ジョンスン本人のバージョンにかなり忠実だ。深いリスペクトの表れといえよう。
「ALBERTA」は、レッドベリーでおなじみのトラディショナル。会場内の雰囲気もなごやかになる一曲。これぞアメリカン・ミュージック!だね。
チャック・リーヴェルのピアノが、なんともいいムードである。
「SAN FRANCISCO BAY BLUES」は戦前から活躍したギタリスト/シンガー、ジェシー・フラーの作品。ECが取り上げたことで、本曲は20世紀を代表するスタンダードとなったといえそう。
「MALTED MILK」は、ふたたびロバート・ジョンスンの作品。スローで物憂い雰囲気が、アンプラグドならではの味わい。
次のECとロバート・クレイの合作「OLD LOVE」は、「LAYLA」というか、元ネタ曲「AS TIME GOES PASSING BY」のフレーズをうまく折り込んだナンバー。ゆったりとしたビートで、熟成した美しいメロディを歌い上げるEC。技術よりもハートで勝負、そんな感じだ。
アンコールとおぼしきラストの曲は、クリームでおなじみのマディ・ウォーターズ・ナンバー、「ROLLIN' & TUMBLIN'」。アップ・テンポでにぎやかに、ステージをしめくくっている。
エレクトリック・ギターにはない、ギター・サウンドの魅力を再発見出来る一枚。
元リトル・フィートのプロデューサーだったラス・タイトルマンによる音作りは、アメリカン・ミュージックのツボを見事にとらえていて、なかなかの仕事。企画ものとはいえ、あなどれません。
過激でシゲキ的な音楽に飽きたときは、こんな一枚がおすすめです。
<独断評価>★★★★