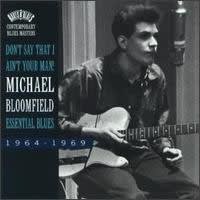2001年6月17日(日)

フリートウッド・マック「ブルース・ジャム・イン・シカゴ VOL.2」(EPIC)
さて、「ブルーズ・ジャム・イン・シカゴ」のVOL.2は、ジェイムズ・レイン、すなわちスパン同様、マディ・ウォーターズのバック・ミュージシャンとして知られるジミー・ロジャーズの「ワールズ・イン・ア・タングル」でミディアム・スローにスタート。
このセッションに登場するシカゴ組ミュージシャンにとっても、またマック組にとっても、弾きなれたおなじみのナンバーなのであろう。
続いて、ダニー・カーワンのオリジナル「トーク・ウィズ・ユー」。高音のリフが印象的な、ミディアム・テンポのナンバーだ。
アップ・テンポで、激しいギター・リフの掛け合いが聴かれる「ライク・イット・ディス・ウェイ」もカーワンの作品。ともになかなかイカしたアレンジのブルースだ。
スロー・ナンバー「サムデイ・スーン・ベイビー」はスパンの曲。ボーカルも彼が担当、これが実に枯れた味わいがある。
セッションの翌年4月、40才の若さで亡くなったのが、実に惜しまれる。
「ハングリー・カントリー・ガール」もスパンのボーカルが聴けるオリジナル。
表芸にしないのがもったいないくらい、素晴らしい歌いぶりだ。もちろん、ピアノ・ソロも音数少なくとも最高にうまい。
エルモア風スライド・ギターで始まる「ブラック・ジャック・ブルース」はテナーのJ・T・ブラウンのオリジナル。低音のシブ~いのどを彼も聴かせてくれる。
やっぱ、マック組、歌ではちょっとかなわんかな~。
メンフィス・スリムことピーター・チャットマンの名曲「エヴリデイ・アイ・ハヴ・ザ・ブルース」、スペンサーのオリジナル・インスト「ロッキン・ブギー」でも、スペンサーのスライド・ギターとブラウンのサックスがフューチャーされている。実に重厚なカラミだ。
ハニーボーイ・エドワーズのナンバー「マイ・ベイビーズ・ゴーン」も、本人の歌をフューチャーして収録。その、がなるようなボーカル・スタイルに、なんとも貫禄を感じてしまう。ギターはバディ・ガイ。
続く「シュガー・ママ」は、ハウリン・ウルフ、テイストなどカバー・バージョンも多い、サニー・ボーイ・ウィリアムスンの作品。
この曲は、ハードでヘビーなアレンジが実にカッコよい。グリーンの泣きのソロも聴ける。
しかし、なんといっても出色は「ホームワーク」ではないだろうか。オーティス・ラッシュでおなじみの、あの曲である。
グリーンの、ラッシュになりきったボーカルもよし、切れ味鋭いソロもまたよし。
彼の、M・ブルームフィールドにまさるとも劣らぬ、黒人ブルースへの傾倒ぶりがうかがえる一曲。ほんとに「濃い」出来ばえだ。
「ハニー・ボーイ・ブルース」は、ビッグ・ウォルターのソロもまじえた、いかにも即興で作った感じのエドワーズ作のインスト・ナンバー。
残る五曲は、ビッグ・ウォルターを前面にフューチャーした「アイ・ニード・ユア・ラヴ(テイク1)」「ホートンズ・ブギ・ウギ」「ハヴ・ア・グッド・タイム」「ザッツ・ロング」、そして「ロック・ミー・ベイビー」。
4曲はウォルターの作品。最後の一曲は、もち、リル・サン・ジャクスンがオリジナル、B・B・キングでおなじみのナンバー。
いずれも、いかにもジャム・セッション的な、自由でくつろいだ感じの演奏である。他では控え目なスパンのピアノも、「ハヴ・ア・グッド・タイム」「ザッツ・ロング」あたりではノリノリのピアノ・ソロを展開してくれる。これもまた聴きもの。
ウォルターのハープとの掛け合いもあって、これもカッコいい。
「フーチー・クーチー・マン」風アレンジにのせて、ウォルターが艶っぽいボーカルを聴かせてくれる「ロック・ミー・ベイビー」。これも味わい深くて、グッド。
2枚通して聴くと、演奏も歌も、個人的にはVOL.2のほうが出来がいいかな、という気はする。
ともあれ、セッション当初は、両陣営とも、「うまくいくのかいな?」という不安はかなりあったらしいが、それはそこ、根っこは同じブルース愛好者、国や人種、年齢を超えてすぐに融和できたという印象だ。
やっぱり、ブルースは音楽における世界共通語だということの、見事な証しですな。
マックのファンのみならず、ブルースを好きなひとにはぜひチェックしていただきたい2枚であります。
(今年の更新は、これが最後です。お正月の三が日は、更新をお休みさせていただきます。ご了承ください。)