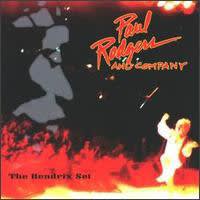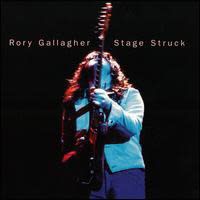2003年1月28日(火)

YAN楽団「横浜の海と空」(YAN-0210)
(1)KODOMOたちへ (2)男のモットー、「もっと!」 (3)すっとボケ (4)貧乏な恋 (5)忘れないで (6)吾輩は営業マンである (7)雨の中へ (8)なんちゃってブルース3 (9)An Injured Bird (10)なすがままで矛盾だらけで (11)どうしようもない (12)なんちゃってブルース(Reprise)
「青春は美しき季節」なんて、どこかの作家か詩人がほざいていたような記憶があるが(歌手かも知れない)、現実には、絵に描いたように美しい青春、ロマンティックな青春なんてのは、そうあるもんじゃない。
若者の日常では、仕事も恋愛も、醜悪なこと、イヤ~なこと、理不尽なことがテンコ盛りだったりする。
ここに登場するのは、「前途洋々」どころか、前途はただただ多難な、不況下のヤング・サラリーマン。
会社には安サラリーでこきつかわれ、ノルマ、ノルマで追いまくられる毎日。
ただ先に入社したというだけで偉そうにしている、無教養でエロオヤジな上司に、「業績が伸びないのはおまえのせいだ」などと怒鳴られ、リストラの恐怖におびえつつサービス残業にいそしむ、いとあはれなり。
仕事が終わったら終わったで、付き合っている彼女のごキゲンうかがいもせにゃならん。
ところがこの女、毎回おごってやっても当然って顔をして、「ありがとう」「ごちそうさま」の一言さえいいやしない。
むこうのほうが高給取りで、年に二回もブランド品を漁りに海外旅行に行くくせして、である。
それでも将来はこいつと結婚しようと思っているのだが、こちとら結婚資金などまったく貯まらない。
もちろん、家を買うなんて、夢のまた夢。
そのうち彼女から、「そんな甲斐性のないあんたとなんか、結婚したくないわ」とか言われそう。
でも、そんな自己チュー女でも、ふられたら次のがなかなか見つからないから、ワガママを聞いてやるしかない。クソッ!
でも生きてりゃなんかいいことあるべさと、上司のクドい小言もさらりと聞き流し、しぶとくしたたかに世間をば渡る。
これぞヤン・サラの生きる道と見つけたり!(なんちゃって)
先日、厚木ファッツ・ブルースバンドの対バンとして、横浜日ノ出町「GUPPY」に登場したバンド、YAN楽団。
彼らの自主制作CDを、知人のCさんから頂戴したのだが、これがなかなか面白い。
このバンドは彼の率いるバンド同様、横浜をホームグラウンドとしている。
リーダーのYAN(ヤン)こと秋山幸人はバンドの楽曲の大半を書き、リード・ヴォーカルとギターを担当。
その他はリードギター、ベース、サックス、男性ヴォーカル1、女性ヴォーカル1、キーボード、ドラムスという総勢8人の大所帯だ。
音のほうは、わりとオーソドックスな(米国系)ロック、ソウル、ブルースが中心で、カッチリとしたバンド・サウンドなのだが、なにより魅力的なのが、その歌詞だ。
キレイごとなんかクソくらえ!とばかり、本音120%で綴られた歌詞に、なんとも好感が持てるのである。
ピアノ・インストの(1)に続いて始まる(2)は、まさにYAN楽団サウンドのショーケース的一曲。
アップテンポの軽快なビートにのってYANが歌うのは、言ってみれば自分自身への応援歌だ。
「もっと もっと モットー!」「短い人生だから/いいたいこと言っちまえーよ!」というアジテーションを自らに投げつける気弱な男の心情は、筆者にもわかりすぎるほどよくわかる。
あのとき、勇気があれば○○が出来たのに…みたいな情けない状況は、20代のころの筆者そのまんまでもあるからネ。
また、テンポ・チェンジをしてブルース調になってからの後半は、セクハラ厚顔オヤジを揶揄した歌詞が超笑えます。
リーダーYANの歌声は、ラフでザラッとした感じではあるが、むしろそのビターな声質が、このバンドの辛口な味わいの楽曲にはしっくりとくるし、説得力もある。
フォービートのジャズィなアレンジにのって歌われるのは(3)。曲調とは裏腹の「C調」な歌詞がいい。
もうバレバレでもいいから、舌先三寸、でまかせでこの土壇場を乗りきれと、YANがアジる。奇妙な味わいのユーモアが光る一曲。
(4)は音こそSAS風の湘南サウンドだが、けっしてさわやか一辺倒な内容ではなく、これからお別れしようというのに、金がないので行き場所もなく、ただただ公園のベンチに座っているしかないという、悲しき貧乏カップルを歌ったもの。
しみじみとした、でもどこかおかしな世界。曲と詞の、独特のミスマッチ感覚が、面白い。
(5)は紅一点のメンバー、ケツ子こと植村結子のリード・ヴォーカルによる、他の曲とはだいぶん趣きの異なる、叙情的なバラード・ナンバー。
少しハスキーな彼女の歌声はどこか懐かしく、聴く者の心を和ませるものがあってなかなかいい。グループ中では、一服の清涼剤のような存在だ。
(6)は、これまたいかにもYAN楽団らしいナンバー。ゴリゴリのファンク・サウンドにのせたラップで、スチャラカ営業マンの日常を歌うナンバー。
ここではもうひとりの男性ヴォーカル、鈴木敏弥も活躍。おまけに、大サービスでケツ子嬢によるセクシー・ヴォイスまで入ってます(笑)。
(7)は、アコースティック・ギターをフィーチャ-したバラード。一種独特のメランコリックでグルーミィな雰囲気を持つ小品。
これを聴けば、YANのもつ幅広い音楽性を感じることが出来るだろう。
(8)はへヴィーなビートでグイグイ押しまくる、ブルース。しかし歌の内容は、見事に軽い(笑)。この対照がまたいい(笑)。
重たいネタを重たく歌ったんじゃ、クドすぎる。ここは「なんちゃって」精神で、ヒョイヒョイと相手をはぐらかしつつ、調子よくいくべし。
現代という「先の見えない時代」においては、それもまたひとつの処世訓だろう。YANはそれを皮膚感覚で見事に会得している。
(9)は唯一、英語詞によるフォーキーなナンバー。ここでは日本人らしからぬYANのメロディ・センスを感じる。まるで、英米産の曲のように聴こえるのである。歌いぶりも、実にシブカッコいい。
さて、アルバムもいよいよ佳境に入り、(10)、(11)と、なかなかリキの入ったナンバーが続く。
(10)はとりとめのない歌詞の中に、作者の偽らざる心境を映し出しているように思える、陽気なロック・ナンバー。
「なすがままで矛盾だらけで今のままでいい」。この詞は決して卑屈な居直りなどでなく、もっと自分のことを大切にしよう、愛そうじゃないかという主張だと思う。
挫折だらけの青春でも、凹んでばかりいないでポジティヴに生きていくことで、何か光明が見えてくるもの、そういうことを言ってるような気がする。
そういう意味で、YANの曲は、よく歌詞を聴き込めば、単なるオチャラケ、コミック・ソングではなく、どこか深遠な哲学さえ匂わせるところがある。
続く(11)も、アメリカン・ロックの王道的サウンドが心地よいナンバー。メンバー全員、実に伸び伸びと豪快に演奏しているのがグッド。
この歌により、青春を過ごした者なら誰でも感じたことのあるであろう「無力感」を、叙情感あふれる言葉にまとめあげたYANは、本当に"詩人"だと思う。美しいメロディに負けず劣らず、歌詞がいいのだ。
ラストの(12)は、(8)のアコースティック・ヴァージョン。メロディも、カントリー・ブルース風にいなたくアレンジしている。
見事に肩の力の抜けたサウンド、そして言葉。なかなかええですね。
以上、YAN、そしてその仲間たちの、実にさまざまな音楽性が詰め込まれたこのアルバムは、聴くたびにさまざまな発見があり、味わいがさらに深くなる。
だから、今後も末長くお付き合いできる一枚になりそうだ。
(余談)今月18日のグッピー・ライヴのとき偶然、YAN楽団のヴォーカル、トシヤ君とうちのバンドのドラマー、K君がかつての仕事仲間であったことが判明してしまった。まったく世間は狭いね(笑)。
<独断評価>★★★☆