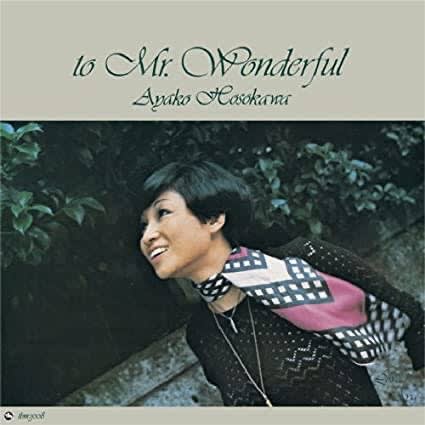2023年1月31日(火)

#440 久保田利伸「Such A Funky Thang!(サッチ ア ファンキー サング!)」(CBS/SONY 32DH 5131)
日本のシンガーソングライター、久保田利伸のサード・アルバム。88年リリース。久保田自身とロッド・アントゥーンによるプロデュース。
久保田は62年静岡生まれ。学生時代にヤマハのコンテストでベストボーカリスト賞を取ったことからチャンスを掴み、86年レコードデビュー。翌年、4thシングル「CRY ON YOUR SMILE」がヒットして一般リスナーにも知られるようになる。
88年初頭にTVドラマの主題歌ともなった「You were mine」が大ヒット、その勢いで7月に本盤をリリースしている。
あえてその曲を入れていないあたり、久保田が自分の音楽、そして人気に自信を持つようになって来たしるしではないだろうか。
果たして本盤は、見事オリコン週間1位、年間4位という大ヒットを記録したのである。
シングルに頼らずのこのセールスは、立派というしかない。
全曲、作曲は久保田自身による。作詞は川村真澄、久保田、もしくは久保田と川村の共作だ。
アレンジはキーボード・ドラムス奏者でもあるプロデューサー、アントゥーンが主に手がけている。
オープニングの「Dance If You Want It」はリカット・リミックス・ミニアルバムともなっている、本盤の代表曲。アントゥーンとの共同作曲。
タイトル通り、ダンスに最適のミディアム・ビート・ナンバー。
久保田といえば、この手のダンサブルな曲がすぐに脳裏に浮かんでくる。
「High Roller」はコール&レスポンスを含む、アップ・テンポのナンバー。
パワフル、エネルギッシュといった久保田のパブリック・イメージまんまの曲だ。「You were mine」も、この流れにある。
「Love Reborn」は久保田のもうひとつの得意分野、バラード・ナンバー。
ファースト・アルバムの「Missing」以来、この路線のファンは実に多い。
愛をもう一度取り返したい恋人たちに捧ぐ、心に響く歌声だ。
「Yo Bro!」はレゲエ・ビートが印象的な一曲。
音楽こそは絆という、すべてのソウル・ブラザーたちに向けたナンバー。
「Merry Merry Miracle」はラテン・ファンクともいうべき陽気な一曲。
ご機嫌なビートに、思わず身体も動き出す。
「Such A Funky Thang! ~隕石が落ちた日~」は当時のブラック・ミュージックの流行を取り入れたサウンド。
短いがラップも聴くことが出来る。
同時期にブレイクしたボビー・ブラウンあたりにも通じるノリのナンバー。
「gone gone gone」は静かなバラード・ナンバー。
こういう繊細な失恋ソングにも、久保田の滑らかなボーカルはぴったりである。
「すべての山に登れ」はシンセ・ビートがアクセントとなったファンク・ナンバー。
歌詞はたぶん、ロジャーズ=ハマースタイン作のミュージカル・ナンバーから来ているのだろうが、こちらはひたすらファンキーである。
「Boxer」はアップ・テンポのファンク・サウンド。久保田の独壇場だな、こういう曲は。
ブラック・ミュージックに影響を受けて、自己の音楽作品に反映させているジャパニーズ・ミュージシャンは、山下達郎をはじめとして枚挙にいとまがないが、ここまで一筋に「ブラック命」な日本人は他にいない。
たぶん、前世は黒人だったのであろう。
「Indigo Waltz」はワルツ・ビートのバラード。
バラードにもいくつかのタイプがあり、甘い予感を歌うもの、ハッピーなラブソングもあれば、悲しい別れの歌もある。
この曲は別れのバラードに入るのだろうが、悲しみの中にもふたりの愛は本物だったと信じる男心が、聴く者を切なくさせる。
久保田単独の作詞曲、ということは彼自身の経験が強く反映されているのだろうか。
「Drunkard Terry」は「なんとかなるさ」のフレーズが耳に残る、ちょっと脳天気で、クレージーなナンバー。
久保田らしい、はっちゃけぶりがナイスだ。
「覚えていた夢」は哀感に満ちたナンバー。
ダンサブルなミディアム・ビートだが、悲しい結末を予感させる恋を歌っている。
幸せとは感じられない、宙吊り状態の恋。誰にでもあるであろう、その感覚を描き出した川村真澄の歌詞が刺さってくる。
ラストの「Such A Funky Thang! ~Reprise~」は、同曲の短いインストゥルメンタル。
以上13曲と盛りだくさんだが、不思議と一気に聴けてしまう。
これはやはり、久保田の卓越したメロディ・センスと、ハンパない歌唱力によるものなのだろう。
その後35年間、久保田利伸は若干の休止期はあったものの、現在に至るまでアーティスト活動を続けている。
日本ではトップに立ったものの、彼の究極の目標は、本場アメリカで黒人アーティストと同じように認められ、ヒットを出すことであった。
その目標は、95年に「TOSHI KUBOTA」として全米でCDデビューし、その後2004年にTV番組「ソウル・トレイン」に日本人としてはYMOに次いで2組目の出演を果たしたことで、それなりに達成したともいえる。
が、たぶん、久保山自身はそれで満足はしていないような気がする。
本物のファンキーを生涯をかけて追求している彼としては、自分の音楽が「アジア人の音楽」として黒人ミュージシャンのそれと区別されることなく、ごく自然に受け入れられるまでは、その挑戦は続くのだろう。
国内での高い評価に甘んじることなく、常にリアルなファンキー・ミュージックを目指す姿勢、見習いたいと思う。
<独断評価>★★★☆
日本のシンガーソングライター、久保田利伸のサード・アルバム。88年リリース。久保田自身とロッド・アントゥーンによるプロデュース。
久保田は62年静岡生まれ。学生時代にヤマハのコンテストでベストボーカリスト賞を取ったことからチャンスを掴み、86年レコードデビュー。翌年、4thシングル「CRY ON YOUR SMILE」がヒットして一般リスナーにも知られるようになる。
88年初頭にTVドラマの主題歌ともなった「You were mine」が大ヒット、その勢いで7月に本盤をリリースしている。
あえてその曲を入れていないあたり、久保田が自分の音楽、そして人気に自信を持つようになって来たしるしではないだろうか。
果たして本盤は、見事オリコン週間1位、年間4位という大ヒットを記録したのである。
シングルに頼らずのこのセールスは、立派というしかない。
全曲、作曲は久保田自身による。作詞は川村真澄、久保田、もしくは久保田と川村の共作だ。
アレンジはキーボード・ドラムス奏者でもあるプロデューサー、アントゥーンが主に手がけている。
オープニングの「Dance If You Want It」はリカット・リミックス・ミニアルバムともなっている、本盤の代表曲。アントゥーンとの共同作曲。
タイトル通り、ダンスに最適のミディアム・ビート・ナンバー。
久保田といえば、この手のダンサブルな曲がすぐに脳裏に浮かんでくる。
「High Roller」はコール&レスポンスを含む、アップ・テンポのナンバー。
パワフル、エネルギッシュといった久保田のパブリック・イメージまんまの曲だ。「You were mine」も、この流れにある。
「Love Reborn」は久保田のもうひとつの得意分野、バラード・ナンバー。
ファースト・アルバムの「Missing」以来、この路線のファンは実に多い。
愛をもう一度取り返したい恋人たちに捧ぐ、心に響く歌声だ。
「Yo Bro!」はレゲエ・ビートが印象的な一曲。
音楽こそは絆という、すべてのソウル・ブラザーたちに向けたナンバー。
「Merry Merry Miracle」はラテン・ファンクともいうべき陽気な一曲。
ご機嫌なビートに、思わず身体も動き出す。
「Such A Funky Thang! ~隕石が落ちた日~」は当時のブラック・ミュージックの流行を取り入れたサウンド。
短いがラップも聴くことが出来る。
同時期にブレイクしたボビー・ブラウンあたりにも通じるノリのナンバー。
「gone gone gone」は静かなバラード・ナンバー。
こういう繊細な失恋ソングにも、久保田の滑らかなボーカルはぴったりである。
「すべての山に登れ」はシンセ・ビートがアクセントとなったファンク・ナンバー。
歌詞はたぶん、ロジャーズ=ハマースタイン作のミュージカル・ナンバーから来ているのだろうが、こちらはひたすらファンキーである。
「Boxer」はアップ・テンポのファンク・サウンド。久保田の独壇場だな、こういう曲は。
ブラック・ミュージックに影響を受けて、自己の音楽作品に反映させているジャパニーズ・ミュージシャンは、山下達郎をはじめとして枚挙にいとまがないが、ここまで一筋に「ブラック命」な日本人は他にいない。
たぶん、前世は黒人だったのであろう。
「Indigo Waltz」はワルツ・ビートのバラード。
バラードにもいくつかのタイプがあり、甘い予感を歌うもの、ハッピーなラブソングもあれば、悲しい別れの歌もある。
この曲は別れのバラードに入るのだろうが、悲しみの中にもふたりの愛は本物だったと信じる男心が、聴く者を切なくさせる。
久保田単独の作詞曲、ということは彼自身の経験が強く反映されているのだろうか。
「Drunkard Terry」は「なんとかなるさ」のフレーズが耳に残る、ちょっと脳天気で、クレージーなナンバー。
久保田らしい、はっちゃけぶりがナイスだ。
「覚えていた夢」は哀感に満ちたナンバー。
ダンサブルなミディアム・ビートだが、悲しい結末を予感させる恋を歌っている。
幸せとは感じられない、宙吊り状態の恋。誰にでもあるであろう、その感覚を描き出した川村真澄の歌詞が刺さってくる。
ラストの「Such A Funky Thang! ~Reprise~」は、同曲の短いインストゥルメンタル。
以上13曲と盛りだくさんだが、不思議と一気に聴けてしまう。
これはやはり、久保田の卓越したメロディ・センスと、ハンパない歌唱力によるものなのだろう。
その後35年間、久保田利伸は若干の休止期はあったものの、現在に至るまでアーティスト活動を続けている。
日本ではトップに立ったものの、彼の究極の目標は、本場アメリカで黒人アーティストと同じように認められ、ヒットを出すことであった。
その目標は、95年に「TOSHI KUBOTA」として全米でCDデビューし、その後2004年にTV番組「ソウル・トレイン」に日本人としてはYMOに次いで2組目の出演を果たしたことで、それなりに達成したともいえる。
が、たぶん、久保山自身はそれで満足はしていないような気がする。
本物のファンキーを生涯をかけて追求している彼としては、自分の音楽が「アジア人の音楽」として黒人ミュージシャンのそれと区別されることなく、ごく自然に受け入れられるまでは、その挑戦は続くのだろう。
国内での高い評価に甘んじることなく、常にリアルなファンキー・ミュージックを目指す姿勢、見習いたいと思う。
<独断評価>★★★☆