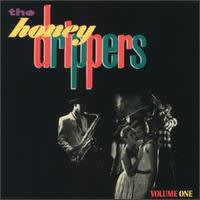2001年12月15日(土)

V.A.「GUITAR SPEAK III」(ビクター音楽産業 VICP-5116)
1.CRYSTAL BALL(NILS LOFGREN)
2.A LIFE IN MOVIES(STEVE HACKETT)
3.THE 62(TOM VERLAINE)
4.NO WATER IN HELL(BOB MOULD)
5.STILL LIFE WITH A DOBRO(ADRIAN BELEW)
6.THAT BOY'S EVIL(GARY MYRICK)
7.RED SHOES(MICK TAYLOR)
8.OTIS(DOMINIC MILLER)
9.EYE OF THE NEEDLE(ROBERT FRIPP AND THE LEAGUE OF GUITARITS)
10.MORNING RUSH HOUR(STEVE MORSE)
以前、ウィッシュボーン・アッシュのインスト・アルバム「ヌーヴォー・コールス」を取上げたが、今日の「ギター・スピークIII」もそれと同じくIRSレーベルの「ノー・スピーク」シリーズからの一枚だ。
新旧とりまぜた、実力派ギタリストたちによる、オムニバス・インスト・アルバム。91年リリース。
これがまた、ギター・ヲタクなら「お~っ!」というような顔ぶればかりなんである。
まずはベテラン・ギタリスト、ニルス・ロフグレンから。筆者の世代には「宙返りギタリスト(!)」として有名なひとである。
彼を語るとき、ついついそのアクロバティックなパフォーマンスばかり言及しがちだが、どっこい、音楽的にも大変しっかりしたものを持っている。
二ール・ヤングやブルース・スプリングスティーンといった大物ロッカーたちにも厚く信頼されているのが、その証左だろう。
このアルバムで演奏する(1)は、自身のオリジナル。多重録音を駆使した、分厚いギター・ハーモニーが印象的な一曲。
続いて、これまた大ベテラン、スティーヴ・ハケットが登場。ジェネシスのギタリストとして、彼らの黄金期を築いた男である。
ジェネシス脱退後は、ソロ、そしてスティーヴ・ハウとのグループ「GTR」でも活躍している彼の収録曲は、(2)。自身のオリジナル。
どこか中近東風のエキゾチックなリフあり、HM風のおいしいメロディアスなソロあり、アコギの繊細な響きあり。高度のテクニック、幅広い音楽性が盛り込まれた一曲だ。
(3)を演奏するのは、ご存知、ニューヨークのパンク・バンド「テレヴィジョン」のリーダーであった、トム・ヴァーライン。
現在はソロで活動している彼のオリジナル。ソリッドで重心の低いギター・サウンドは、なんともいえずカッコよろしい。エコーの使いかたが実にうまく、耳に心地よい響きをもたらしてくれる。
次に登場する、ボブ・ムールドは、知名度はかなり低いかも知れないが(実は筆者も初めて聴いたクチである)、アメリカの若い世代のギタリストの中では、実力派の評価が高いという。
以前には「「ハスカー・ドゥ」というバンドにいたという彼のオリジナルが、(4)。
デス・メタルのビートにのって、メロディともノイズともつかぬ、アヴァンギャルドなソロ・プレイが展開される。
「カオス・サウンド」ともいうべき、過激な音の洪水に、身をゆだねてみよう。
さて、(5)では、多くのロック・アーティストのバッキング(ザッパ、ボウイ、トーキング・ヘッズなど)、そしてキング・クリムゾンのメンバーとしても知られる名ギタリスト、エイドリアン・ブリューが登場。
ここで彼は、なんと、エレキ・ギターではなくドブロ(リゾネイター)を弾いている。
ハワイアン、カントリー、ブルースなどでは使われるものの、あまり一般的ではないこのギターを使って、彼は実に不思議なムードのオリジナル曲を演奏する。現代音楽風というか、環境音楽というか、静謐ながら妖しい。
さすが、ロックの狭い範疇にとどまることのない、超実力派だけのことはある。目からウロコ!な一曲である。
(6)は、これまた新世代のホープ、ゲイリー・ミリックのオリジナル。
若手とはいえ、すでにスティーヴィ・ワンダーや、ジャクスン・ブラウンといった大物にも認められ、アルバムに参加しているぐらいだから、ただのヒヨッコではない。自身が率いるバンド、ザ・フィンガーズでも活躍。
収録曲は、ヴェンチャーズの「パイプライン」を下敷きにしたものだが、そのHMをベースにしたギター・プレイはあくまでもヘヴィーで、攻撃的。
ノーキーもびっくり。新世代の「エレキバンド」サウンドとは、まさに、これなのかも知れない。
さて、筆者の世代にも大変おなじみの名前が登場。ミック・テイラーである。
ブルースブレイカーズ、ストーンズを経て、ソロで活動を続ける彼の収録曲は、(7)。
第二期ジェフ・ベック・グループにいたキーボーディスト、マックス・ミドルトンと組んでの演奏だが、これはミドルトンの作品。ここでミックは、音色といいフレーズといい、フュージョン色の濃いプレイをしているので、ミック=ブルース・ギタリストという先入観で聴くと、だいぶん違うので驚くかも知れない。
91年当時、彼はかなりフュージョンに入れ込んでいたのである。現在ではまた、ブルースに回帰しているのだが。
いつもとはちょっとテイストの変わったミックの演奏を、味わってみてほしい。
続く(8)は、アメリカ人ギタリスト、ドミニック・ミラーのオリジナル。
ミラーも、クリッシー・ハインド率いる人気バンド、プリテンダーズをふりだしに、いくつかのバンドを渡り歩き、スティングのバンドに参加するようになった、「ギターを抱いた渡り鳥」的存在。
そのキャリアはダテではないことがよくわかるのが、この演奏だ。ファンキーなビートにのせて、伸びやかなトーンで、余裕たっぷりのプレイを聴かせてくれる。
そのフレーズには、ブルーズィなセンスも十分感じられる。
お次は、ミック・テイラーにも負けないベテランが、登場。ロバート・フリップだ。
ロック・ファンなら知らぬ者はない、キング・クリムゾンの中心的存在。30年以上、常にトップを走り続け、さまざまな話題を提供し続ける男である。
そんな彼が、アコースティック楽器だけで編成したオーケストラが「ザ・リーグ・オブ・クラフティ・ギタリスツ」である。彼のオリジナル曲、(9)を収録。
端正でセンシティヴ、自然体なサウンドが聴ける。稀代のプログレ・バンド、クリムゾンとはまた違った、彼の一面を知ることが出来る。
さて、大トリは、「カンサス」などのバンドでプレイしてきたキャリアを持つ、スティーヴ・モーズ。自身のオリジナル、(10)を収録。
彼のプレイはHR/HMを基本にしながらも、シンフォニックな音作りを持ち込むなど、そこにとどまらない音楽的な広がりを感じさせる。今後も活躍が期待されるプレイヤーのひとりだ。
以上のように、全編、トップ・プレイヤーたちの、スーパー・テクニックとアイデアに満ちた演奏を収録。
これだけのテクニシャンたち10名の演奏が一枚で聴けるのだから、筆者を含めたギター・ヲタクどもにはこたえられない。
ライヴ盤も含めて4枚も出ている「ギター・スピーク」シリーズ、ギターにうるさい貴方なら、ぜひチェックしてみてほしい。