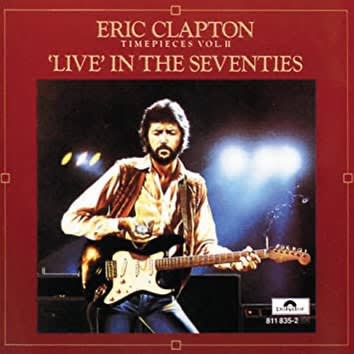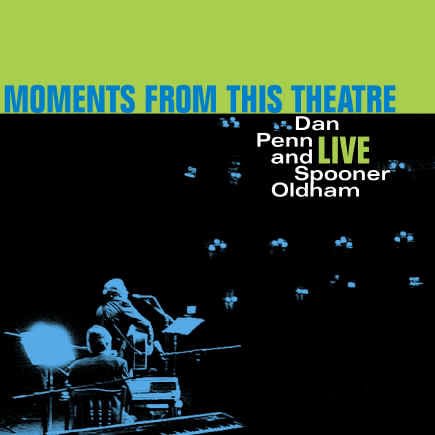2002年6月2日(日)

#106 ブラインド・フェイス「スーパー・ジャイアンツ・ブラインド・フェイス」(ポリドール POCP-2268)
1.HAD TO CRY TODAY
2.CAN'T FIND MY WAY HOME
3.WELL ALL RIGHT
4.PRESENCE OF THE LORD
5.SEA OF JOY
6.DO WHAT YOU LIKE
7.EXCHANGE AND MART
8.SPENDING ALL MY DAYS
ここのところブルースが続いたので、ちょっと気分転換。
ブラインド・フェイス、最初にして最後のアルバム。69年リリース。
68年11月、かのエリック・クラプトンを擁していたバンド、クリームは解散したが、翌年クリームを母体に結成されたのがこのブラインド・フェイスである。
当時、いくつかの有名バンドの元メンバーから作られた、いわゆる「スーパー・グループ」がブームとなりつつあった。
元ハードのピーター・フランプトン、元スモール・フェイシズのスティーヴ・マリオットを中心にしたハンブル・パイしかり、元バーズのデイヴィッド・クロスビー、元バッファロー・スプリングフィールドのスティーヴ・スティルス、元ホリーズのグレアム・ナッシュによるCS&Nしかり。
このブラインド・フェイスも、そういったブームの流れの中にあった。デビューコンサートは、ロンドンのハイドパークで10万人の観客を前に行ったというし、このデビューアルバムのセールスも、すさまじかったらしい。
しかし、評価は必ずしも高くはなかった。当時の「ニューミュージック・マガジン(現ミュージック・マガジン)」のレビューとかを読むと、「CS&Nのアルバムを聞いたとき以上の物足りなさを感じた。」(福田一郎氏評)とある。リスナーの多くは、クリームをさらに超えるような、スリリングでハード、へヴィーな演奏を期待していたのだが、肩すかしをくらったのである。
要するに、周囲の「期待」が大き過ぎたといえる。
メンバーを見れば、まあ、それもしかたない。エリック・クラプトン、ジンジャー・ベイカーの元クリーム組に加え、当時メキメキを頭角をあらわしていたバンド、トラフィックの看板スターであったスティーヴィ・ウィンウッド、そしてその三人に比べればかなり小粒だが、ファミリーというバンドでマルチ・プレイヤーぶりを発揮していた実力派のリック・グレッチ。
このメンツでスゴいサウンドを期待をするなというのが、ムリというものだろう。
「ブラインド・フェイス(盲目的信頼)」というグループ名も、彼らが、自分たちへの周囲の過大な期待に対する皮肉として、つけたものらしい。
で、30年以上の歳月を経て、この話題作(問題作?)を再度検証してみる。
まずはウィンウッドのオリジナル、(1)から。ヴォーカルも、ウィンウッド。というより、このグループでは原則的に彼しかリードをとっていない(後で例外のトラックも出てくるが)。
クリーム時代には少し歌っていたクラプトンも、実力派シンガーとして十代のころから高い評価のあったウィンウッドの前では萎縮して、自分から歌いたいとは言えなかったようだ。
ゆったりした曲調、トラフィック的な雰囲気を多分にたたえたサウンド。そしてウィンウッドの見事な高音のシャウト。
クラプトンも間奏では弾きまくってはいるものの、主役はどう見てもウィンウッド、である。
(2)は、のちにクラプトンもコンサートではよく取上げるようになったウィンウッド作のナンバー。
繊細で美しいメロディが、なんとも印象的。やはり、ウィンウッドの歌のうまさはピカ一といえよう。そして、クラプトンのアコギによる好バッキングも光る。
クラプトンがステージで歌う際は、キーが高かったため、リードをイヴォンヌ・エリマンほかの女性シンガーに預け、自身はハーモニーをつけている。
(3)は、伝説のロックン・ローラー、バディ・ホリーの代表的ナンバー。オルガン、ピアノ、そしてヴォーカル&コーラスとウィンウッドが八面六臂の大活躍。
間奏のピアノ・ソロではジャズィな側面も見せ、このグループがハード・ロックのような方向を目指しているのではないことを感じさせる。こうなると、どうしても、クラプトンの影は薄くならざるをえない。
(4)はクラプトンが作り、ウィンウッドが歌ったナンバー。クラプトン自身も大変気に入り、後にはライヴで必ず自ら歌うまでになっている。
神への感謝の気持ちをこめて書かれた、スローテンポのおごそかなバラード・ナンバー。もちろん、ウィンウッドのソウルフルな歌いぶりはパーフェクトだ。
途中、テンポチェンジをして、クラプトンのワウ・ギターがフィーチャーされる。クラプトンのギターは意外に出番が少ないだけに、ファンとしては聴き逃せないところだ。
(5)は、再びウィンウッドの作品。これもなかなか「ウィンウッド節」のきいた、ソウル色豊かなナンバー。
こうやって見てくると、明らかにクリームよりは、トラフィックのカラーのほうが強いサウンドだといえそうだ。
この曲ではリック・グレッチのエレクトリック・ヴァイオリンのソロがメイン。ギターはいまひとつ表に出ず、リズムやリフ中心にとどまっている。
クリーム・ファンだったひとたちに、こういう非ハード・ロック的展開が不評だったのは、想像に難くない。
(6)は唯一、ジンジャー・ベイカーの作品。冒頭と終盤ではヴォーカルが聴かれるが、15分以上という長丁場の大半は、各プレイヤーのインプロヴィゼイション。
それも、ハード・ロックではなく、ジャズに近いアドリブ合戦。クラプトンの音も、明らかにクリーム時代のそれから変化を見せつつある。
クリーム後期から使いはじめたファイアーバードが、彼の当時のメインギターだったようだが、そのソリッドでクリーンなトーンキャラクターを生かすように弾いている。後のストラト路線への「過渡期」の音といえよう。
途中、中だるみっぽい展開もあり、また、混沌としたエンディングといい、果たしてLPの片面の大半を使ってやるようなことか?という疑問も出てこなくはないが、これはこれで彼らとしての「実験」であったのだろう。
実際、彼らは自らを「パーマネント・グループ」とはあまり認識していなかったそうだ。むしろ「スーパー・セッション」のような臨時編成のセッション、プロジェクト、そういう意識のほうが強かったらしい。
クリーム時代からもともと、クラプトンとベイカーは仲がよくなかったそうで、ウィンウッドがベイカーをメンバーとして希望しなかったらこのプロジェクトは成立しなかったという裏事情から考えても、ブラインド・フェイスがその後、正式な解散発表をすることなく空中分解を迎えたのは無理からぬことだったといえよう。
世間的には、全米ツアーを行い、スタジアムクラスの会場を毎回満杯にした(もちろん、クラプトンの人気によるもの)こととはうらはらに、グループの将来の「見取り図」はなにもなかったのである。
作り手の意識と、聴き手のそれとには、常にギャップがあるものだが、ここまで乖離しているケースも珍しい。
さて、最後の2曲はアルバム発表時には未収録だったトラック。
(7)は、ウィンウッド作のインスト・ナンバー。クラプトンのギターと、グレッチのエレキ・ヴァイオリンのからむリフが耳に残る。これも、いわゆるハード・ロック色はまったくなく、かといってブルースとも違う。むしろ、後のキング・クリムゾンのような「プログレ色」を感じさせて興味深い。
もちろん、クラプトンは年を追うごとに非インスト色を強め、以後その方向には、まったくいかなかったのだが。
(8)はある意味、「問題作」。なんでこんなテイクを収録したのか、さっぱりわからない。
ウィンウッドの作品なのだが、歌っているのはウィンウッドとはとても思えない。たぶんグレッチだと思うのだが、まるでアマチュアバンドのような(!)ヘタさ加減に笑ってしまう。おまけにバンド演奏も、タイトとはいいがたい適当なもの。
これって、シャレのつもり!?
まあ、オリジナル・イッシューから外して正解でした。
ということで、とてつもない「期待」を寄せられて出発したわりには、フツーのレベルの作品しか作れずに多くのファンの落胆をよんだというアルバムだったが、一曲一曲よく聴きこめば、大半は水準以上の出来ばえであるし、そう悪くもない。
とくに(2)や(4)は、後世にも残った名曲。(3)や(5)もよく出来ている。
ややウィンウッドが目立ち過ぎのきらいがあり、クラプトン・ファンには不満もあるだろうが、ウィンウッドの歌のうまさがこの一枚を救っているのも事実。
あなたも、たまにはライブラリーから引っぱり出して、聴いてみよう。
<独断評価>★★★☆