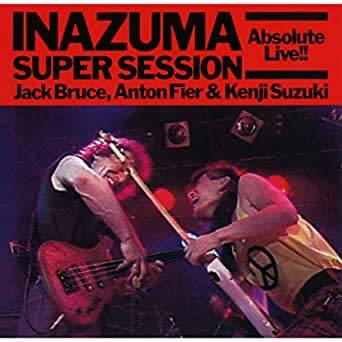2003年12月21日(日)

#198 山下達郎「シーズンズ・グリーティングス」(MOON AMCM-4180)
クリスマスも近いので、今回は「季節モノ」。山下達郎のクリスマス・アルバムである。93年リリース。
彼が83年にリリースしたシングル、「クリスマス・イブ」がいまだに売れ続けており、わが国における「ホワイト・クリスマス」並みのスタンダード・ナンバーになりつつある。
その英語詞版「CHRISTMAS EVE」、そしてア・カペラの「ホワイト・クリスマス」を中心に構成された、クリスマス・ソングの集大成盤がこれである。
多重録音によるア・カペラあり、オーケストラ&コーラスのゴージャスなバッキングによるものあり。いずれにせよ"凝り性"な彼の真骨頂がタンノウできます。
<筆者の私的ベスト4>
4位「SMOKE GETS IN YOUR EYES」
実はこれはクリスマスとは関係ないナンバーだが、出来がいいのでピックアップ。いうまでもなく、プラターズのビッグ・ヒット、「煙が目にしみる」である。
元々はジャズ作曲家、ジェローム・カーンが1933年に作った古~い曲。これを戦後プラターズがR&Bとして蘇らせ、さらに達郎が新しい衣を着せて歌い継いでいるのだ。70年の年月を越えて生き続ける、究極のスタンダード・ナンバー。
優雅なストリングス、ホーンの演奏に乗せて、いかにも心地よさげに、高らかに歌う達郎。
プラターズの絶唱にもひけをとらない、快唱であります。
3位「HAPPY HOLIDAY」
多重録音による、ドゥ・ワップ・コーラスが印象的なナンバー。58年、シェルズなる黒人コーラス・グループによるヒット、といっても日本ではほとんど知られていないが。
達郎はおなじみの「ON THE STREET CORNER」シリーズで、この手のコーラスにたびたびトライしているが、これもその延長線上のサウンド。
いかにも生きがよく、キャッチーなハーモニーに、心底ハッピーな気分になってしまう。
こういう「勢い」のある曲のほうが、シナを作って甘~く歌うタイプの曲よりも出来がいいと思ってしまうのは、筆者だけ?
2位「CHRISTMAS EVE」
これは「MELODIES」のオリジナルのバック・トラックを使い、アメリカのシンガー・ソングライター、アラン・オデイによる英語詞で歌うヴァージョン。オデイは「YOUR EYES」「BIG WAVE」なども作詞しており、達郎と係わりが深い。
原曲のイメージにほぼ近いドラマが展開される歌詞に、思わず落涙してしまうリスナーも少なからずいるだろう。かくいう筆者もそのクチ!?
クリスマスといえば楽しく、ハッピーな日、こういう一般的なイメージの逆をついて、大失恋、大悲劇の日にもしてしまった達郎。
日本では、クリスマスにデートできるひと、できないひとと、はっきり色分けされてしまう文化が、このヒット以来できてしまったような印象がある。(特にバブル期以降。)
なんだかな~。彼の曲も、功罪半ばという気がするね(笑)。大体、日本人はクリスマスという神聖な祭典を、何だと思ってんだ!
それはさておき(笑)、そういう悲しい、後ろ向きの内容の歌なれど、やっぱりいい曲だと思う。
アーティストは誰でも、「会心の一作」をものするために、ああでもない、こうでもないと試行錯誤を繰り返すものだろうが、これは「神が降りてきた」、そういう一曲だと思う。今後も、多くのひとびとに愛され続けていくことは、間違いないだろう。
1位「WHITE CHRISTMAS」
1位はやはり、これしかあるまい。数々のスタンダード曲をものした大作曲家、アーヴィング・バーリン、42年の作品。
第二次大戦中に書かれたこの一曲が、稀代のクルーナー、ビング・クロスビーという歌い手を得たことで、世界一売れたシングルとなったのである。
60年以上、米国内のみならず、世界中で歌いつがれているのだから、達郎の20年というロング・ヒットもまだまだスケールが小さい、小さいってことやね。
ヤマタツさんもまだ50そこそこだろうから、これからも30年、40年、よぼよぼのジイサンになるまで、「クリスマス・イブ」を歌い続けていって欲しいもんだ。「日本一のロング・ヒット」ぐらいには、認定されるかもね。
余談はともかく、このア・カペラ版「ホワイト・クリスマス」、その多重録音に対する凝りかたはハンパではない。
何十回も執拗にコーラスを重ねていくことで、この曲にクロスビー版とはまったく違った、聖歌のような厳かさを与えることに成功している。
音の求道者・山下達郎の、まさに面目躍如なトラックである。必聴。
他にもクリスマスがらみの、有名曲、シブめの曲、各種満載であります。ハッピーなクリスマスをお迎えのかたも、残念ながらそうでないかたも、BGMにぜひどうぞ。
<独断評価>★★★☆