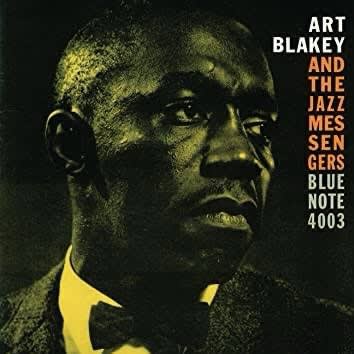2004年11月7日(日)
#248 BEAT CLUB ALL STARS「BEAT CLUB ALL STARS」(Yotsuba Records BCS-OM001)
栃木県宇都宮市にある、ライブハウスを兼ねたスタジオ、「BEAT CLUB STUDIO」。そこに集うミュージシャンたちの集団「BEAT CLUB ALL STARS」がリリースしたオムニバス・アルバム。インディーズレーベル「Yotsuba Records」より本年リリース。
実はこの一枚、知人のhisaeさんからありがたくも頂戴したのだが、一度聴いてみて、そのクォリティの高さにビックリしてしまった。
もう、この中からすぐにメジャー・シーンに躍り出てもおかしくないレベルのアーティストが何組もいるのだよ。
いずれのアーティストも、基本的にはアコースティックギターをフィーチャーしたサウンドなのだが、フォーク、ボサノバ、フュージョン、ブルースなど極めてバラエティに富んでいてあきさせない。
ショート・ジングル「BEAT CLUB STUDIO」で登場するのはトリオ編成のJamsbee。
2曲目の「Cafe Deja Vu」は英語詞による、フォーキーなバラード。
リードヴォーカル・上原誠のせつない歌声、廉慎介のハモりが、いい雰囲気を出してる。ギター2本、べースによるアンサンブルも綺麗にまとまっている。
どこか往年のグループ、BREADを想起させる音。筆者のふだん聴いている音楽とはまるきり方向性が違うが、その高い音楽性には素直に賞賛の辞を寄せたい。
続くはソロシンガー・屋代篤司による「エッセンス」。
ふだんはアコギでの弾き語りスタイルのようだが、本盤ではドラムスも加えたメリハリある演奏をバックに、ハイトーンでのヴォーカルを聴かせる。
本人の多重録音によるハーモニーも、なかなか素晴らしい。
2曲目の「熱風」は、ファンク風味のナンバー。ハードにドライヴするアコギ・サウンドを聴かせる。
この曲も、屋代の張りのある硬質な歌声がなんともいい。
ただ、比較的複雑なコード進行にもかかわらず、アレンジがコードカッティング一辺倒なので、いささか違和感がある。編曲にもうひとつ工夫があればさらに良し。
次に登場するのは、ギター、あるいはピアノで弾き語りというスタイルの小川健。曲は「リーフ」と「君に届けたいフレーズ」。かな~り甘口の声なので、筆者的にはちと苦手(笑)。
でも、声質といい、純愛路線の歌詞といい、ポップな曲調といい、いかにも女性にはウケそうだな。守備範囲外なので(笑)、コメントはこのへんで勘弁。
四番手はCliche ♭5(クリシェ・フラット・ファイブ)という、女性シンガーnaomi.kをフィーチャーした2人組のユニット。
サウンド指向の強い、いかにも都会的で洗練された音を聴かせる。お洒落系といいますか。
ヴォーカルが中島美嘉風、ボサノバ調の「影」はことにカッコいい。でもバラードナンバー、「星を数えてる」はちょっとありきたりな曲調かな。何となく今井美樹みたいだし。
筆者的には、彼らに正統派バラード路線よりは、カッとんだお洒落系を歩んで行ってほしいと思うとります。
さて、お次に登場するのはひでぼうず。もちろん、当サイトでもおなじみの、ひであきさんとBoseさん、あのお二人である。
本盤ではべースを加えた編成で、ハードでファンキーな演奏を聴かせてくれる。
インストゥルメンタル・ナンバー、「コブラツイスト(Thousand earthworms feel so good)」は、インプロヴィゼーション炸裂、いかにもフュージョンな一曲。
副題からわかるように、かなりエロティックな含みをもった曲で、なんと、あのhisaeさんやみぎねじさんの色っぽいヴォイスも聴けます。要チェキ!ですぞ。
もう一曲は「Breath」。こちらはヴァイオリンを加え、リラックスした雰囲気のバラード。ヴァイオリンに合わせた歌が聴けますが、このヴォーカルはみぎねじさん。
アコースティック・ギターの美しい響きを最大限に生かした演奏。テクニックには定評のあるこのデュオ、さすがに安心して聴けますな。
続くはえだ たかし。彼もふだんはギターで弾き語りというスタイルのひと。
一曲目の「One Night Blues」は、彼がソロと並行してやっているユニット「みじぇっと」の相方、いしかわ☆さちよとデュエットしたアコギ・ブルース。
この、いしかわ嬢の声が、筆者的にはツボにハマってしまった。ちょっぴりハスキーな泣き節。一度聴いたら忘れられない。
彼女のCDだったら、絶対買って聴くんじゃないかな。ライブでもぜひ一度観てみたい人です。
えだ たかしでもう一曲。こちらはバンド編成での「Fly High!」。清涼感のあるアップテンポのナンバー。
ハイトーンでの歌唱にちょっと不安定なところがあるので、そんへんが彼の今後の課題かな。
そして、超個性派シンガー登場。Mint. 1/2(ミントにぶんのいち)である。アコギとカズーでカントリー調の「電車にゆられて」のようなトッポい曲を歌ったかと思えば、竪琴を達者に弾きながらメロディアスなバラード「感謝のテーマ」をキメたりもする。
ステージでのパフォーマンス、MCも抜群に面白いそうで、ローカルでは既に有名人的存在。
そのうち、メジャーシーンでいつのまにやら活躍してた、なんてなことになりそうな人だね。
最後はふたたびJamsbeeがスタジオライブで登場。歌うは「餃子ブルース」。
この曲はNESTの公開セッション、寿家さんのオフ会でも、ひであきさんらが披露していたので、すでにご存じのかたも多いだろう。
オリジナルはこのJamsbee。とはいえ、もうこの「BEAT CLUB STUDIO」に集う人々にとっては共有財産みたいな愛唱歌になっている。
実際、このテイクでも、オーディエンスとの大合唱になり、盛り上がりまくる。
歌詞は毎回アドリブでいろいろと変わるそうで、そのへんがいかにもブルースっぽくていい。
Jamsbeeの、フォーク路線とはまた違った別の、ブルーズィでファンキーな魅力があふれた一曲である。
以上、さまざまなスタイルのオリジナル・ナンバーがテンコ盛り、約60分、フルに楽しめるので、興味をお持ちになった方は、ぜひ、上記のサイトにアクセスして欲しい。
筆者的には「ひでぼうず」と「えだ たかし&いしかわ☆さちよ」が今もパワープレイ中。
実にナイスな音盤。hisaeさんには、感謝しかない。
<独断評価>★★★★