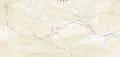7月10日(水曜日)、前回は杉沢コースから登りましたが悪天候に阻まれ山頂へ到達することができませんでしたので、今回は幌加コースから再挑戦です。
前日の夜札幌を立ちます。
大雪ダム湖のそばにある除雪ステーションの片隅にテントを張り仮眠をとります。
朝5時に目を覚まし、行動開始です。
6:00分、登山口までやって来ました。

すでに5台ほど車が止まっています。

登山口です。ここから山頂まで10.5Km、長い戦いの始まりです。
何度か沢を渡り、笹原を歩きます。
以前は笹が登山道を隠すほどに生えていたのですが、今はきれいに刈り取られており道に迷う心配はありません。
所々ぬかるみがありますが、それも好天が続いていた影響で小さくなり靴をドロドロにするほどではありません。
快調に歩いて7:10分、沼まで来ました。


ちょっと、神秘的な雰囲気の沼です。
ここから尾根に向かってドンドン登ります。
これが少し苦しいのですが、少しの仮眠にもかかわらずメンバーは快調に歩きます。
8:35分、細い尾根まで登ってくると山頂が姿を見せてくれます。


ここまではいい天気でしたが・・・
ここから細い尾根を歩きます。
ハイ松が枝を伸ばしており、歩きづらいのですが頑張って先へ進みます。
そうすると、天狗原に上がる沢状の草付き斜面が現れます。

残雪がありますが、もう少し早い時期ですと一面が雪渓となっている沢です。
登るにしたがって傾斜がどんどん増していきます。

最後は土の登山道になるのですが、濡れていると滑るので注意が必要です。

この最後の急騰を登りきると大雪の山並みが見えています。
さあ、ここからは山容が変わり高山の雰囲気が一気に増してきます。


砂礫地の高山帯を歩くと前回引き返した地点に出ます。



ここからニペソツの山頂が見えるはずですが、雲に隠れています。
どうやら天気の具合が怪しくなってきました。


所々に咲いている高山植物のお花に癒されながら歩きます。

そして最後の下りに挑みます。


後ろを振り返るとこんな岩山です。

左手の沢を見るとここにも沢山の花が咲いています。


振り返ると天狗岳が突き上げるように見えています。
最後の急登を耐えると山頂は間近かです。
12:25分、やっと山頂に着きました。
6時間25分かけての山頂です。
しかし、辺りは雲に覆われ眺望がありません。
しかも雨が降ってきました。
雨具を着て記念写真を撮ります。

今回初めてニペソツ山の山頂を踏む2人です。
雨が大粒になり強くなってきましたので、すぐに下山します。
この下山も大変でした。
しかし、何度も休憩を取り、天狗原を降るあたりで雨がやんでくれたのは幸運でした。
アミノバイタルなどのサプリメントの力を借り、弱っているメンバーの荷物を分けて負担を軽くするなどみんなの力を結集しての下山でした。
その甲斐あって、日没寸前の19:15分に下山することができました。

現在では、この幌加コースからしかニペソツ山に登ることができません。
有志の方々によりコース整備が行われており、その努力には感謝しかありません。
ニペソツ山は、とてもいい山です。
ぜひ、みなさんも機会を作って登ってください。
前日の夜札幌を立ちます。
大雪ダム湖のそばにある除雪ステーションの片隅にテントを張り仮眠をとります。
朝5時に目を覚まし、行動開始です。
6:00分、登山口までやって来ました。

すでに5台ほど車が止まっています。

登山口です。ここから山頂まで10.5Km、長い戦いの始まりです。
何度か沢を渡り、笹原を歩きます。
以前は笹が登山道を隠すほどに生えていたのですが、今はきれいに刈り取られており道に迷う心配はありません。
所々ぬかるみがありますが、それも好天が続いていた影響で小さくなり靴をドロドロにするほどではありません。
快調に歩いて7:10分、沼まで来ました。


ちょっと、神秘的な雰囲気の沼です。
ここから尾根に向かってドンドン登ります。
これが少し苦しいのですが、少しの仮眠にもかかわらずメンバーは快調に歩きます。
8:35分、細い尾根まで登ってくると山頂が姿を見せてくれます。


ここまではいい天気でしたが・・・
ここから細い尾根を歩きます。
ハイ松が枝を伸ばしており、歩きづらいのですが頑張って先へ進みます。
そうすると、天狗原に上がる沢状の草付き斜面が現れます。

残雪がありますが、もう少し早い時期ですと一面が雪渓となっている沢です。
登るにしたがって傾斜がどんどん増していきます。

最後は土の登山道になるのですが、濡れていると滑るので注意が必要です。

この最後の急騰を登りきると大雪の山並みが見えています。
さあ、ここからは山容が変わり高山の雰囲気が一気に増してきます。


砂礫地の高山帯を歩くと前回引き返した地点に出ます。



ここからニペソツの山頂が見えるはずですが、雲に隠れています。
どうやら天気の具合が怪しくなってきました。


所々に咲いている高山植物のお花に癒されながら歩きます。

そして最後の下りに挑みます。


後ろを振り返るとこんな岩山です。

左手の沢を見るとここにも沢山の花が咲いています。


振り返ると天狗岳が突き上げるように見えています。
最後の急登を耐えると山頂は間近かです。
12:25分、やっと山頂に着きました。
6時間25分かけての山頂です。
しかし、辺りは雲に覆われ眺望がありません。
しかも雨が降ってきました。
雨具を着て記念写真を撮ります。

今回初めてニペソツ山の山頂を踏む2人です。
雨が大粒になり強くなってきましたので、すぐに下山します。
この下山も大変でした。
しかし、何度も休憩を取り、天狗原を降るあたりで雨がやんでくれたのは幸運でした。
アミノバイタルなどのサプリメントの力を借り、弱っているメンバーの荷物を分けて負担を軽くするなどみんなの力を結集しての下山でした。
その甲斐あって、日没寸前の19:15分に下山することができました。

現在では、この幌加コースからしかニペソツ山に登ることができません。
有志の方々によりコース整備が行われており、その努力には感謝しかありません。
ニペソツ山は、とてもいい山です。
ぜひ、みなさんも機会を作って登ってください。










































































































 左が私で右がS氏です。
左が私で右がS氏です。