
(2014.03.01訪問)
知恩院を初めて訪ねました。東山界隈はウロする回数はかなり多いのですが、ビッグが残っていたんですワ。
残念ながら御影堂は平成大修理でしばらく拝観は出来ませんが、境内は自由に歩けます。そして各所で法然
さんへの厚く深い信仰と浄土宗の宗勢の強さを感じ、とくに境内最高所に建つ法然さん廟は聖者が眠りにつ
く祈りの聖地として独特の空気感が漂っていました。
▼三門 (国宝)。
二層楼門、桁行五間三戸 (高さ24メートル、横幅50メートル)、入母屋造、本瓦葺。
元和七年 (1621年) 徳川秀忠寄進。楼上内部は、仏堂で、中央に宝冠釈迦牟尼仏像、脇壇には十六羅漢像)
が安置。

三月十八日まで、京の冬の旅「非公開文化財特別公開」で楼上が公開されています。
[ 知恩院 ]
●山号 華頂山 (かちょうざん)
●寺号 知恩院 (ちおんいん) 正式名 華頂山知恩教院大谷寺
●宗派 浄土宗総本山
●開山 法然上人 (ほうねんしょうにん)
●開創 承安五年 (1175年)
●本尊 阿弥陀如来坐像 (阿弥陀堂)。
法然上人像 (御影堂)。
▲京都市東山区林下町400 TEL.075-531-2111
▲拝観料 境内自由 方丈庭園400円 御朱印300円
▲拝観時間 4月~11月 9:00~16:30
▲市バス12・31・46・201・203・206系統「知恩院前」下車徒歩約5分
地下鉄東西線「東山」下車徒歩約8分
知恩院縁起 (知恩院HPから抄出)
法然上人の本願は「南無阿弥陀仏」と称えることにより、人々が救われるという専修念仏でした。承安五年
上人四十三歳の時、この地に浄土宗が開宗されたのです。法然上人は専修念仏を信じて比叡山を下り、吉水
の禅房、現在の知恩院御影堂の近くに住み、教えは人々の心をとらえました。しかし、旧仏教からの弾圧凄
まじく、上人の弟子住蓮、安楽が後鳥羽上皇の怒りをかい、建永二年上人は四国流罪、五年後帰京、吉水旧
房は荒廃、今の勢至堂のある場所、大谷禅房に住むことになりました。翌年、病床についた法然上人は、弟
子の源智上人の誓願で念仏の肝要をしたためます。それが「智者のふるまいをせずして、ただ一向に念仏す
べし」と述べた「一枚起請文」です。建暦二年(1212年)一月二十五日、八十歳で入寂。
▼三門扁額。華頂山と揮毫され、大きさは畳二畳以上あるそうですヨ。

▼女坂。

▼女坂の生け垣に咲くサザンカ。

▼男坂。

▼御影堂 (国宝) の今。現在平成三十年度完成を目指して平成大修理中です。御影堂に入ることは出来ません。

▼手水舎。

▼多宝塔。

▼阿弥陀堂。本尊阿弥陀如来坐像。像高270cm。桁行五間、重層、入母屋造、本瓦葺。

▼阿弥陀堂扁額。「大谷寺」と書かれた後奈良天皇の宸筆。マァ読める人は少ないでしょうネ。

▼法然上人御堂 (重文) の山門。方丈庭園はここから入ります。
御堂は桁行42.9m 梁間23.7m 棟高16.9m、入母屋造、本瓦葺。慶長十五年(1610年)建立。

▼方丈大玄関。

▼方丈庭園門。元は扉があったんでしょう、取り付け金具が残っています。

▼大方丈 (重文)。入母屋造、桧皮葺。寛永十八年 (1641) 建立。内部拝観不可。

▼小方丈 (重文)。入母屋造、桧皮葺。寛永十八年 (1641) 建立。内部拝観不可。

▼方丈庭園。南庭と北庭で構成される池泉回遊式の庭園。江戸初期、小堀遠州と関係深い僧玉淵によって作
庭されたと伝えられる庭園です。寛永十八年 (1641年) 作庭。

▼方丈庭園。

▼方丈庭園。架かる石橋は青石橋。

▼方丈庭園。東側の庭園は「二十五菩薩の庭」と呼ばれ、阿弥陀如来が西方極楽浄土から二十五菩薩を従え
て来迎する様子を石と植込みで表現したものだそうです。

▼権現堂。徳川三代を祀っています。

▼宝仏殿。本尊阿弥陀如来立像。桁行七間、寄せ棟造、本瓦葺、一間の向背付、裳階付き。
平成四年(1992年)建立の新しいお堂です。

▼宝仏殿扁額。

▼経蔵 (重文)。五間四方の宝形造、本瓦葺、裳階付き。元和七年 (1621年) 建立。宋版大蔵経約六千帖を安
置する八角輪蔵を安置しているそうです。

▼納骨堂。

▼大鐘楼 (重文)。宝仏殿裏の石段を上ったところに建っています。
入母屋造、本瓦葺。十二本の柱で70トンの大梵鐘を支えています。延宝六年(1678年)建立。

▼梵鐘 (重文)。デカイです、とにかくデカイ。
鐘高330cm、直径280cm、重量約70トン。寛永十三年(1636年) 鋳造。

▼鐘木も大きい。除夜の鐘の十七人撞きは超有名、大迫力ですネ。鐘木に巻かれた十七本の綱。

▼法然上人廟への参道。

▼参道脇のみかん殿、名はなんと申す?

▼勢至堂山門。法然上人廟への入口でもあります。

▼勢至堂 (重文)。享禄三年(1530年)再建。七間四方、単層、入母屋造、本瓦葺。知恩院最古の建造物。
この地は、法然上人大谷禅房の故地であり、念仏発祥、知恩院発祥の聖地です。

▼勢至堂内陣。中央後ろに本尊勢至菩薩坐像、前に法然上人像をお祀りしています。

▼御手水。

▼参道石段上に御廟拝殿。桁行三間、梁間二間、入母屋造、檜皮葺。宝永七年(1710年)建立。

▼拝殿からの本廟。

▼法然上人本廟。前面は唐門、後ろが本廟。法然上人遺骨を奉安する廟堂。方三間、宝形造、本瓦葺。
上人は建暦二年(1212年)この地にあった大谷禅房で入滅。その後、門弟が廟堂を建て遺骨を奉安。

▼往きは男坂を上り、帰りは女坂を下り三門を仰ぎつつ雨の知恩院を辞しました。

▼三門前から北へ行くと黒門があります。

▼黒門の前道を南へ下ると古門があります。

ちなみに三門前道の門は新門と呼ばれ、本来ここからが知恩院参道のようです。
▼御朱印です。

京に着いた途端振り出した雨はシトシトと降ったりやんだり、一番嫌な降り方、濡れながらヤケクソで歩き
回りました。京都は大体天気予報の当たらんところですか、まったく!
今日の フ ロ ク
▼古門前の白川。

▼今日の白川は水少ないです。
真鴨夫婦にエサをまいていたオバさんが云ってました、白が邪魔しに来てるんですって。

知恩院 オ シ マ イ 長々とどうも。
↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。
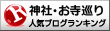 神社・お寺巡り ブログランキングへ
神社・お寺巡り ブログランキングへ












































































































