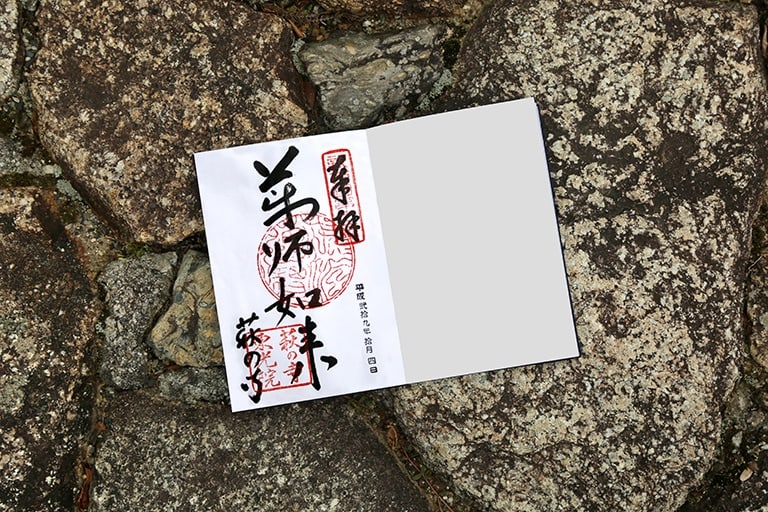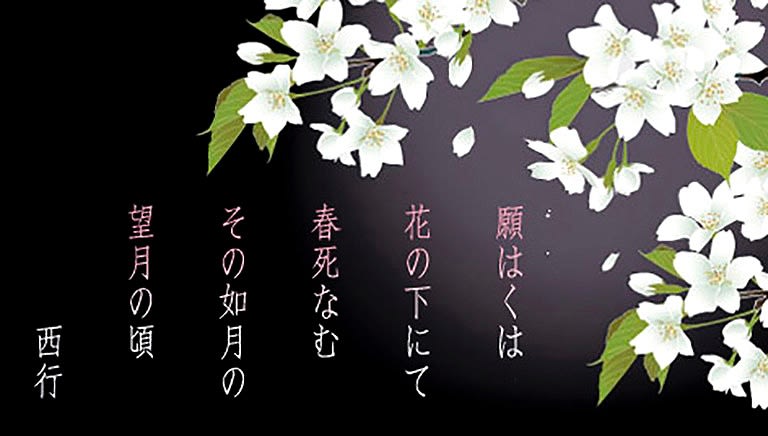(2017.10.08訪問)
坊村の明王院から坂本へ向かいます。さすが叡山のお膝元、クルマも人も溢れんばかり、次に訪ねたのは律院と云うお寺、坂本の界
隈はよく歩くのですが律院は初めての訪問、しかし訪問出来ませんでした。律院では何か大きな法要があるらしく、門外まで人で溢
れています。本堂までとてもとても行き着くことは出来ません。まして写真など論外のごとし。
よし取り敢えず腹ごしらえと日吉そばへ。そば屋へ入って鰊うどん下さ〜い。
心と腹が満たされ、さてと道路の左を見ると前方に赤い大きな鳥居が見えます。叡山鎮守の日吉大社の鳥居です。
そうだ今日は久々に神社を訪ねよう。
▼日吉大社シンボル山王鳥居。

[ 日吉大社 ]
●社号 日吉大社(ひよしたいしゃ)
●開創 崇神天皇七年 (BC91年)
●祭神
西本宮 大己貴神 (おおなむちのかみ)
大己貴神は出雲神話の最大のヒーロー大国主の別名。素戔嗚尊より五世の孫
東本宮 大山咋神 (おおやまくいのかみ)
山の地主神で農耕治水を司る神とされる。近江日枝山(比叡山)およ葛野の松尾に鎮座し、里山に鎮まる神とされる。
宇佐宮 田心姫神 (たごりひめのかみ)
宗像三女神の一柱。宗像大社では沖ノ島にある沖津宮に祀られている。
牛尾宮 大山咋神荒魂 (おおやまくいのかみのあらみたま)
白山宮 菊理姫神 (くくりひめのかみ)
白山比咩神社の祭神。菊理媛の「くくり」は「括る」に もつながり、「和合の神」「縁結びの神」として崇敬。
樹下宮 鴨玉依姫神 (かもたまよりひめのかみ)
賀茂氏の祖先とも云われている神で、神武天皇の母神玉依日売命の別名ともいわれ、八咫烏の子孫とも云われる神です。
三宮宮 鴨玉依姫神荒魂 (かもたまよりひめのかみのあらみたま)
▲滋賀県大津市坂本5-1-1 Tel.077-578-0009
▲http://hiyoshitaisha.jp
▲JR湖西線「比叡山坂本駅」下車徒歩20分
京阪石山坂本線「坂本駅」下車徒歩10分
名神高速道路 「京都東IC」から西大津バイパス(国道161号線)経由、滋賀里ランプで下車、T字交差点左折で道なり。
湖西道路「坂本北IC」から交差点右折で道なり。
▼社号石柱は旧表示そのまま。官幣大社ですよ。

日吉大社縁起 (日吉大社HPから抄出)
比叡山の麓に鎮座する当大社は、およそ2100年前、崇神天皇7年に創祀された、全国3800余の日吉・日枝・山王神社の総本宮です。
平安京遷都の際には、この地が都の表鬼門(北東)にあたることから、都の魔除・災難除を祈る社として、また伝教大師が比叡山に
延暦寺を開かれてよりは天台宗の護法神として多くの方から崇敬を受け今日に至っています。
▼社号扁額。

▼大宮橋(重文)。日吉三橋の一つで三橋の中で最も豪華な造りといいます。

▼その豪華な造りを横から見ると。

▼参道少し行くと、日吉大社シンボル山王鳥居「惣合神門」鳥居上部の合掌の形から「合掌鳥居」と呼ばれるそうです。

▼西本宮に向かう参道。

▼参道途中右手に立派な拝殿が見えます。宇佐宮拝殿(重文)です。

▼宇佐宮本殿(重文)。祭神は田心姫神 (たごりひめのかみ)
やや高い外縁に高欄を巻き、両端に阿吽の獅子が置かれています。
桁裄五間、梁間三間、日吉造、檜皮葺、一間向拝付、慶長三年(1598年)造立。

▼西本宮楼門(重文)。大社に相応しい豪華な楼門です。
重層楼門、三間一戸、入母屋造、檜皮葺、天正十四年(1586年)推定造立。

▼ご苦労さ〜ん、上層軒下四隅にお猿が屋根を支えています。「棟持ち猿」と云うそうです。

▼楼門を潜るとすぐ前に西本宮拝殿(重文)。

▼西本宮本殿(国宝)。祭神は大己貴神 (おおなむちのかみ)
縁に高欄を巻き、両端に阿吽の獅子が置かれています。
桁裄五間、梁間三間、日吉造、檜皮葺、一間向拝付、天正十四年(1586年)造立。

▼外縁両端に阿吽の獅子が置かれています。これは左側吽の獅子です。

▼西本宮本殿を中心に瑞垣が巡っています。

▼白山姫神社拝殿(重文)。四方吹き放し方三間、入母屋造、檜皮葺、慶長三年(1598年)造立。

▼白山姫神社本殿(重文)。祭神は菊理姫神 (くくりひめのかみ)
高床式の建物で縁に高欄を巻き、両端に阿吽の獅子が置かれています。
三間社流造、檜皮葺、一間向拝付、慶長三年(1598年)造立。

▼こぼれ陽が美しい東本宮に向かう参道です。

▼神木にもスポット。

▼東本宮楼門。

▼東本宮楼門を入ると左に樹下神社拝殿(重文)。
四面とも格子と格子戸のユニークな造り、外縁は高欄が巻かれています。
桁裄三間、梁間三間、入母屋造、檜皮葺、文禄四年(1595年)造立。

▼樹下神社本殿(重文)。祭神は鴨玉依姫神 (かもたまよりひめのかみ)
外縁は高欄が巻かれています。三間社流造、檜皮葺、一間向拝付、文禄四年(1595年)造立。

▼東本宮拝殿(重文)。四方吹き放し方三間、入母屋造、檜皮葺、文禄五年(1596年)造立。
石垣上に建てられているので、下から見ると屋根の稜線がまるで羽根の様、今にも飛び立ちそう。

▼東本宮本殿(国宝)。祭神は大山咋神 (おおやまくいのかみ)
桁裄五間、梁間三間、日吉造、檜皮葺、一間向拝付、文禄四年(1595年)造立。最近修復されたのか美しい建物です。

▼外縁両端に阿吽の獅子が置かれています。これは右側阿の獅子で、少々寄り目は愛嬌か。

▼東本宮楼門を出るとスグ二宮橋(重文)。日吉三橋の一つ、天正年間豊臣秀吉の寄進と伝わるそうです。

橋を渡り少し坂を上るとはじめの鳥居に、日吉大社これにて オ シ マ イ
さほど広くない境内に、これでもかとお社が並んでいます。それぞれの神様に拝殿と本殿、神社ファンには応えられないでしょう。
平安京の鬼門除け厄除けとして、叡山の鎮守として2000年を越える社歴は半端じゃありません。
魔除け厄除けの象徴神猿(まさる)として「魔が去る」「勝る」に通じ、語呂合わせ気味にお猿が大切にさているようです。
参道に本物がいましたのでおちょくりましたが、完全に無視されました。
↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。