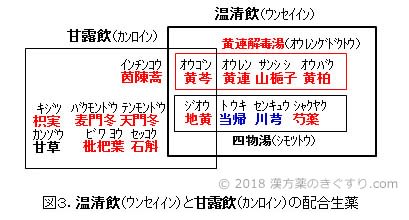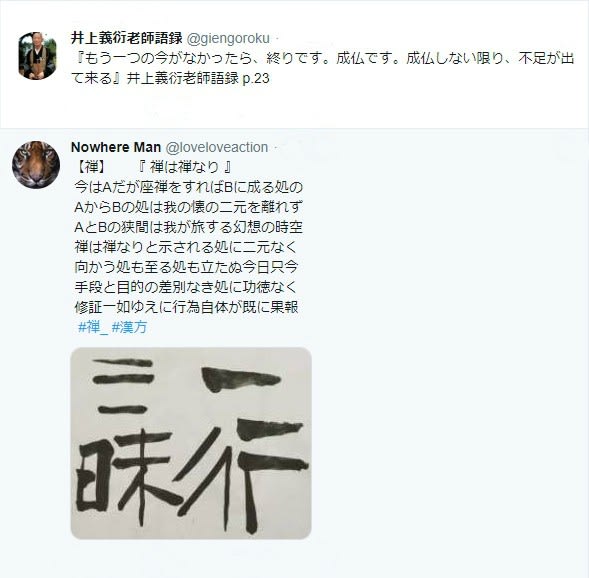次が清暑益気湯ですね。
これは、今年は非常に涼しいのであまり出ないのですが、
それでも私のところで1人だけ、ちょっと暑くなった頃にもらいに来て、
もう1カ月前から服み始めています。
「この薬を飲みだしてから大丈夫だわ」と、言って、
今日再診に来ていました。
これは補中益気湯から導かれた薬です。
物の本によっては補中益気湯の方を、
清暑益気湯に何かを足したというような書き方をしていますけれども、
本来は補中益気湯の方が先です。清暑益気湯は
補中益気湯から非常に病状を限定しやすい柴胡とか升麻を除いて、
万人向けにして滋養強壮成分を加えたというお薬です。
まだ話してはいませんけれど、
この清暑益気湯というのは五積散と逆の処方になります。
五積散の話も今まで何度か出ましたけれど、
五積散は別に冬に使う薬じやないのです。それは言いましたね。
普通の人だったらやられないような時期に
寒さでやられてしまう人が、五積散なのです。
体の表面が開いていて、外邪に侵入されやすい人です。
五積散を一番使うのは、前にも話したように5月の未頃ですね。
このような人は体の表面が完全に開きっぱなしになって、
内部の心の火がまだ燃えない小満の時期が一番弱いのです。
その前はやはり春先です。体の表面が春になって、
まだ春の気が十分巡らない時期もやはり寒さに弱いのです。
真冬には意外と五積散は使わないのです。
清暑益気湯は、どちらかと言うと夏に使うのですが、
誰だってそんな暑さの中だったらやられるよな、
というようなときにやられる人は清暑益気湯じやないのです。
あんな暑い環境、あるいはこんな暑い日が続いたらみんな参るよな、
というようなときは、どちらかと言ったら別の薬になります。
胃苓湯とか五苓散系統になってきます。
清暑益気湯はちょっと暑くなっただけで、普通の人は大丈夫なのに、
真っ先に倒れるような人に使います。
でも、前もこの話をしたと思うのですが北海道には多いです。
北海道の人は非常に暑さに弱いです。
九州にいたときは清暑益気湯はほとんど使っていないのです。
今と変わらないほど患者さんの数は診ておりまして、
今ほど難病の人ばかり診ていたわけではないのです。
逆に地域医療としては、
その地元の人みんなを診ていたような状態でした。
そういう状態でも清暑益気湯は、
一夏に2~3人ぐらいしか処方しなかったですね。
著さで簡単に倒れていたら、九州では生きていけないですからね。
だいたい夏場は30度を超すのが当たり前ですし、
ちょっと外を歩くともう35~36度、
アスファルトの照り返しの上などを測ると、40度を超すような、
そういう状態でしたね。あるいは何十日も、昼も夜も
25度以下に下がらないとか。2週間ぐらいは30度以下に下がらないとか、
そういう状態ですから、逆に暑さに強いのですね。
その代わり九州の人は寒さに非常に弱かったです。
これも前に言ったかもしれません。
九州にいるときに1人当たりに使う附子の量は倍でした。
加工附子ですけれど10グラムまで使った人がいますね。
北海道だったら加工附子で、一番多い人で4グラムぐらいです。
北海道の人は寒さに強いのです。
やはり人間の体というのは順応するのです。
その代わり北海道の人は25度を超す日が数日続くと、
夏バテの人が何人も出てきます。すべての人じやないのですがね。
でもやはり1つの地域にいるとどんどん出てきますね。
だから北海道の先生は頭で考えていたのでしょうか、
清暑益気湯は暑いときに使う薬で、
九州やそういうところで使う薬だと思っているのですね。
私が来るまでは、ほとんど
北海道で清暑益気湯は使われていなかったのです。
でも私が北海道に戻ってきた最初の夏に32度ぐらいになって、
私のいるところは33度までなったのです。
その年、冬がマイナス32度、
夏がプラス33度になってびっくりしました。
記録的な猛暑ではあったのですが、
本当に清暑益気湯は北海道に全然、在庫がなかったのです。
北海道中からツムラさんがかき集めても間に合わず、
「本社に増産をかけているから」とか言ったりしました。
それぐらいなかったのです。
でも、その次の年からは安定供給されるようになりました。
こういうときに非常にいい薬です。
今話したことはすべて、普通の人ではなくて、
どちらかと言うと太陰経が弱い人です。
でもこういう言い方をすると間違えやすいです。
内因病の時、私は太陰経が悪いという言い方をします。
太陰病とは言わないのです。
太陰経が悪いと言っている意味は、肺や脾が悪いという意味なのです。
外因病を言うときは、太陰病だとか厥陰病だとか
太陽病、陽明病と病を付けます。そこを混乱しないでください。
太陰経と言っているときは、肺や脾というのが面倒だから
太陰経が弱いと言います。
同じく肝が弱いとき厥陰経が弱いとか、
あるいは腎や心が弱いとき少陰経が弱いと言ったりします。
六経弁証の意じやないのですね。
これも何度か言ったように、真夏は本来、
心の支配になりますので、衛気も営血も心が上がります。
今年みたいに今のところ涼しいと、
心火が上がってもこんなもので済むのですが、
これがさらに暑熱で外からあぶられると、もっともっと
心火が勢いよくなります。そうすると
心の上にある肺が焼かれます。心の隣にある脾も焼かれます。
肺が水分不足になると腎水も不足していきます。
腎水が不足するとますます心火は上がります。
腎水が不足すると脾は腎から水をもらえなくなります。
脾は水をもらえない状態で心火にますます炙られるから、
全然ものが食べられなくなり、これが夏バテの状態です。
こういうところ(肺と腎、脾と腎、心と腎の関係)は五行ですが、
これ(心と肺、心と脾の関係)は五行じやないのです。解剖学的な関係ですね。
心火が上がり、熱を持ったら上にある肺が直接炙られてしまいます。
そばにある脾も熱を伝えられて参ってしまいます。
解剖学的な関係でやられてしまうのです。
もちろん、肺や脾が非常に丈夫な人だったら、
よほど無茶をしない限りやられないのですが、
もともと肺や脾がちょっと弱い人の場合は焼かれてしまうのです。
清暑益気湯というのは、そういう薬で、
普通の人はまず参らないのですが、肺や脾の弱い人が参ってしまう。
そういうときに非常によく効きます。
常日頃かかっている人が来ることもありますが、
夏バテの時期にこれだけで来る人も結構います。
普通は外来に来ないで、季節ごとにばっと来る人というのが、何人かいるのです。
例えば花粉症の時期に絶対、葛根湯加川芎辛夷が欲しいといって来る人とか、
五積散の時期にあれを欲しいといって来る人がいますね。
それから清暑益気湯を、暑くなった途端にもらいに来る人がいます。
それからテキストに書いてあるように、
今の時期に流行っているのは夏風邪ではないのです。
普通、今の時期はそんなにひどくならないのですが、
気温が上がってくれないと、
変な時期に寒邪が入ってくるので風邪をひくのです。
これは夏風邪ではありません。
夏風邪は、本当の夏の暑い時期とか、
暑い時期が続いた夏の終わりぐらいに流行り出します。
それは暑さでやられたための風部です。
これには大人にも子供にもこの清暑益気湯が非常によく効きます。
抗生剤も何もほとんど効きません。多少咳をしていようが、
多少熱があろうが、多少脱水状態であろうが清暑益気湯が効きます。
うんとひどい咳とかそういうのならば、
ちょっとまた別のことを考えないといけないけれど、
そういう意味での夏風邪の特徴というのは、
単にこわい、微熱がある、本人は風邪だと思うと言います。
食欲がないとか、もちろん寒けがしたりします。
でも、今言ったような咳とかそういう症状というのは
あまり強くないのが特徴です。でも本人は風邪だと思うのです。
現実にそういう患者さんが結構周りにいるから、
やはり伝っていくのかなという感じがあります。
あれに非常にこの清暑益気湯が効きます。
この状態のときには普通の風邪薬はいらないですね。
清暑益気湯だけでやってほとんど効きます。だから暑い時期
あるいは暑い時期の終わりぐらいに流行りだす風邪のときに、
非常に重宝して使う薬です。
第18回「さっぽろ下田塾」講義録
http://potato.hokkai.net/~acorn/sa_shimoda18.htm

https://www.kigusuri.com/kampo/kampo-care/015-2.html
[参考]:清暑益気湯